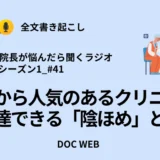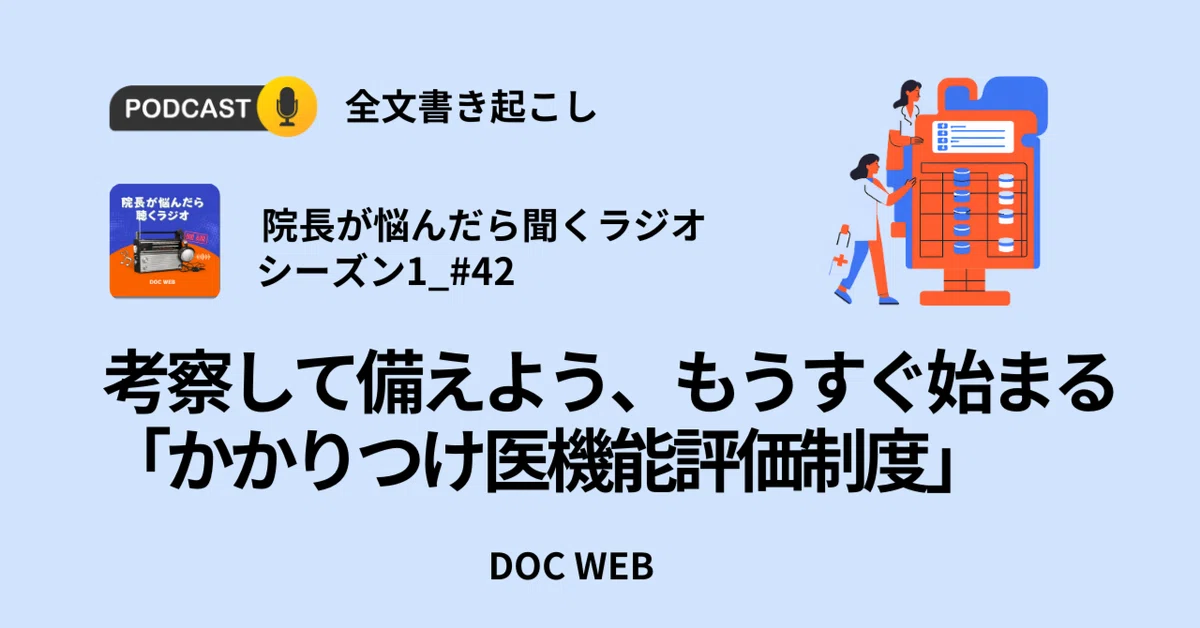
PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第42回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今日のテーマ:クリニックに関する国の動向
(高山)今日のテーマは「クリニックに関する国の動向」です。
(大西)硬いテーマですね。
(高山)前回は少し曖昧な内容というか、「陰褒め」という新しい言葉を広めようという回でしたが、今回はがらりと変わって、かなり硬いテーマです。国の動向についてお話しいただきます。
かかりつけ医機能評価制度とは?
(高山)今回のテーマは「クリニックに関する国の動向」、特に「かかりつけ医機能評価制度」について詳しくお話しいただけますか?
(大西)2025年に入り、この「かかりつけ医機能評価制度」が医療現場でざわざわしています。
(高山)ざわざわですか。
(大西)はい、ネガティブな意味で。なぜこの制度を導入するのかと疑問視する声が多いです。制度の名前から、プラスにもマイナスにも捉えられる印象ですが。
(高山)確かにそうですね。追い風なのか、向かい風なのか、どちらとも言えない。どちらかと言うと、面倒な制度になりそうな予感がしますね。
(大西)この制度が始まったら面倒だ、という声が聞こえてきそうですが、そもそも「病院機能評価」という制度が以前からありました。
病院の規模やスタッフ数、医療機器の種類、保有技術など、数値化できるデータを報告させる制度です。
(高山)はい。
(大西)ただし、これは病院向けの制度で、診療所は対象外でした。最近になって外来、そして今回「かかりつけ医」に特化した制度として導入されようとしています。
(高山)医療機関が、保有する機能や実績を国に報告し、国が医療機関の実態を把握するための制度という認識で良いでしょうか?
(大西)その通りです。実態を報告させる制度ですね。これとは別に「第三者評価制度」もあります。
「病院機能評価」は、評価団体が作成したフォーマットに基づいてチェックを行い、クリアすれば「機能評価制度認定医療機関」を名乗れるというものです。
(高山)ああ、それは聞いたことがあります。
(大西)「かかりつけ医機能評価制度」は、それとは少し違います。国が定めた「かかりつけ医のあるべき姿」というルールに対して、医療機関が自己評価を行い、その結果を報告する仕組みです。
(高山)主語が変わるんですね。
(大西)そうです。つまり、自分がどんな診療科目で、どんな病気を診ることができ、地域でどんな活動をしているのかを報告することになります。
(高山)報告した以上、その内容に沿った患者さんが来院されるわけですから、少し大げさに報告すると、自分の首を絞めることになりかねませんね。
(大西)その通りです。自己申告であるがゆえの難しさがあります。例えば、コンサルタントとしての資質を自己評価するとします。
「医療ITが得意」「医療制度が得意」「マーケティングは苦手」というように評価するわけですが、「マーケティングが得意」と報告してしまうと、マーケティングの依頼が殺到してしまいます。
不得意なことは、なるべく少なく報告するに違いありません。
(高山)確かに。
(大西)ただし、この制度では、一定の水準を満たしていないと「かかりつけ医」として認められません。
「このクリニックは、かかりつけ医としてふさわしくない」という評価につながりかねないのです。
(高山)病院選び、クリニック選びをする際に、この評価が公表されるのでしょうか?
(大西)はい。特定機能病院と歯科医院を除く、200床以下の病院と診療所が対象となります。
(高山)「かかりつけ医」というとクリニックをイメージしていましたが、病院も対象なんですね。
(大西)国としては、まずは中小規模の病院にこの制度を導入し、様子を見たいという考えのようです。
地方の医療を考える
(高山)地域のクリニックを「かかりつけ医」とする基本方針は変わらないのでしょうか?
(大西)基本的には変わりませんが、医療過疎地域などでは、地域包括ケアシステムがうまく機能していないケースもあり、必ずしもクリニックをかかりつけ医とするのが最適解とは言えない状況も出てきています。
厚労省が考える理想的な医療提供体制が、全ての地域に当てはまるとは限らないのです。
(高山)国としては、医療を全国津々浦々に行き渡らせるための仕組みづくりを目指していますが、どうしても制度に幅を持たせる必要が出てきてしまうのです。
(大西)さらに、都市部と地方の医療格差も広がっています。
地方は高齢化が進み、人口が減少しているため、医療機関の数も必然的に少なくなります。
一方、都市部は人口が多く、若い世代も多いので、医療機関の数も多くなります。まるで別の国のようです。
国は、それぞれの地域の状況に合わせた医療提供体制を構築しようとしているのです。いわゆる地方分権ですね。
(高山)なるほど。
(大西)過去10年、20年は「地方分権」や「地域包括ケアシステム」を推進してきましたが、地域によって差が出てきているのが現状です。
うまくいっている地域と、そうでない地域と差が出てきている。
うまくいっていない地域では、病気になった時に大変な事態になりかねません。
その結果、地方の人口流出が加速するという悪循環に陥っているのです。医療は、地域にとって重要なインフラです。
地方自治体の運営方法にも問題があるのかもしれませんが、医療体制の整備が不十分だと、その地域の魅力は低下してしまいます。
(高山)この制度は、いつから開始されるのでしょうか?
(大西)4月から制度の運用が開始されますが、実際のアンケート開始は11月、公表は来年になる見込みです。
医療機関検索サイト「ナビィ」で公開される予定です。ただし、患者さんがこの情報をどの程度活用するかは未知数です。
おそらく、医療機関同士が紹介先を探す際に活用されるのではないでしょうか。
医療機関の情報共有と課題
(高山)医療機関同士の情報共有は、現状では不十分なのでしょうか?
(大西)はい、医療機関同士はお互いのことをほとんど知りません。
自分の出身大学や勤務先の病院のことぐらいしか知らないのが現状です。
この制度によって、医療機関同士が学び合うきっかけになればと思っています。
きちんとしたデータベースが構築できれば、良い制度になる可能性を秘めていると思います。
ただし、情報を悪用する人が出てくる可能性や、制度への参加を拒否する医療機関が出てくる可能性も否定できません。
(高山)医療DXも、国が旗振り役となって推進していますが、参加に消極的な医療機関も多いと聞きます。
いくら良い制度を作っても、うまく機能しなければ意味がありません。
名前も少し硬いですし、「ナビィ」では医療関係者以外には分かりにくいかもしれません。
「みんなの病院」のような、親しみやすい名前にした方が良いかもしれませんね。
(大西)確かにそうですね。
真面目な人たちが作った制度なので、仕方がない部分もあると思いますが。
ネーミングに予算をかけるわけにもいかないでしょうし、広告代理店に依頼すれば、もっと良い名前になったかもしれません。
今後、CMなども必要になるでしょう。
(高山)この制度は、クリニックが進むべき方向を示す羅針盤のような役割を果たすのでしょうか?
(大西)制度の良し悪しは、実際に運用してみないと分かりません。ただ、大筋では良い制度だと思います。
「どんな診療科目で、どんな病気を診られるのか」「時間外診療、在宅医療にどのように対応しているのか」といった情報を報告させる制度なので、国が定めた医療提供体制のレールに、医療機関が乗っているかどうかをチェックするチェックリストとして機能するでしょう。
(高山)なるほど。
(大西)ただし、国の医療方針自体に疑問を持っている医療機関は、この制度に参加しない可能性があります。
ネットワーク構築の重要性
(高山)在宅医療などは、医療機関のネットワークが不可欠です。国が主導しなくても、情報共有の仕組みは必要ですね。
(大西)その通りです。「地域包括ケアシステム」「地域医療連携ネットワーク」「全国医療情報プラットフォーム」など、国は様々なネットワークを構築しようとしていますが、重要なのは、患者さんの情報を医療機関同士でどのように共有するかです。
患者さんが病気になった時に、過去の病歴をスムーズに追跡し、治療に役立てることが重要です。
因果関係を明確にすることで、より適切な治療方針を立てられるようになります。
病院と診療所が連携し、患者さんの情報を共有しながら治療を進めていくことが、ネットワーク構築の目的です。
「過去の情報は全くありません」という状況では、適切な治療を行うことは難しいでしょう。
(高山)過去の検査結果がない場合、またゼロから検査をすることになり、時間とコストがかかってしまいます。
患者さんにとっては大きな負担になりますね。
(大西)はい。多くの患者さんは、全身検査が必要なケースもあるでしょう。
以前に同じ検査を受けたことがあるのに、また検査を受けることになっても、なかなか異議を唱えることはできません。
医療費もかさみますし、患者さんは納得いかない思いをするでしょう。
もし自分が大きな病気をしたとしたら、あらゆる情報を集めて、とことん治療法を探したいはずです。
そのためにも、医療情報の整備は不可欠です。情報が不足していると、根拠のない民間療法などに頼ってしまう可能性も出てきます。
情報過多の現代社会において、国が情報を整理・精査し、患者さんにとって信頼できる情報を見極められるようにすることは、非常に重要な課題です。
この制度がうまくいくかどうかは分かりませんが、大きなチャレンジであることは間違いありません。
制度の課題と展望
(高山)現場の先生方は、この制度に対して様子見をしている方もいれば、まずは乗ってみようと考えている方もいると思います。
報告項目が100や200もあると、うんざりしてしまうかもしれませんが、そこまでは多くないのでしょうか?
(大西)そこまで多くはありません。ただ、制度設計は官僚が行うため、現場の医師からは不満の声も聞こえてきます。
「現場を知らない人たちが作った制度だ」という反発があるのです。
「地方の医療」「介護」「在宅医療」は、ネットワークが不可欠です。
そして、ネットワークを機能させるためには、情報のキャッチボールが重要になります。
情報を正しく届ける仕組みがなければ、制度はうまく機能しません。だからこそ、国はこの制度を導入しようとしているのです。
(高山)医療機関検索サイト「ナビィ」だけが全てではないということですね。
(大西)その通りです。医療における最大の問題は「情報の非対称性」です。
情報を持っている人と、持っていない人がいる。特に、医療機関は情報を持っているのに、患者は情報を持っていないという状況です。
インターネットが普及した現代では、玉石混交の情報が溢れています。国は、この情報を整理したいと考えているのです。
(高山)情報格差の是正も、この制度の目的の一つなんですね。
(大西)はい、それも重要な目的です。この制度がうまくいけば、医療費の削減にもつながります。
国の医療方針に沿って、医療資源の再配分が適切に行われるからです。ただし、個々の医療機関にとっては、面倒な制度だと感じるかもしれません。
(高山)国にとってはメリットがあっても、個々のクリニックにとっては経営的なメリットがあるかというと、必ずしもそうとは限りませんね。
(大西)それが、今の日本が抱える大きな問題点です。全体像を見て判断できる人が減り、自分や自分の周りのことしか考えられない人が増えています。
SNSの普及も、この傾向に拍車をかけていると言えるでしょう。
自分の興味のある情報しか目にしなくなっているのです。
(高山)情報が偏ってしまう危険性がありますね。
(大西)自分の知っている情報だけで全てを判断するようになると、情報に偏りが生じます。
最近よく言われるように、テレビや既存メディアにも同じことが言えます。
スポンサーの意向や、特定の有識者だけが発言する状況では、情報操作が行われている可能性があります。
私たちは、そのような偏った情報を長年見続けてきたわけです。
(高山)はい。
(大西)国は、全体像を見て医療制度を改革したいと考えてこの制度を導入しますが、うまくいくかどうかは難しいところでしょう。
時代の過渡期における一つのチャレンジと言えるかもしれません。
厚労省は「これからは医療ネットワークの時代だ。
ネットワーク構築には情報が不可欠だ。
情報を適切に流通させる仕組みが必要だ」というメッセージを発信してきましたが、「地域医療連携ネットワーク」のような従来の取り組みは、必ずしも成功しているとは言えません。
(高山)これまでのやり方ではうまくいかなかった部分を、「ナビィ」を活用することで改善しようとしているんですね。
(大西)その通りです。ただし、どれだけの医療関係者が、この制度の意義を理解しているかが重要になります。
(高山)理解していなくても、まずは情報共有の仕組みを構築することが第一歩になるのではないでしょうか。
今後5年、10年かけてこの制度を運用し、より合理的で無駄がなく、患者さんにもメリットのある医療体制を構築していくことが、日本の医療の目標です。
(大西)まさに、頭の良い人たちが作った制度ですね。頭の柔らかい人たちが作ると、SNSのようになってしまうかもしれません。
(高山)理想と現実のバランスを取るのが難しいですね。陰謀論のような極端な意見も出がちですし、最大公約数的な制度設計は容易ではありません。
(大西)InstagramやFacebookのように、医師がおすすめする医師を紹介するような民間サービスは、恣意的になりがちです。今回の制度は、そのような恣意性を排除するために作られたのだと思います。
(高山)「かかりつけ医機能評価制度」についてお話を伺いました。今後の日本の医療の方向性を示す制度として、注目していきたいと思います。
(大西)そうですね。
(高山)続きは次回にしたいと思います。大西さん、ありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。