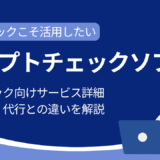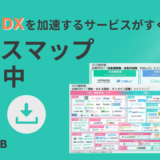PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第50回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)記念回の50回ですね。よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今日のテーマ:クリニックの近未来を予測する
(高山)今日のテーマは「クリニックの近未来を予測する」です。
(大西)良いですね。50回にぴったりの内容だと思います。
近未来の定義
(高山)クリニックの近未来についてですが、どのくらいの期間を想定しましょうか?5年、10年、それとも30年?
(大西)IT業界では、変化の速さを表す「ドッグイヤー」という言葉があり、4年で1サイクルと言われています。
4年ごとにシステムが変わるという認識で良いでしょう。今回は4年後に設定しましょう。
(高山)なるほど、ごく近い将来の話ですね。
2030年頃までを想定して、どのような変化が起こるかを予測していきましょう。
今までは治療中心でしたが、予防医療へのシフトが始まっているように感じます。
今後はどうなっていくでしょうか?
(大西)2030年は国の政策の転換点となる年です。
電子カルテの完全普及が目標として掲げられており、デジタル化が急速に進むと考えられます。
すでにデジタル化は進んでいるものの、さらに加速していくでしょう。
デジタル化が進むと、様々な変化が予想されます。
5年前のコンビニエンスストアを例に考えてみましょう。
コンビニに見る近未来像
(高山)5年前のコンビニですか?
(大西)当時のコンビニは、どこも同じような品揃えで特徴がありませんでした。
横並びの状態だったと言えるでしょう。
しかし、5年経った今では、各コンビニが独自の特色を打ち出しています。ポジショニングが明確になり、分散化が進んだ印象です。
コンビニは、これまで手を出していなかった分野に進出しています。
例えば、コンビニカフェはその代表例です。
(高山)確かに、コンビニカフェの登場で、他のコーヒーブランドは苦戦を強いられていますね。
(大西)100円で高品質なコーヒーが飲める時代になりました。
(高山)コンビニにカフェが導入され、その後はコンビニ同士のカフェ競争が始まりました。
青い看板のコンビニでは店員がコーヒーを淹れてくれます。
このように考えると、クリニックでも従来の常識では考えられないような変化が起こるかもしれません。新しい発想が求められる時代です。
(高山)コンビニは、この5年間で他にどのような変化を遂げたのでしょうか?
(大西)野菜の販売、コーヒーの提供開始、ホットスナックの種類の増加などがあります。
また、Tシャツや靴下なども販売するようになり、スーパーの領域に進出しています。
一方、スーパーは客足が減り、苦戦を強いられています。
コンビニは「便利なお店」というコンセプトを追求し、クロスセルやアップセルを繰り返すことで変化を生み出してきました。
クリニックにおける変化
(高山)レジも大きく変わりましたね。
セルフレジの導入が進み、店員の役割も変化しています。
(大西)日本語が堪能ではなくてもレジ業務ができるようになりました。オペレーションの変化です。
レジだけでなく、購買行動も変化しています。
セルフレジの普及で、会計がスピーディーになりました。
(高山)私も、最近は有人レジが空いていてもセルフレジを利用することがあります。
(大西)セルフレジの方が早いので当然ですね。
日本では万引きのリスクを考慮して、監視体制を強化することでセルフレジを運用しています。
海外では、少額の万引きは罪に問われない地域もあるようです。
例えばロサンゼルスでは、少額の万引きは捕まらないそうです。
(高山)興味深いですね。
コーヒーのサイズ問題も話題になっています。
Sサイズを注文したのに、Lサイズを入れてしまうケースなどです。
(大西)このようなコンビニの変化から、クリニックの未来像を予測することができます。
(高山)具体的にどのように参考にすれば良いのでしょうか?
(大西)5年後の未来を想像し、現在のコンビニの戦略を参考にすると良いでしょう。
昔は、総合病院がスーパーのような役割を担っていました。
様々な診療科があり、何でも対応できました。
しかし、コンビニのように、特定の分野に特化し、利便性を高めることが重要です。
内科でありながら、皮膚科の診療も行うなど、診療科の垣根が低くなる可能性があります。
「この診療科が専門です」という従来のスタイルは、変化していくでしょう。
変化の具体例
(高山)例えば、「薬だけ処方してほしい」という患者さんのニーズへの対応はどうでしょうか?
(大西)以前はグレーゾーンでしたが、患者さんは診察を受けずに薬だけを受け取りたいと考えています。
オンライン診療の活用が考えられます。受付、診察、検査なども、コンビニのように変化していくでしょう。
(高山)スーパーとコンビニの違いは、在庫数や回転率です。
(大西)クリニックの場合は、敷地面積、人員配置、サービス内容が重要です。
これらをコンパクト化し、1人でも運営できるような体制が求められます。
スーパーでは何百人もの従業員が必要ですが、コンビニは少人数で運営できています。
私も以前コンビニで働いていましたが、夜勤は1人でした。
品出し、陳列、レジ、揚げ物など、全ての業務を1人で行っていました。
(高山)すごいですね。私は2人体制でした。
12時から朝の7時まで1人で勤務していたとは驚きです。
何かあったら対応できないのではないかと心配になります。
(大西)ラグビー選手なので、体力には自信がありました。
ミニマムな思考で業務をこなしていました。
コロナの影響で、私たちの生活も大きく変化しました。
ミニマム思考が定着し、スーパーで買い物をする際も、必要なものを事前に決めて効率的に買い物を済ませるようになりました。
患者ニーズの変化
(大西)「ストア・コンパリゾン」という本を読んだことがあります。
店内の設計によって、消費者の購買行動がどのように変化するかを分析した本です。
例えば、レジ周りに電池や祝儀袋を置くことで、ついで買いを促すことができます。
食品売り場を奥に配置し、肉、魚、牛乳などの必需品を最後に購入させることで、店内の回遊率を高めることができます。
しかし、このような戦略は、消費者が買い物を楽しむという側面を無視しています。
(高山)確かに、最近は買い物を楽しむ余裕がない人が多いかもしれません。
早く帰りたいという気持ちが強くなっています。
(大西)クリニックに置き換えると、待ち時間を減らすことが重要です。
患者さんのニーズを的確に捉える必要があります。
この点で、クリニックと患者さんの間にずれが生じているように感じます。
(高山)患者さんの要求と、クリニックが提供するサービスの間にずれが生じています。
このずれを修正できたクリニックだけが生き残ることができるでしょう。
患者さんの心理状態や行動パターンは、コロナをきっかけに大きく変化しています。
この変化にいち早く気づく必要があります。
(大西)私も多くのクリニックに足を運んで、先生方と話す中で、変化を感じています。
1か月に30件ほどのクリニックを訪問し、様々な診療科の先生方と意見交換をしています。
最新のクリニックから古いクリニックまで、幅広く見ているからこそ、変化に気づくことができるのだと思います。
先生方から受ける相談内容も変化してきています。
クリニックのスタッフのニーズ
(高山)「早く帰りたい」という患者の心理以外にも、変化はありますか?
(大西)スタッフも早く帰りたいと思っています。先生も本当は早く帰りたいのではないでしょうか。
医科の会合に参加したくないという先生も多いと聞きます。また、金銭面でも変化があります。
後払いなどが普及し、患者さんは待たされることを嫌がるようになっています。
患者は受付で待たされることなく、すぐに診察を受け、診察が終わったらすぐに帰りたいと考えています。
待たせないことが重要です。
待合室は不要になるかもしれません。
レストランで予約をしたのに、30分も待たされたらどう思いますか?
予約の意味がありません。クリニックでも同じことが言えます。
まずは診察室に通し、そこで待ってもらうようにすれば良いでしょう。
診察室兼待合室のような形です。
クリニックの設備と運営
(高山)小さな診察室をたくさん作るのが良いですね。
(大西)待合室は可動式にして、必要に応じて大きさを変えられるようにすると良いでしょう。
椅子も個別式にすることで、柔軟に対応できます。
待合室は、細い廊下に椅子を並べるだけで十分です。
椅子が足りなくなったら、待合室自体をなくすことも可能です。
患者さんがクリニックに入ったときに、人がたくさん待っていると、「次回にしよう」と思ってしまうかもしれません。
(大西)予約なしで気軽に立ち寄れるクリニックが求められています。
混雑しているクリニックは、良いクリニックではないという認識が広まっています。
昔は、混雑しているクリニックが良いクリニックだと考えられていましたが、今は逆です。
混雑しているということは、待ち時間が長いということです。
(高山)最近訪れた駅前のクリニックは、まさにそのような設計でした。
待合室には丸椅子が並んでおり、必要に応じて数を増減できるようになっています。
発熱外来と非発熱外来が左右に分かれており、どちらからも診察室に入ることができます。
10分単位の予約制で、LINEで予約をしてから来院することで、待ち時間を最小限に抑えることができます。
クレジットカード決済も可能です。スムーズな流れで診察を受けることができました。
(大西)待たない、待合室がない、会計もスムーズ。これが今後のクリニックの理想像です。
オペレーションの人員も最小限に抑える必要があります。
人材不足の時代だからこそ、少ない人数で効率的に運営することが求められます。
採用が難しいという相談をよく受けますが、私は「採用しなくても良いのではないか」と答えています。
(高山)少ない人数で工夫すれば良いのです。
(大西)先日、あるクリニックでは、8人体制だった受付を6人に減らしたそうです。
その代わり、システムを導入することで効率化を図りました。
予約システム、ウェブ問診、自動精算機、キャッシュレス決済などを導入した結果、6人でも余裕を持って運営できるようになったそうです。
経営者からすると、「6人で回せるなら、もっと減らそう」という発想になるかもしれません。
人員配置の最適化
(大西)人は多ければ良いというものではありません。
むしろ、少ない方が良い場合もあります。重要なのは、どこに人を配置するかです。
ホテルでは、受付に人はいませんが、裏側ではコンシェルジュが活躍しています。
コンビニでは、物流に多くの人員を配置しています。
トラックが商品を運び、品出しを行うためです。
朝便、昼便、夜便と、こまめな配送を行うことで、在庫を最小限に抑えています。
クリニックにおけるロジスティクスは、診察、検査、処置です。
これらの業務に人員を集中させるべきです。
保険診療と自費診療の変化
(高山)他に変化の兆候はありますか?
(大西)保険診療の比率が下がり、自費診療の比率が上がっていくでしょう。
保険診療のルールには限界があります。自費診療に移行できるものは、国としても歓迎するはずです。
また、受付の無人化も進むでしょう。
そして、オンライン診療の比率も高まっていくと考えられます。
(高山)オンライン診療は使いにくいという声も聞きますが、どうすれば良いでしょうか?
(大西)電話ボックスのような個室を作り、オンライン診療専用の部屋にすれば良いでしょう。
先生はオンライン診療が終わったら、すぐに外来の診察に戻ることができます。
オンライン診療は、患者を待たせることなく、スムーズに行う必要があります。
「こんにちは」と挨拶をして、患者の話を聞き、必要があれば看護師に交代すれば良いでしょう。
薬を処方するだけなら、1~2分で十分です。
現状は、オンライン診療に時間をかけすぎている傾向があります。
(高山)オンライン診療はまだ新しい制度なので、慎重になりすぎる傾向があります。
国も様子見の状態でスタートしたため、クリニック側も真面目に取り組まざるを得ません。
そのため、多くのクリニックは自費診療としてオンライン診療を提供しています。
(大西)自費診療のオンライン診療は、厚労省はノータッチなんで。
直美(ちょくび)という選択
(大西)「直美」という言葉をご存知ですか?
直接、美容クリニックに行くことを指す言葉ですね。
大学病院に残らず、直接美容クリニックに就職する若い先生が増えています。
美容クリニックで経験を積んで資金を貯め、その後開業するという流れです。
彼らは、ベンチャー企業のような発想でキャリアを築いています。
(高山)直美を経て、保険診療を行うクリニックを開業するという戦略ですね。
(大西)大学病院に勤務していては、なかなか資金が貯まりません。
役職に就けば給与は上がりますが、その分仕事も増えます。
まずは美容クリニックで資金を稼ぎ、その後自分の専門分野で開業するのが賢明な選択です。
まとめと次回予告
(高山)このような先生が増えている中で、近未来のクリニックは、自費診療中心、コンパクト化、効率化、オンライン診療の導入などが進むと予測されます。
患者ニーズを捉え、効率的なクリニックを作っていくことが重要です。
(大西)今から5年前に火がついたこの流れは、今後5年間で完成形を迎えるでしょう。
5年後には、また違った話をしていると思います。
(高山)今回は「クリニックの近未来予測」についてお話しました。次回は、今回の話を踏まえて、「こんなクリニックがあったら面白い」というテーマで話をしたいと思います。
(大西)分かりました。よろしくお願いします。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。