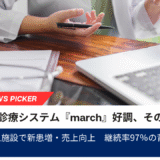PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第62回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今回のテーマ:学習する組織づくり(ベクトル合わせ)
(高山)今日のテーマは、前回に引き続き「学習する組織づくり」です。
(大西)前回話した内容の中から、今回は「ベクトル合わせ」という話をしたいと思います。
前回は心理的安全性、つまり活発にコミュニケーションが取れて会議で話ができるような組織が良いという話でしたが、今回は方向性を合わせないとチームとしてまっすぐ走れない、という話をしていきたいです。
(高山)それではこの後、ベクトルを合わせていく秘訣について語っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
(大西)お願いします。
ベクトルが合っていないチームの典型例
(高山)学習する組織づくりというテーマで、今回は「ベクトルをどうやって合わせていけばいいのか」「そもそもベクトルとは何か」「そういった意識はどうすれば作れるのか」といった話をしていきたいと思います。
大西さん、まず、ベクトルが合っていないチームの典型例を教えていただけますか?
(大西)組織ができた時、必ずその組織にはベクトル、言い換えれば「同じ方向性」があります。
これが合っていないと、様々なコミュニケーションの断絶が起こります。
例えば、院長が言ったことにスタッフが従わなかったり、言われたことと違うことをしたりします。
また、よかれと思ってやったことが全く意図と違った、というように歯車が噛み合わないことがよく起きます。
歯車を合わせるためには、まず大まかな方向性だけでも決めておくと良いと思います。
例えば、ものすごく早く立ち上げるフェーズなのか、今は基盤を固めるフェーズなのか、それとも組織を作るフェーズなのか。
様々なフェーズによって、走り方もスピードも変わってきます。
これもベクトルの1つです。
よくあるのが、先生1人だけが頑張っていて、スタッフは頑張っていないように感じてしまうケースです。
これはベクトルが合っていない状態です。
(高山)そうですね。スタッフ一人ひとりは「自分は頑張っている」と思っているわけですが、よく言われる「残念な人の行動」というものがあります。
チームのベクトルと違う方向に一生懸命走っても、なかなか成果には繋がりません。
まるで「一人だけ違う方向を向いて頑張っている」という状態になり、全く報われない行動になりがちです。
そんな状況が起きていたら、ベクトルが合っていないということですね。
なぜベクトルを合わせる必要があるのか?
(大西)そうです。私はずっとラグビーをやってきたのでよく分かるのですが、一つの目的はトライをすることでも、一人ひとり役割は違います。
スクラムを頑張る人、パスを出す人、ボールを蹴る人、それぞれ役割は違いますが、ベクトルが合っていれば同じ方向へ進んでいけます。
しかし、ベクトルが合っていないと呼吸が合わなくなります。
「なぜスクラムを頑張らないんだ」「なぜパスをちゃんと放らないんだ」といったマイナス面が出てきてしまいます。
ですから、ベクトルが合っていないチームほど、前回お話ししたように愚痴や不満が出やすくなります。
(高山)なるほど。「こんなに頑張っているのに評価されない」と感じたり。
ベクトルが合っている人から見ると、むしろ力を抜いているように見えてしまうこともありますよね。
(大西)私もサラリーマン時代は、部下をそのことでよく叱っていました。今思えばナンセンスでしたね。
「なぜ頑張らないんだ」と言っても、頑張り方は人それぞれです。
(高山)そうですね。「頑張る」の定義は難しいですが、ビジネスや目的のあるチームにおいては、成果を出す必要があります。
(大西)そこの大前提として、組織にはプロフェッショナル集団と、様々なレベルの人が集まった寄せ集め集団の大きく2種類があると考えた場合、寄せ集めの集団であればあるほど、このベクトルが大事になってきます。
レベルが一定ではない組織ほど、ベクトルがないと前にまっすぐ進めません。
一方で、プロ野球選手やプロサッカー選手のように、ある一定以上のレベルの集団であれば、そこまで気にしなくても機能したりします。
(高山)彼らは分かっていますし、「勝利するために」という目的がもともと明確だからですね。
(大西)あとは、これまで培ってきたものがあるからです。
以前の回で新卒採用や未経験者採用の話をしましたが、そういった背景からも、どうしてもこの「ベクトル合わせ」が必要な時代になってきていると感じます。
(高山)常に必要なことではありますよね。
レベルの高いチームであってもベクトルのすり合わせは必要ですし、色々考えられるが故に、考えすぎて違う方向に行ってしまう選手も出てくるでしょう。
だからこそ、チームのリーダーが常にベクトルを示し続けることが大事だと思いますが、ベクトル合わせの一番の必要性は何でしょうか。
(大西)ベクトル合わせの必要性は、その船が沈没しないためです。
(高山)沈没したら困りますね。
(大西)みんなで漕ぐ船ですから、ベクトルが合っていなければ方向を間違うし、岩にぶつかるかもしれません。
旗を振る役のリーダーがいて、漕ぐ役の船頭や船員がいて初めて船は進みます。
旗を振る人もいなければ、誰も漕がないのでは沈没してしまいます。
(高山)なるほど。目標に向かってそれぞれが力を合わせるためにベクトル合わせが必要だということですが、肝心のベクトル合わせは、どのようにすれば良いのでしょうか。
ベクトルを合わせるための具体的な方法
(大西)まず、ベクトルとは何かを定義すると良いでしょう。これは「理念」にあたります。
まずは理念を、朝礼や定例会議、年に1回の方針発表会などで、そういった場で必ず触れてほしいと思います。
理念をただ唱和しているチームがありますが、私はあまり好きではありません。
「理念、何々何々」と唱えるだけでは、全く心がこもっていません。
理念に基づいたエピソードを話し合う時間も必要です。
例えば、「当院の理念は笑顔を大切にすることです」とします。
その理念について、「どんな時に笑顔の大切さを感じましたか?」という問いかけをし、それに対して「患者さんとやり取りしている時」「困っている患者さんからお礼を言われた時」といったエピソードを交えないと、理念は血肉化していきません。
理念にエピソードを足す、ということをしています。
(高山)より具体的に理念を落とし込むということですね。
(大西)そうです。もう一つ大事なのは、今の現状を包み隠さず話すことです。
リーダーが、「今は患者さんを増やすフェーズです」「今は患者さんが増えすぎているので、待ち時間をどう減らすかというフェーズです」というように、現在のフェーズをきちんと話してあげると、スタッフも「なるほど」と納得できるのではないでしょうか。
(高山)そうですね。私もよく思うのですが、リーダーが見ている景色と現場のスタッフが見ている景色が異なっていると、同じベクトル合わせができていたとしても、情報の粒度が違ったり、優先順位が合っていなかったりします。
そういったことが生じないように、リーダーは常に自分が見ている景色を共有すると良いと思うのですが、クリニックの中でそうした機会を設けるのは難しい気もします。
リーダーが心掛けるべきこと
(大西)取りづらいですね。朝礼をしない、会議をしない、ましてや方針発表会などしないというクリニックがほとんどです。
その理由は、「意味がない」と思っているからかもしれません。
例えば、朝礼が単なる報告・連絡・相談の場になってしまったり、会議をすると院長の独演会になってしまったり。そういうことに、なりがちです。
だから、一度はやってみたけれど諦めてしまった、というケースも多いようです。
(高山)諦めずにやり続けるということでしょうか。
(大西)最初に「設計する」ことが大事だと思います。
私たちは、朝礼を「何をする場所か」と定義づけることが必要だと考えています。
朝、クリニックに来て、みんなの顔色や状態を確認する場であり、今日一日をどう過ごすかを考える場です。
そして、今年一年間の中の一日なのだということをすり合わせる場だと、私は考えています。
毎日同じ日などないはずなのに、毎日が同じ日だと勘違いしている人が多いように感じます。
(高山)リーダーとフォロワーでは役割も違いますし、全員がリーダーと同じ気持ちでいられるなら良いのですが、同じ景色を見ても感じることは人それぞれ違います。
そう考えると、多少の差異や理解度の違いに関しては、ある程度目を瞑るというか、許容する範囲があっても良いのかなと思いますが、そのさじ加減は難しいですよね。
(大西)難しいですが、スピードを例にあげると、リーダーが速く走るとします。その時、後ろを振り向かないといけません。
リーダーが圧倒的に前を行ってしまい、振り返ると誰もついてきていない、という組織をよく見ます。
それに対して、立ち止まる。振り返る。ゆっくり走る。これはリーダーがやらなければいけないことだと思います。
(高山)リーダーとしては焦りも生じますよね。
(大西)だから、「このままだと黒字化できない」と思うと、焦って暴走しがちです。
私もそうでした。ただ、その時に振り返れたら、あるいは少しジョギングするくらいのペースに落とせたら、また違っただろうなと、これは私の反省からも感じます。
(高山)そうですね。そういった意味で、定期的に場を設けて、できるだけベクトルを合わせる努力をするということですね。
何かコツはありますか?
前向きな発言と改善提案がコツ
(大西)前回の復習も兼ねてお話ししますが、コツは、リーダーは全て前向きな発言に徹することです。
リーダーが愚痴を言ったり弱みを見せたりすると、そこに付け込まれるというか、組織全体がそうなってしまいます。
リーダーはどんなに辛くても弱音は吐かず、前向きな発言しかしない。
一方で、スタッフの立場からすれば、これはリーダーだからという話ではなく、いずれ自分がリーダーになる時のための話なのです。
リーダーは院長だけではありません。看護チームのリーダーもいれば、事務チームのリーダーもいます。
いずれ誰もがリーダーになるものだという考えで、この前向きな精神が伝播していってほしいです。
あとは、「言いたいことが言えない」という点について、少し誤解している人がいます。「言いたいこと」は、別に悪口ではありません。
(高山)そうですね。
(大西)「気になることをちゃんと言えない」という状況で、その気になることが「〇〇は駄目だと思います」という否定だとすれば、それは残念な話です。
「こんな良いことがありました」というのも言いたいことでしょうし、「ここをこんな風に直したい」という改善提案は、非常に前向きだと私は思います。否定する提案ではなく、改善提案をしてほしいと話しています。
(高山)コツは前向きな発言ということですね。
(大西)前向きな発言と、改善の提案です。
愚痴や不満がある時に「どんどん言ってくれ」という先生がたまにいますが、言われる方は辛いですよ。
ですから、不満や愚痴は発生する前に解消しておきたいものです。
溜め込まないで。
(高山)そうですね。そういったものは個別にワンオンワンで聞いたりとか。
観点が違うから、そういったことが起きてしまうわけですね。
(大西)すれ違いがほとんどですよね。「そういうつもりはなかったのに」というような。
その辺りのすり合わせも毎朝の朝礼でやっておくと、良いなと感じます。
(高山)そうですね。
(大西)もう一つのコツは、「今日は今日しかない」と伝えることです。「昨日と今日は一緒だと思うなよ」と。
今日は今日、明日は明日です。
一日一日、きちんと気持ちを切り替えてきてほしいのです。
「今日を良い一日にしましょう」という話をしています。
(高山)なるほど。それだけでも、かなり前向きなイメージになりますね。
(大西)これを最初に宣言するだけで、一日が清々しくなります。
「なぜ大きな声で『おはようございます』と言わなければいけないのか」と思うかもしれませんが、小さな声では清々しくなりません。
ただ、もともと声が小さい人は「なぜ強要されなければいけないんだ」と感じるでしょうから、自分の精一杯で良いので、朝一番に声を出す。
それによって良いスタートが切れます。そういったことをやり続けること、つまり「続けること」がコツでしょうね。
(高山)そうですね。しっかり設計をして、目的意識を持って継続していく。
ベクトル合わせを諦めずに、ぜひ院長の先生方には実践していただきたいです。
(高山)ということで今回は、学習する組織づくりの第2項目目として、「ベクトルをどうやって合わせていくのか」という話をしてきました。
続きは次回にしたいと思います。大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。