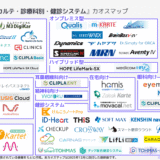PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第68回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今回のテーマ:お薬
(大西)テーマはずばり「お薬」です。
(高山)お薬ですね。今回はお薬について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いいたします。
骨太方針における「OTC類似薬」とは
(高山)ということで、今回は骨太方針その3、お薬ということですが、OTC類似薬について解説をお願いします。
(大西)医療費を削減したい国は、毎回診療報酬改定で医薬品関連の費用を下げてきています。ただ、ここに来て、もう下げることが難しくなってきているんですね。
その理由は、薬不足が深刻化し、薬がうまく流通できなくなっているためです。
また、物価高のせいで原材料の輸入価格が非常に高騰しており、薬の利益がほとんど出ない状態になっています。
おそらく薬価はもう限界まで来ていると考えられます。そうなると、薬の値段を下げるという政策が行き詰まります。
ではどうするかというと、薬関連で医療費を下げるもう一つの方法として、「市販で売られている薬は市販で買ってもらう」つまり処方箋から外すという考え方が出てきます。
これがOTC類似薬です。要は、市販のOTC薬と似ている成分のものは、できるだけドラッグストアなどの市販で購入してもらい、調剤薬局やクリニックでもらう薬は、それ以外のものにしようという動きが出てきたわけです。
(高山)この取り組みは、かなり以前からOTC医薬品で進められていましたよね。
(大西)ずっと前から「スイッチOTC」ということで、処方箋薬をどんどん市販薬に切り替えてきました。
有名なところではロキソニンやアレグラなどですね。こういった花粉症の薬や痛み止めの薬は、ドラッグストアで販売しても良いことになりました。
なぜOTC医薬品は普及しないのか?湿布薬の例
(大西)しかし、この政策を進めても、すべてが市販薬に切り替わるわけではありません。
なぜなら、クリニックで処方してもらった方が1割負担などで済むため、患者さんにとっては安いからです。
(高山)患者さんからすれば「安い」という話になってきますよね。
(大西)その通りで、患者さんからするとドラッグストアでは買わなくなってしまう。
(高山)思い当たる節があります。
(大西)ですから、いくら進めても医療費削減には繋がらないのです。
例えば、その代表例が湿布薬です。湿布薬は、細かい話は省きますが、1割負担なら1枚10円程度、場合によってはもっと安く買えてしまいます。
最大で63枚、9袋分も処方してもらえる。これが1割負担で手に入ると、ほとんどタダ同然の非常に安い値段で、湿布薬を常備薬として家に持って帰れてしまうわけです。
(高山)9割引ですからね。
(大西)一方で、ドラッグストアで買うと定価で購入しなければなりません。
(高山)定価か、よくて2、30%オフくらいでしょうか。
(大西)そうなると、やはり処方箋でもらおうとなりますよね。
(高山)まるでバーゲンセールのように見えてしまいますね。
(大西)見えてしまいます。つまり、同じものでもクリニックに受診すれば安く手に入るわけです。
(高山)もちろん、基本料として受診料がかかるので、相殺してどうなるかという点はありますが。
(大西)それでも安く買えるので、患者さんは待ってでもクリニックや薬局へ買いに行くわけです。
国が検討する具体的な対策
(大西)国としては、この状況にメスを入れたい。ではどうすればいいか。
いくつか考え方があり、例えば「どちらか一方でしか売れなくする」とか「どちらかの値段を高くする」といった案が検討されました。
その中で出てきたのが、OTC類似薬を処方箋の対象外にするという議論です。
(高山)これは、製薬メーカーにとっては死活問題ではないですか?
(大西)いえ、製薬メーカーとしては、おそらくどちらでも良いのかもしれません。
(高山)販売量が一定だとすれば、どこで売れるかの違いでしかないと。
(大西)そういうことですね。ただ、製薬メーカーも今の時点で経営は非常に厳しい状態です。
さらにややこしいことに、この種の薬はほとんどが後発品(ジェネリック)であり、先発メーカーはあまり関心がないという問題もあります。
本当に管理が難しい薬や、まだ治験が必要な新しい薬は処方薬であるべきですが、発売から30年、40年経っているような薬は、もう調剤薬局ではなくドラッグストアで買えるのだから、そちらで購入してください、というように患者さんの意識を変えようとする政策と言えますね。
(高山)この「OTC類似薬」という言葉ですが、以前は「OTC」だったように思います。この「類似薬」という部分で、範囲が広がるのでしょうか?
(大西)いくつか案が出ていますが、まず一つは、調剤薬局で処方できる量を減らすという方法です。
例えば、今は3ヶ月分まとめて処方してもらえることもありますが、これを「1ヶ月分しか出せない」というルールにする。
もし3ヶ月分出す場合は「リフィル処方箋」という制度を使いますが、これは薬局では受け取れてもクリニックへの再診は不要、というルールを定着させたい意図が裏にはあります。
そうすると、できるだけ薬は薬局でもらい、クリニックには行かないという流れができます。
これだけでクリニックの受診料が下がるため、医療費は削減されます。
(高山)なるほど。
(大西)このOTC類似薬をリフィル処方箋の対象に限定すれば、わざわざOTC類似薬をもらうためだけにクリニックへ行く人が減るというわけです。
(高山)クリニックに行かずにバーゲンセールで買えるなら、余計に欲しくなるということもありそうですが。
(大西)その可能性もありますね。患者さんにとっては、その方が都合が良いかもしれません。
ただ、国はさらに厳しい策も検討しています。「選定療養費」という、一部を保険、一部を自費とする混合診療を認めるルールを拡大しようという動きです。
(高山)ほう。
(大西)これを利用すると、診察は保険、薬は自由診療となり、OTC類似薬の自己負担が10割になる、というような政策も考えられています。
(高山)どんどん蓋が閉まっていく感じですね。
(大西)こうなると患者さんは、「長時間並んで薬をもらっても自己負担が高いなら、薬局で買った方が安いし早い」と考え、クリニックには行かなくなるだろう、という狙いです。
この2つの策をうまく融合させていくのだと思います。
医療現場が抱える課題と懸念
(大西)先日、医師の方々にヒアリングしたところ、「OTC類似薬の中でも、市販に移行しても良い薬はある」という意見でした。
代表的なのは湿布薬や痛み止めなどです。しかし、国が今問題視しているのは糖尿病や高血圧の薬です。
高血圧の患者さんの薬までOTC類似薬で良いとなると、「副作用の管理は大丈夫か」という懸念の声が上がっています。
(高山)医師の監督のもとでOTC類似薬を服用する、といった世界になるのでしょうか?
(大西)血圧の推移を毎回管理するのは、薬が適切かどうかの確認だけでなく、副作用をチェックする意味もあります。
患者さんが薬局で薬をもらう際に服薬指導を受けますが、今、調剤薬局は非常に混雑しています。
(高山)確かに。
(大西)その中で適切な確認がなされず、情報が抜け落ちてしまう可能性があります。
現状でも、報連相(報告・連絡・相談)が不十分だったり、説明が足りなかったりするケースがあります。
そして、何か問題が起きた時に責任を問われるのは、処方箋を出した医師なのです。
(高山)うーん。
(大西)そんなリスクを考えると、医師としては「クリニックに来てほしい」と思うわけです。
さらに問題なのは、OTC類似薬が増えると、医師が患者の服薬状況を把握しにくくなる点です。お薬手帳には、基本的にOTC薬は記載されません。
(高山)確かにそうですね。
(大西)我々は問診で「熱が出た時に何の薬を飲みましたか?」と尋ねますが、患者さんが市販の風邪薬などを服用していると、我々がこれから出そうとしている薬と成分が重複してしまうことがあります。
このように、OTC類似薬の導入は、やればやるほど医師の負担を増やす側面があるのです。
(高山)「これを飲んでしまったのか」という事態が起こり得ますね。
(大西)いつもは「市販薬は飲まずに、我々が出す薬を飲んでください」と指導するのが一番シンプルです。
しかし、これが「この薬は薬局で、この薬は我々が」という形になると、薬局で適切な説明がなされなかった場合にトラブルが起き、その責任がすべて医師に来てしまうのです。
(高山)ドラッグストアで買ったものは、あくまで自己責任という形で責任を分けたいところですが、そうはいかないのですね。
(大西)処方元であるクリニックと、処方を受ける患者さんとの間の信頼関係が、現状では少し曖昧です。
その曖昧なまま制度を進めるからこそ、トラブルが起きるのではないかという怖さがあります。
今後の展望と医療現場のホンネ
(高山)そもそもOTCは処方箋を出しませんよね。
(大西)出しません。だから、処方箋を出さないものに医師は責任を持ちません。しかし、患者さんはそうは考えません。
「この薬を飲んで調子が悪くなったのですが」と相談されれば、医師は対応せざるを得ず、どんどん困ることになります。
(高山)管理が難しくなりますね。
(大西)そうした副作用の管理が必要な薬までOTCに拡大してしまうと、難しい問題が出てきます。
事故が起きる前に、しっかりとしたガイドラインを作ってほしい、というのが医療現場の思いです。
OTC類似薬を進めようという勢いは理解できますが、様々なことをきちんと考えてほしい、というのが現場の気持ちですね。
(高山)国としては、薬だけをもらいに来るという患者さんの行動をやめさせたいわけですね。
(大西)そうです。だから、もっと根本的な問題として、診察をせずに薬を出す「無診投薬」を行っている医療機関に対して、もっと厳しく対応していくべきではないかという意見もあります。
その代表例が「湿布だけもらいに来る」患者さんです。内科や精神科で湿布が大量に処方されている現状は、少しおかしいですよね。
(高山)なるほど。まずは、そうしたあるべき姿ではないところから是正していくということですね。
すでにもうOTCになっているものから手をつけていくと。
(大西)その通りです。「これはもう市販でいいよね」「医療機関で出さなくてもいいよね」と、すでに定着しているものからまず対象にしていくのが第一弾。
そして第二弾でリフィル処方の活用。根本のベースにあるのは「医療機関に行く患者を減らしたい」という思いです。
(高山)色々考えていますね、厚労省も。
(大西)考えていますが、一番気をつけなければいけないのは、骨太の方針も財務省の案も、すべては「こうしなさい」というトップダウンの指示だということです。
これに対して厚労省がどこまで実行するのか、そして現場が受け入れられる形にするために、これから日本医師会などと相談して決めていくことになります。
次のステージはその議論になるので、そこがまた読みどころですね。7月から、いよいよ次期診療報酬改定の話が始まります。
(高山)そうですね。骨太の方針が出された後、それがどこまで「骨抜き」になっていくのか、そういった議論がスタートするわけですね。
(大西)元々の「何のためだったか」という目的がずれないでほしいと思います。
(高山)議論を進めるうちに、方向性が変わっていくこともありますからね。
(大西)はい。
(高山)また骨太方針について、まだ項目がいくつか残っていますので、続きは次回にしたいと思います。今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。