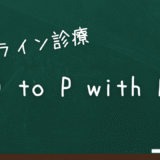PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第73回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか。
今回のテーマ:トレンドは「事業承継」
(高山)今日のテーマはクリニック開業のトレンドでいきたいと思います。
(大西)最近の開業には様々な流れがあると思いますが、その中の一つのトレンドとして、事業承継や第三者承継が挙げられます。
まっさらな状態から開業するのはなかなかハードルが高いため、そういった流れが出てきているのかなという感じがしますね。
(高山)そうですね。一昔前と開業スタイルが変わってきたということで、そのあたりを本日聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
(高山)クリニック開業のトレンドが最近変わってきているということですが、全くの新規開業をする先生は少し減ってきて、どちらかというと事業承継のスタイルが増えている、そんな感じなのでしょうか。
(大西)そうですね。日本の構造的に言うと、開業に適した場所がだんだんなくなってきているという背景もあります。
(高山)立地的にですか。
(大西)立地的にです。一方で、長年開業されていた先生が代替わりを迎える際に、後継者がいないという問題が顕在化しています。
そこで、後継者を探そうという流れが生まれているのだと思います。
(高山)場所は既にあるけれど、引き継ぐ人がいないという状態ですね。
(大西)そうです。以前であれば息子さんや娘さんに引き継いでいたのでしょうが、この少子高齢化の時代では、なかなかそううまくはいきません。
少し話がずれるかもしれませんが、医師は比較的、晩婚化の傾向があり結婚が遅いんですよね。
(高山)ええ。
(大西)そうなると当然、子供ができるのも遅くなります。すると、いざ事業を引き継ぎたいというタイミングで、お子さんがまだ大学生であるといったケースも出てきます。
そういった事情で、引き継ぎが難しいというケースもありますね。
(高山)なるほど。同族承継ではなく、第三者の先生を見つけて継承していくということですが、事業を継承したいというニーズは高まっているのでしょうか?
買い手側の本音:「しがらみは不要、でも患者は欲しい」
(大西)売りたい側は、確実に事業を継承したいと考えています。しかし、買いたい側は、あまりしがらみを求めてはいません。
(高山)ほう。
(大西)クリニックの建物(器)や場所は欲しいけれど、それ以外の部分はゼロから作りたい、というのが本音ではないでしょうか。
(高山)なるほど。気持ちとしては新規開業に近いけれど、クリニックの建物や患者さんは引き継ぎたい、ということですね。
(大西)その通りです。開業する時に一番怖いのは、「患者さんが来てくれるかどうか」じゃないですか。
もともとあったクリニックであれば、確実に患者さんが来てくれることが保証されている。そこだけに保険をかけたい、という気持ちなのでしょう。
(高山)そうですね。自信がある一方で、不安もあるという感じですかね。
(大西)ええ。私自身、医師ではありませんが、会社を作るときに一番不安だったのは「売上がずっと続くのか」ということでした。
どれくらい顧客を獲得できるか、すごく心配でしたからね。その部分が保証されていると、やはり楽ですよね。
(高山)楽ですよね。ある程度自信がなければ開業も独立もしないでしょうが、集患はマーケティング活動になるので、ゼロから集めるのはリスクが伴います。
(大西)マーケティング活動をほとんどしなくていいというのは、経営者としてはかなり楽なはずです。
(高山)そうですね。仕事の大半がそこでしょうから、最初からその負担がないのは楽ですよね。
(大西)そうです。
(高山)一方で、事業承継をすると、自分のブランドをゼロから作り上げるのが難しくなるということはありませんか?
開業の動機も変化:「安定」を求める医師たち
(大西)そこも最近のトレンドだと思うのですが、自分でブランドを作りたいから開業するというよりは、安定したいから開業するという道を選ぶ人が増えています。
(高山)ほう。それは、勤務医だと安定しないということですか?
(大西)勤務医の場合、大学に所属していると様々な病院へ転籍させられる、いわゆる「異動」があります。
あるいは当然、出世競争もあるでしょうし、能力がなければずっと平のままです。
最近の傾向として、上の世代がどんどん抜けていくので、若くしてすぐに組織の「長」になってしまうこともあります。
そうなると、責任がかなり重くなります。
また、今の病院は独立採算制を取らなければならないところが多く、業績に対してかなり厳しく言われるのが実情です。
(高山)なるほど。
(大西)そうした状況を、自分の裁量でコントロールしたいと思った時に、開業という選択肢が出てくるわけです。
もしかしたら開業した先生方は、勤務医を続けるより開業する方が簡単だと感じているかもしれません。
(高山)なるほど、そうですよね。これは大企業と中小企業の関係にも似ていて、ビジネスの世界でも同じことが言えると思います。
大きな組織にいると、大きな売上目標が課せられたり、自分の思い通りに進められないのに収益は確保しなければならなかったり、そういった矛盾を感じることがありますよね。
(大西)そうですね。私もサラリーマン時代はまさにその矛盾を感じていました。
大きな業績を上げても給料が増えるわけではないのに、業績を上げれば上げるほどスタッフが増え、売上とスタッフに対する責任だけが重くなっていく。そうすると精神的に参ってしまいますよね。
(高山)それなら自分でやった方がいい、という話になりますよね。
(大西)ええ。開業して10年も経てば、また色々と大変なこともあるのでしょうが、開業して10年経った先生方にお話を聞くと、「最近は結構楽しいよ」とおっしゃる方が多いですね。
(高山)ほう。
(大西)むしろ勤務医の先生の方が、少しお疲れになっているような印象を受けます。
(高山)大変そうなのが、なんとなく分かります。開業のスタイルがそのように変化しているのは、医師個人のキャリアに対する考え方が変わってきているからなのでしょうか。
医師像の多様化:経営者としてのキャリアパス
(大西)そもそも、医師を目指す人たちのタイプも変わってきているように感じます。
(高山)医師を志望する段階で、考え方が変わってきていると。
(大西)そうです。もともと医師の家系に生まれたお子さんは、親の跡を継ごうかという気持ちが少しはあるかもしれませんが、親の側は「別に継がなくてもいいよ」と言っているケースも少なくありません。
人は自分の人生を考える時、周りの人を参考にしますよね。ですから、参考にする対象が医師だから医師になる、という層がまず一つあります。
次に、サラリーマン家庭に生まれ、何かのきっかけで医師になる人たち。
この人たちは大きく二つに分かれます。
一つは「経営者」として医療というマーケットを見ているタイプ。もう一つは「社会貢献」として医療を見ているタイプです。
社会貢献を志向する人たちは、例えば国境なき医師団に参加したりします。
一方で、経営者として医療を見ている人たちは、経営者になるための近道として医師という職業を選んでいるので、一つのクリニックに留まらず、二つ、三つと拡大していく志向を持っています。
そう考えると、同じ医師であっても、そのスタイルは多様化してきているのだなと感じますね。
(高山)昔ながらのクリニックの先生というと、ご自身のクリニックを一つだけ持ち、そこで一生を終えるというイメージがありましたが、最近は経営者として分院展開や多店舗展開をしていくという思考の先生が、昔よりも増えているという感じですか。
(大西)そうですね。元々の、言葉を選ばずに言えば「赤ひげ先生」のような地域密着型のドクターは、開業して儲けようという意識はあまりなかったはずです。地域に貢献したい、という思いが強かった。
今の先生方は、もちろん地域に貢献したいという思いを持つ方もいる一方で、最も潰れるリスクの低い業態が医療機関である、という視点で考えている人もいるのではないでしょうか。
(高山)そうですね。最初からそのように考えて医師を目指す人は少ないかもしれませんが、もともと医師という職業に興味があった人が、ビジネスの思考も取り入れている、という感じでしょうか。
(大西)ええ。だから、たまに先生方から「コンサルタントをやりたいです」と言われることもありますよ。
(高山)ほう。
(大西)理由を尋ねると、「そういう分野に興味がある」と。一度コンサルタントを経験してからもう一度開業すれば、もっと良い経営ができるかもしれないと考えて、そちらの勉強をしたいという方もいます。
(高山)戦略コンサルのようなイメージですね。
(大西)そうです。マッキンゼーやアクセンチュア、ボストン・コンサルティング・グループのような会社に入ってから開業する先生もいます。
(高山)私の身近でも何人かそうした先生がいますので、昔よりビジネス志向の方が増えているというのは、その通りなのでしょうね。
今後の開業で考えるべきポイント
(高山)事業承継を活用してリスクを抑えつつ開業する人が増えていること、そして分院展開などを視野に入れる経営者タイプの先生が増えているということですが、今これを聞いている先生の中にも、これから開業を考えている方がいるかもしれません。
今後、例えば立地、診療科目、経営のスタイルや規模など、どのような目的で開業すると良いか、これから考えていく上でのポイントとなるような指標があれば教えていただけますでしょうか。
(大西)「失敗しないためにはどうするか」という視点が非常に大事だと思います。
成功する方法については誰もが語りますが、失敗した経験は隠したがるものです。
(高山)ええ。
(大西)しかし、成功の裏には必ず失敗があります。逆に言えば、失敗さえしなければ必ず成功するのではないか、と考えています。
少し失敗例なども交えながら考えてみると、例えば、まず考えなければいけないのが「法人」にするか「個人」のままいくか、という点です。
(高山)ほう。
(大西)もし開業してすぐに法人になりたいのであれば、法人の事業承継しかありません。個人の場合、必ず個人の実績がないと法人にはなれないからです。
(高山)ほう。
(大西)ただ、法人格は売買されることも多いので、手っ取り早く法人になる方法として、法人格を買ってそこの理事長や理事になる、というやり方もあります。
(高山)なるほど。
(大西)その際に、持ち分があるかないかといった点も考えなければなりません。
また、最近先生方からよく質問されるのは、「何科だったら上手くいくか?」ということです。これも一つのトレンドかもしれませんね。
(高山)それは、ご自身の専門科目は一旦置いておいて、成功しそうな診療科目を選ぶ、といったこともあるのですか?
(大西)標榜科目は自由に選択できます。例えば、ご自身は内科医だけれども皮膚科もやりたいという先生は、「内科・皮膚科」として開業し、皮膚科の先生を外部から呼んでくる、ということも可能です。
(高山)ああ、なるほど。自分以外の先生を呼べば、確かに可能ですね。
(大西)そうです。そして皮膚科の方が強くなれば、ご自身は経営に専念していく、という形も取れます。
ですから、診療科目は必ずしも自分の専門領域で、というのが当たり前ではなくなってきています。最近はその考え方も変わってきているかな、という印象です。
他にも、立地に関してもコロナ禍を境に考え方が変わってきていますし、目指すべき売上規模も変化しています。
(高山)ええ。
(大西)ですから、「こうすれば成功する」という決まったやり方が通用した時代は、もう終わりつつあるのだと思います。そのあたりを、これからしっかり考えていく必要がありますね。
(高山)なるほど。時代が変わってきているからこそ、医師のキャリアの考え方も変わってきている、ということかもしれませんね。
今後、これから開業しようとしている先生へのアドバイスとして、転ばぬ先の杖という意味で、後半戦ではそのあたりを詳しくお聞きしたいと思います。
(高山)ということで、続きは次回にしたいと思います。大西さん、ありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。