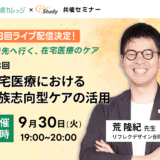PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第75回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか。
今回のテーマ:診療科目
(高山)今日のテーマはクリニック開業のトレンド、診療科目編です。
(大西)診療科目は選ぶのが難しいですし、将来どうなるかというのもなかなか読めないところなので、開業において結構大事な選択肢かもしれませんね。
(高山)そうですね。この後、最近はどのような診療科目の開業が多いのか、また将来的にどんな診療科目が良いのか、そういったことをお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
開業トレンドの診療科目
(高山)診療科目についてですが、開業のトレンドや傾向として、最近はどのような診療科目が最近増えていますか?
(大西)私の肌感覚ですが、診療内科、精神科が増えている気がしますね。
(高山)昔よりも増えているというイメージでしょうか。
(大西)元々、それほど多くはなかったのだと思います。あんまり。ですから、例えば自分が病気っぽいなと思っても、診療内科や精神科に行くということに対してハードルが高かったんですよね。
(高山)患者にとって、ですよね。
(大西)患者にとってです。だけど最近はすごく身近になってきていて、「プチうつ」なんて言葉があるように、意外に増えているというか、開業しやすい診療科なんです。
最近増えている「精神科・診療内科」とその理由
開業しやすい理由①:医療機器が少なくコストを抑えられる
(高山)開業しやすいというのは、どのような点でしょうか?
(大西)医療機器がほとんどないという点です。
(高山)確かに、そういうイメージはあまりないですね。問診して、話を聞いて処方するというのがメインの活動なのかなというイメージです。
(大西)そうですね。ですから、あったとしても採血があって心電図を取るぐらいです、検査は。他の科に比べると開業コストが安いんです。
(高山)レントゲンの機械などもいらないと。
(大西)いらないです。
(高山)なるほど。超音波もいらないし。
(大西)エコーも内視鏡もいらないです。
(高山)では、電子カルテと心電図計、測定器があれば開業できるわけですね。
(大西)そうです。血液検査も外注ですから、それもいらない。
(高山)そうすると、クリニックの広さ、箱の大きさも抑えられますね。マンションの一室で開業しているのもよく見かけます。
(大西)そうですね。ですから、本当に30坪とかで開業できるんじゃないかなと。
僕がお手伝いしているところが少し大きめの精神科が多いので30坪ぐらいですが、20坪でもいけると思いますよ。
(高山)そうですよね。20坪で開業できたら、そんなにリスクではないですもんね。
開業しやすい理由②:ニーズの増加と治療法の確立
(大西)あと、精神科を目指す人たち、先生方が増えたんですよね。
(高山)それはなぜなんでしょうか。ニーズが増えてきているからですかね。
(大西)まず、臨床心理士とか公認心理士といった心理士が結構人気なんです。
当然、ドクターで精神科を選ぶ人も増えてきました。なぜかなと思った時に、病気の整理がだいぶついてきたのかなと。
精神科・診療内科は、これまでは何かもやっとした病気が多かったのですが、かなり細分化されてきたりしています。
(高山)確かに、20年前ぐらいの精神科や診療内科というと、少し医者の中でもアウトローではないですけど、「エビデンスはあるのか」といった懐疑的な見方が多い状態だった気がします。
しかし最近は、だいぶ解明されてきたというか、経験が重なって治療法として確立されてきている感じなのでしょうか。
(大西)そうですね。あと、お薬がすごく良くなってきていて、副作用が少ないお薬が増えました。
(高山)薬は大事ですね。
(大西)あとは、コロナの影響がすごく大きいと思います。
(高山)どういう影響があったのでしょうか?
(大西)新型コロナが流行してから、うつ病っぽい症状の方が増えています。それから、戦争の影響も大きいらしいですよ。
(高山)日々、そういったニュースに接するから、ということですか?
(大西)そうです。戦争の画像を見るとパニックになる人が出てきています。
(高山)患者側のニーズも高まってきていて、薬も副作用が少ないものが出てきているので、治療として標準化が進んでいるという感じですかね。
(大西)そうですね。これまで病院で診ていた疾患が、かなり開業医で診られるようになっていますし、最近は在宅とか訪問看護の分野でも精神科が伸びているので、開業のバリエーションが増えてきている感じです。
(高山)そうなのですね。ただ、患者さんの中では、私の周りもそうですが、やはり精神科に通うことへのハードルは未だにありますし、「薬漬けにされてしまうのではないか」といった、昔の漫画じゃないですけど、そういったイメージはまだまだ払拭されていないかなと思いますが、最近はどうなんでしょう。
(大西)いや、若い人が多いですね、受診する人が。もう10代、20代です。例えば、自分が物忘れがひどいとなると「ADHDじゃないか」と相談に来る人とか。
あとは、お子さんだと自閉症スペクトラムという病気とか。そういった患者さんが増えてきているので、かなり低年齢化しているかなという感じがします。
(高山)なるほど。そのあたりの情報は、子育て世代の間でよく出てくる情報ですよね。
SNSなどでも流れてくるので、今まで心配しなかった人たちも心配しがちというか。
(大西)そうですね。精神科は、儲かる・儲からないというより、ある程度患者数さえ見込んでおけば、結構安泰な診療科なんです。
アップダウンが少ない科でもあります。
(高山)繰り返し来院されるということですかね。
(大西)そうです。1回来たら月に1回は来られます。
(高山)患者さんは、だいたい何人ぐらいですか?
(大西)ライン的には、1日30人を超えてくればいいんじゃないでしょうか。
他の科に比べると1日の外来患者数も少なくて済むというのも良い点ですね。1人あたりの単価が高いので。
(高山)1人あたりに費やす時間もそれなりにありますよね。
(大西)ただ、初診は長いですが、再診は5分なので、それほどでもないです。
(高山)クリニックを開業して、精神科や診療内科だと、先ほどの話にもありましたが、それ以外にも少し軽いタッチで、患者さん側もそんなに重く考えずに「不調を感じるから行ってみようかな」というように、ハードルが低くなっている感じなのでしょうか。
(大西)そうですね。また、働きたいスタッフも増えてきています。ただ、一つ気をつけなければいけないのが、元々そういった疾患に興味のある人は、ご自身も同じような疾患を持っている可能性があるということです。
どっちが患者か分からない、というスタッフさんもいます。
(高山)そういうパターンも見受けられるのですね。
(大西)ですから、私たちがいつも言うのは、診療内科・精神科の場合はスタッフ選びが一番大事だということです。
もう一つのトレンド「皮膚科」
(高山)他に何か特徴的な動きはありますか?
(大西)皮膚科が増えてきているな、という感じがしますね。
(高山)皮膚科というと、どちらかというと若い方々が美容への意識が高く、できるだけ医療で解決したいというニーズが高まっているのかなと想像しますが、どうでしょう。
(大西)そうですね。あとはアレルギーとかアトピーですね。そのあたりが増えています。
(高山)アトピーの患者さんとか、そういった患者さん自体が増えているのか、あるいは意識が高まって通院する人が増えているのか、私もデータを持ち合わせているわけではないので分かりませんが。
(大西)アレルギーを持っているお子さんは多くなっていますね。あとは、確かに昔に比べると、ニキビの患者さんですごく気にする方も増えていますし、大人になってくるとシミとかそばかすを消したいとか。
このあたりも結構増えてきているので、若い人も増えていますけど、年配の方も増えている感じがします。
(高山)皮膚科だと、やはり自費診療と並行して開設する先生が多いですか?
(大西)そうですね。皮膚科も、先ほどの診療内科・精神科と同様に医療機器が少ないんです。
レントゲンがないので。ですから、美容を手がけない先生方は、それほど医療機器は必要ありません。顕微鏡ぐらいです。
ただ、美容系に力を入れている先生はレーザーを買うので、それは結構な金額になります。
(高山)なるほど。皮膚科だと、アルバイトの先生が日替わりで来るようなパターンも想像してしまうのですが。
(大西)そうですね。最近問題になっている「直民(ちょくみん)」の問題もありますから、直民の先生方はとりあえずアルバイトに行ってノウハウをマスターしますからね。確かに、アルバイトの先生はよく見かけます。
(高山)あと、皮膚科は女医さんが多いですよね。
(大西)そうですね。ある意味、小さく始められるというのも大きいのかもしれません。
開業のキーワードは「費用の抑制」
(高山)皮膚科も、開業費用を抑えられそうなイメージがありますね。
(大西)これが一つのキーワードでしょうね。開業費用を安く抑えられる診療科が選ばれてきている。
それぐらい物価が高くなってきているので、「最初にドカンと投資したくない」という雰囲気がありますね。
(高山)そうですね。内装費用もそうですし、人件費もそうですし、昔より必要な金額が大きくなってきていますよね。
(大西)人も採るのが大変ですし、機械を買うのも大変です。ましてや院内薬局もほとんどないので、初期投資をかなり安く抑えなければいけないのですが、ふと気づくと結構高くなっているんですよね。
「内科」のトレンド:二極化する開業スタイル
(高山)他の診療科目はどうですか?
(大西)内科も安定して増えてはいるのですが、大きく二極化している感じがします。
一つは、内科と小児科を合わせたような「ファミリークリニック」をやりたいという先生。
もう一つは、消化器や循環器などに特化した検査をやりたいという先生です。
ですから、普通の風邪を診るような、ただの内科というクリニックは少なくなりました。
多分、調べてみたら分かると思うのですが、「〇〇内科」というよりも、「ファミリークリニック」とか「総合内科」といった名前が増えてきているかなという感じがします。
(高山)かかりつけ医としての受け皿を担おうと考えて開業される先生が多くなってきているのですね。
(大西)そうですね。内科の先生は、もれなく在宅医療も伸ばしていけるので、在宅ニーズも考えると、内科はやはり開業しやすい診療科なのかなと思います。
(高山)まさしく、家族全員を診ていくという立場になるわけですね。
(大西)そうです。子どもの頃から診ていて、亡くなるまで看取る。プライマリーケアからターミナルケアまでですね。
ただ、そう考えて在宅医療を始めたものの、やめてしまう先生もいるんです。しんどいんですよね。
(高山)開業してから、違うスタイルに変えていくということですか?
(大西)そうです。例えば、ファミリークリニックとして始めたけれど、近隣に小児科ができて患者さんを取られてしまうとか。
あるいは、在宅もやる気でいたけれど、実際にやってみたら24時間365日仕事をしなくてはならず、ちょっとしんどい、といったケースです。
そういったことを考えると、やはり専門に特化している先生の方が、実は内科はうまくいっている感じがしますね。
(高山)専門性を持ちつつ、それを強みとして生かしながら、患者さんへの入り口は広くしておく、という感じでしょうか。
(大西)そうですね。一昔前に、大学病院などで「総合医」という科ができましたよね。
何でも診る科ですが、その先生方が開業してみると、強みが弱いんです。
(高山)逆に分かりづらいのかもしれないですね、患者さんにとっては。「何でも来てください」と言われても。
(大西)そうそうそう。何でも診ますよ、と言うのですが、診た後は紹介状を書くことになるので、患者さんがリピートしていかないんです。
(高山)入り口としては良いのかもしれませんが、確かにそうですね。原因を解明するのが仕事、という側面もありますからね。
(大西)そうです。ですから、患者さんにうまく定着してもらうには、例えば糖尿病に特化した医療機関とか、消化器特化、循環器特化というように、何回もリピートしてもらえる科の方がいいのかなと。
消化器も、大腸内視鏡や胃カメラをやりますし、点数が高い大腸内視鏡を強みにしていくことができますからね。
ただの「内科」というクリニックは減りました。逆に、「私はこれが強みです」と言える先生が伸びています。
「整形外科」のトレンド:承継開業が主流の理由
(高山)整形外科はいかがですか?
(大西)整形外科は、数としてはほぼ変わらないと思いますが、新しく整形外科を始める先生よりも、お父様の代から息子さんや娘さんの代に引き継がれているケースが多いですね。
(高山)なるほど。
(大西)これは一つ特徴的なのですが、おそらく整形外科は一番、代々続けていくのが良い診療科なのかな、という感じがします。
(高山)それはなぜですか?
(大西)おそらく、町に整形外科があって、そこに高齢者のコミュニティができて、ぐるぐる回っていく、という構図があるからです。
先代がいて、息子さんが帰ってきて「良かったね」というような、すごくコミュニティ化される診療科なんです。
(高山)歌舞伎の世界みたいですね。
(大西)そうそう。「代々続く整形外科」みたいな科が、やはり伸びています。
整形外科の難しいところは、その地域に一つあると、結構独占するような形になりやすく、競争が難しいんです。エリアは狭いのですが。
患者さんの層が60代から90代だとすると、その中でも特に高齢の方は在宅医療に移行しますし、常に新しい患者さんを獲得していく必要があります。
その中で、「整形外科」というもののブランディングが、「地域に一つ」「町に一つ」といった形になりやすい。あとは、開業費用が高いですね。
(高山)設備がたくさん必要ですもんね。
(大西)設備もそうですし、人も多く必要です。
(高山)リハビリのスタッフの方も多いですもんね。
(大西)そうです。ですから、開業時のスタッフ数が一番多いのが整形外科なので、それを一から集めることを考えると、承継した方がスタッフも引き継げる、ということなんですよね。
(高山)なるほど。開業のしやすさという点で障壁があるので、承継したり、全くの新規でゼロから始めるのは難しい診療科なのですね。
(大西)先ほどのマーケティングのケースで言うと、競合がめちゃくちゃ強いところがあると、不思議なことに、整形外科は混めば混むほど、どんどん混むんです。
(高山)へえ。
(大西)これはおそらく、「みんなが行っているところに行きたい」ということなんでしょうね。「あそこは良いよ」と聞いたりして。
高齢者の方は、症状が「肩が痛い」「腰が痛い」「膝が痛い」のどれかで、これで9割だそうです。
そして、治療法も注射、薬、リハビリとある程度決まっていて、ある意味フォーマット化された高齢者の方が多いわけです。
そうすると、同じような流れで、みんな同じクリニックに行くのかな、という感じがしますね。
(高山)治療方針に関しても限られていますし、やはりご本人でないと分からないかもしれませんが、年を重ねると変化をあまり望まなくなりますよね。慣れているところでずっと診てもらいたい、と。
(大西)そうです。それに、駐車場も広くないといけないし、建物も大きくなくてはいけないので、そもそも土地がない、という問題もあるのかなと思います。
(高山)適切なスペースを確保するのも、最近は難しいですよね。
(大西)私が整形外科のお仕事をしていると、いつも古い整形外科がリニューアル、リニューアルを繰り返しているケースが多いなと感じます。
(高山)面白いですね。
(高山)面白がってはいけないかもしれませんが、診療科目ごとにそういった特性があるんですね。
将来を見据えた診療科目の選び方
(高山)大学を出て資格を取り、30歳ぐらいまで修業して、自分の専門性を磨いていくわけじゃないですか。
そうなると、その専門性を生かして開業、という流れになると思うので、そこから考え始めると遅いということですよね。
(大西)そうです。自分の10年後、20年後に開業すると決めているのであれば、20年後の人口動態を見ておいた方がいいのかなと。
どういう社会になっていそうか。今の若い先生は開業が早いので、10年間ぐらいのスパンで考えていると思います。
(高山)それを踏まえて、もう大学時代から専門性をどうしようか、と考え始めた方がいいんですね。
(大西)そうです。一つの選択肢として、ご両親が開業医の先生は、親のクリニックを継ぐかどうかを決めなければいけません。
継がないのであれば、診療科は別のものを選んでもいいわけです。その時に、患者が増えそうな科、ニーズが増えそうな科を選ぶのか。
それとも、逆張りで、衰退しそうだけれども、みんなが選ばない科を選んだ方がいい場合もあります。
もし開業するのであれば。そういったのも一つのやり方かもしれません。
(高山)逆張り戦略、みたいな。
(大西)そうです、逆張り戦略。あとはエリアですよね。前回やりましたけど、何県で開業するか、何市で開業するか。これも結構大事な要素です。
今、みんなが自分の地元に帰るかというと、そうでもないですからね。
(高山)確かに、日本自体が狭くなってきていますし、移動手段も発達しているので、常に一緒にいなくてもいい、という状況が促進されていますよね。地元に帰らずに過ごすというパターンも。
(大西)そうですよね。あとは、10年後にはオンライン診療なんかもっとできるようになっているでしょうし。
ですから、10年後を考えると、オンライン診療がやりやすい科がいいのかな、という感じがしますね。
さっきの整形外科や皮膚科は、オンライン診療はちょっと苦手なんですよね。患部を触らないと分からないので。
一方で、診療内科・精神科はオンライン診療にすごく向いているので、ここはやはり伸びると、みんな踏んでいるんでしょうね。
(高山)ということで、今回は診療科目の最近のトレンドについてお伺いしてきましたが、診療科目によって傾向性がはっきりと違うな、という印象を受けました。
ぜひ、これから開業を目指される先生も、10年後、あるいは20年後ぐらい先を見据えつつ、検討していただければなと思います。
ということで、続きは次回にしたいと思います。大西さん、ありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。