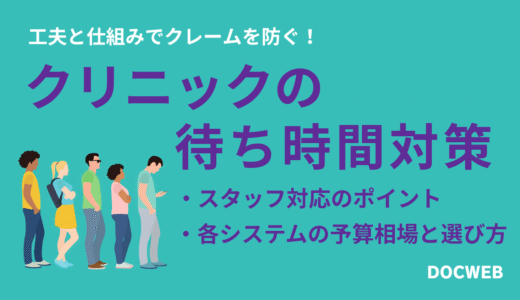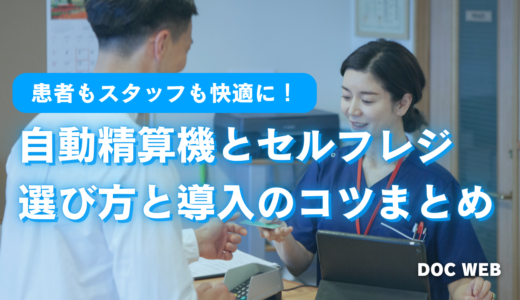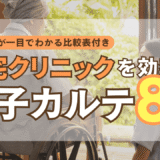PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第83回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
受付無人化時代における事務スタッフの書類作成業務
(高山)今日のテーマは、前回に引き続き、「受付無人化時代」の業務フロー設定についてです。
今回は特に、事務スタッフが作成すべき書類に関して、深掘りしていきたいと思っています。
(大西)書類作成は、いくら無人化を進めても、どうしても残ってしまう業務ですよね。
私自身も書類作成は得意ではないので、
嫌だなと感じる仕事ですが、それを嫌がらずにこなしてくれる人がいるのは、非常にありがたいことです。
そんなお話ができればと思います。
(高山)それでは、事務スタッフの書類作成・提出について、深掘りしていきましょう。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
クリニックにおける多種多様な書類作成業務
(高山)事務スタッフの書類作成業務というと、我々二人とも苦手分野ではありますが、そもそもクリニック内では、どのような書類を作成する必要があるのでしょうか?
(大西)まず、保険制度上、必要な書類があります。
レセプトはもちろん、各種届け出などもそうです。
その他、自治体や生命保険会社などに提出する書類もあります。
これらの書類は、毎日作成するもの、月に一度のもの、年に一度のものなど、締め切りも様々です。
最近では「データ提出加算」のように、データを提出することでお金がもらえる制度や、「ベースアップ評価料」のように、スタッフの給与改定を報告することで評価される制度など、手続きが面倒なものが増えてきています。
先生方は、そうした手続きが面倒で敬遠しがちですが、そこを事務スタッフに任せられると、非常に助かるわけです。
(高山)そういった書類を地道に作成・提出していくことは、人件費と比べて、きちんと採算が取れるものなのでしょうか。
(大西)書類作成が得意な人が1人か2人いれば、十分に採算は取れます。書類作成を嫌がらない人がいることが重要です。
できれば2人いると理想的ですが、誰もいない場合は、無理にやらない方が良い可能性もあります。
書類作成業務の属人化とデジタル化の課題
(高山)長年勤めているベテランスタッフが、経験を基に書類作成を一人で抱え込んでしまい、新人には教えずに自分でやってしまう、というケースも多いのではないでしょうか。
(大西)そうした人がコツコツと作業しているのを横で見ていると、「Excelのマクロを使えば自動化できるのに」と思うこともあります。
(高山)ただ、都度発生するようなイレギュラーな書類作成業務を、その都度システム化するのは難しいですよね。
(大西)例えば「データ提出加算」のように、3ヶ月に一度、定期的に発生する業務であれば、各メーカーも作成支援ソフトを開発するなど、仕組み化が進んでいます。
しかし、「ベースアップ評価料」のように、一度提出したら終わり、というような書類のためにマクロを組んでも、あまり意味がありません。
パソコンが苦手で作業が遅い、という人もいますし、そもそも紙に丁寧に字を書くのが苦手、という人もいます。
早く紙媒体がなくなればいいのに、と個人的には思っています。
昔の就職活動では、手書きの履歴書が必須でした。あれは本当に嫌でしたね。間違えたら一から書き直しで。
(高山)緊張しながら書いて、最後の最後で失敗すると、また書き直し。非常に時間がかかりました。
(高山)あれは、応募者の事務能力を測るための一つのテストだったのかもしれません。
(大西)字の綺麗さ、マス目にきちんと収まっているか、曲がっていないか、など、手書きの履歴書からは様々なことが読み取れます。
(高山)紙文化の時代には、それが必要なスキルだったのですね。
デジタル化の波と「マニュアル読解力」の重要性
(大西)そして時代はデジタル化へと進み、自治体の書類なども含めて、あらゆるものがデジタル化されようとしています。
そうなると今度は、ExcelやCSV、Wordといった形式の書類が増えてきます。
(高山)特にExcel形式は多いですね。ただ、たまにCSV形式で、と言われると、それが何なのか分からない人もいるでしょう。
Excelで作成してCSV形式で保存すれば良いだけなのですが、カンマ区切りやタブ区切りなど、形式がいくつかあって、どれを選べばいいのか分からない、ということも起こります。
(大西)いずれにせよ、紙の時代からデジタルの時代へと移り変わっても、「締め切りがあり、提出先が決まっていて、フォーマット通りに作成しなければならない」という本質は変わりません。
今、一番求められているのは、「マニュアルを読む力」かもしれません。
(高山)特に役所などが作成するマニュアルは、細かくて分かりにくいことが多いです。
一生懸命読んでも、どういう意味なのか理解できない、ということもあります。
(大西)文章を作成する側が、少し意地悪な書き方をしている場合もあります。
私は診療報酬の読解を仕事にしていますが、「なぜこんな書き方をするのか、誤解を生むだろう」と感じることも少なくありません。
(高山)事務スタッフの方々は、書類作成だけでなく、診療報酬の算定などにおいても、まずはその根拠となる「書類(マニュアル)を読む力」が非常に重要になってきているのです。
(大西)インプットとアウトプットで言うと、インプット、つまりマニュアルを読み解く時間の方が圧倒的に長い。
アウトプット、つまり書類を作成する作業自体は、それほど大変ではありません。しかし、1枚の書類のために10ページのマニュアルを読まなければならないとなると、多くの人が苦手意識を持ってしまいます。
役所文化というか、彼らが欲しいものと、我々が提出したいものには、どうしてもズレが生じます。
「なぜこんなものを出さなければならないんだ」とイライラしながら作業するから、仕事がしんどくなるのです。
(高山)一方で、自分の仕事だと割り切って、時給で働いている人の方が、かえって落ち着いて取り組めるのかもしれません。
AI時代における書類作成の未来
(高山)今後、AI、特に生成AIが進化すれば、バラバラのフォーマットで作成された人間の文章を読み込んで、自動的に転記してくれるようになるかもしれませんね。
(大西)マニュアルを1ページに要約する、といったことはAIにもできるでしょう。
しかし、マニュアルというのは、各項目に対応するコメントが紐づいているため、単純に要約してしまうと意味が通らなくなってしまいます。
マニュアルを分かりやすい日本語に翻訳する、といった使い方は有効かもしれませんね。
AIにマニュアルを学習させ、難しい書類の作成をサポートさせる、という未来はあり得ます。
(高山)「ここの項目はどういう意味?」と質問すれば、AIが答えてくれるようになれば便利ですね。
(大西)それが人間を介さずにできるようになれば、本当の意味でAIを使いこなせていると言えるでしょう。
(高山)そうなれば、自分の持っているデータをアップロードし、「このマニュアル通りに書類を作成して」と指示するだけで、AIが作業を代行してくれるようになるかもしれません。
(大西)近い将来、そうしたことが可能になるでしょう。しかし、現時点ではまだ難しい。
(大西)だからこそ、「受付無人化時代」の過渡期である今、書類を正確に転記できたり、マニュアルを読み解いたりできる人材を、事務スタッフとして確保しておく必要があるのです。
ただ、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIの導入には、まだコストがかかりすぎるという問題もあります。
先日も、軽く100万円はかかると言われ、まだまだクリニックレベルでは導入のハードルが高いと感じました。
(高山)パッケージ化されていれば良いのですが、現状では人件費と比較して考える必要があります。
(大西)しかし、月給という形で支払われている人件費は、具体的なコストとして見えにくい。
もしかしたら、システムを導入した方が、結果的に赤字になってしまう可能性も否定できません。
これからのクリニックに求められる人材とは
(高山)こうした環境の変化によって、クリニックで揃えるべき事務スタッフに求められる能力も変わってきている、という印象を受けました。
(大西)次回は、これからのクリニックが揃えるべきスタッフ、つまり、どのような能力を持った人材を採用すべきか、という点について、お話ししていきたいと思います。
(高山)大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
少しでも気に入っていただけましたら、番組のフォローをぜひお願いします。新しいエピソードがいち早く届きます。
番組への感想はハッシュタグ「#院長が悩んだら聞くラジオ」をつけて投稿いただけると励みになります。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
- 院長の理念と思いやりの心を行動で届けることができる、おもてなし力の高い個人とチームを育成する研修プログラムを提供
- クリニックにふさわしい応対の流れを創るロールプレイを多用した研修
- ホスピタリティにあふれた高品質の接遇を提供していきたいクリニックにおすすめ
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。