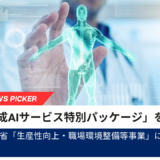PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第48回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何ですか?
今日のテーマ:チーム医療 患者を「様」づけから「さん」づけへ
(高山) 今日のテーマは「チーム医療」です。
(大西) 「チーム医療」というと、少し古い話になりますが、「患者様」と「患者さん」という呼び方の話から始めたいと思います。
1990年代には、患者様と呼ぶのが一般的でした。
しかし、2000年代に入ると患者さんと呼ぶようになりました。
この辺りがチーム医療のターニングポイントだったのではないかと思います。
今日はそのことについてお話しできればと思います。
(高山) ありがとうございます。
「患者様」「患者さん」という違いが、チーム医療にどう影響していくのか、興味深いですね。
今日もよろしくお願いします。
(大西) よろしくお願いします。
チーム医療における患者の役割
(高山) 今日のテーマは「チーム医療」です。
(大西) 「チーム医療」というと、少し古い話になりますが、「患者様」と「患者さん」という呼び方の話から始めたいと思います。
1990年代には、患者様と呼ぶのが一般的でした。
しかし、2000年代に入ると患者さんと呼ぶようになりました。
この辺りがチーム医療のターニングポイントだったのではないかと思います。
今日はそのことについてお話しできればと思います。
(高山) ありがとうございます。
「患者様」「患者さん」という違いが、チーム医療にどう影響していくのか、興味深いですね。
今日もよろしくお願いします。
(大西) よろしくお願いします。
チーム医療における患者の役割
(高山) では、「チーム医療」についてですが、大西さんの考えでは、患者さんもチーム医療に含まれるのでしょうか。
私のイメージでは、医療従事者がチームを組んで患者さんを診るというものです。
(大西) 病院とクリニックでは少し事情が違いますが、今日はクリニックの話をしたいと思います。
クリニックでは、どうしても患者さん以外の人、つまり医療スタッフがチームの中心から外れていく傾向があります。
例えば、チームの中心は医師です。
その次にナース、コメディカルが続きます。
一番遠いところにいるのが事務スタッフ、そして患者さんという構図です。
しかし、今の考え方は違います。
患者さんもチームの一員ですし、事務スタッフもチームの一員です。
以前よりチームの範囲が広がったと言えるでしょう。
(高山) なるほど。冒頭でお話しいただいたように、「患者様」「患者さん」という呼び方の変化も、このことに関係しているのでしょうか。
(大西) その通りです。
元々は「患者第一主義」という考え方が、顧客満足という発想から医療にも持ち込まれました。
バブルとその崩壊を経験した1990年代には、いかに患者様を満足させるかが、医療経営の本質だと考えられていたのです。
そこで生まれたのが患者第一主義です。
しかし、行き過ぎるとやり過ぎになってしまう。
例えば、接遇を過剰に重視するあまり、本質を見失ってしまうことがありました。
90年代には、元CAを講師に招いて接遇研修を行うクリニックもあったほどです。
挨拶の角度、物の渡し方など、細かく指導していたようですが、表面的なことばかりに気を取られ、本質を見誤っていたように思います。
(高山) 当時も、そのような議論がありましたね。
(大西) 本質とは、患者さんを治すことです。
そのためには、患者さんの協力が不可欠です。
患者さんもチームの一員として、治療に積極的に参加してもらうことが重要なのです。
(高山) ビジネスの視点で見れば、患者さん=お客様として、大切に扱うべき存在でした。
しかし、実際には患者さんも治療に協力しないと、治療は成り立ちません。
(大西) 笑い話ですが、もし患者さんをお客様として扱うなら、クリニックの入口では「いらっしゃいませ」と言うべきでしょう。
そして「何かお探しですか?」と尋ねるわけです。しかし、医療の世界ではそうではありません。
患者さんは何か目的があって来院するのです。
ウィンドウショッピングをしているわけではない。
(高山) 確かに、患者さんには明確な目的意識がありますね。
(大西) そうです。
患者さんは「どんな病気か知りたい」「症状を治したい」など、目的意識を持って来院されます。
一般的な顧客とは異なるのです。
だからこそ、「患者様」から「患者さん」という呼び方に変わっていったのだと思います。
患者主体とインフォームド・コンセント、ACP
(高山) 「患者様」として扱われてしまうと、どうしても医療提供者側が主体となってしまいそうですね。
患者として主体的に治療に参加してもらうためには、どうすればいいのでしょうか?
(大西) 2000年代に入り、インフォームド・コンセントやACPといった概念が登場しました。
当初、インフォームド・コンセントは、説明と同意という一方通行のコミュニケーションでした。
しかし、インターネットの発展とともに、ACP、つまり患者さん、医療スタッフ、家族を巻き込んだ双方向のコミュニケーションへと変化していきました。
全員で一緒に考えようという考え方です。この頃から、「患者さん」という呼び方がより適切になってきたと感じます。
(高山) 「患者様」では、しっくりきませんね。
チーム医療の概念は、病院のコメディカルチームから広まったように思います。
クリニックのようにスタッフが少ない場合でも、チーム医療の意識は重要なのでしょうか。
(大西) 今、話題の朝ドラにもNSTというチームが登場しますね。
栄養士、看護師、医師がチームを組んで、患者さんのフォローアップをしています。
病院では、こういったチーム医療が一般的になりつつありますが、クリニックでは看護師が1、2名、事務スタッフ1名、医師1名というように、少人数で運営しているところがほとんどです。
このような少人数で、どうやってチーム医療を実践すればいいのでしょうか。
クリニックは、病院のピラミッド構造をそのまま小さくしたようなものです。人数が少なくても、チーム医療の意識は大切です。
そして、クリニックにおけるチーム医療で重要なのは、患者さんをチームの一員として巻き込むかどうかです。
もっと言えば、「患者教育」という視点が重要になります。
(高山) 「患者教育」とは、あまり聞き慣れない言葉ですね。
(大西) 10~20年前から、待合室にモニターを設置して情報発信をするクリニックが増えてきました。
どんな情報を発信すればいいのか。
例えば、「こんな症状はありませんか?」「こんな病気の可能性があります」「気になることがあればご相談ください」といった内容です。
患者さんの治療への協力を促すための、きっかけづくりと言えるでしょう。
(高山) 啓もうCMのようなものですね。
患者教育とインターネット、AIの活用
(大西) 例えば、高山さんが「お腹が痛い」という症状で来院されたとします。
その場合、考えられる病気はいくつかあります。
上腹部であれば逆流性食道炎、下腹部であれば大腸炎、おへそ周りであれば感染系の病気などが考えられます。
待合室でこういった情報を発信することで、患者さんは自分の症状について考えるきっかけになります。
診察室に入る前に、「どこが痛いのか」を自分で確認することで、医師とのコミュニケーションもスムーズになります。
以前は、医師が患者さんの身体を触診して「どこが痛いですか?」と尋ねていましたが、今は患者さん自身が自分の症状を把握しているケースが増えています。
これは、インターネットの普及によって医療情報が簡単に入手できるようになったことが背景にあると思います。
(高山) なるほど。情報が多く入手できるようになったことで、患者さん自身も積極的に治療に参加するようになったのですね。
(大西) ただ、インターネット上には正しい情報だけでなく、誤った情報も混在しています。
そのため、正しい情報を伝えることが非常に重要になっています。
例えば、「インターネットでこんなことが書かれていたのですが…」と患者さんに言われても、医師としては対応に困ることがあります。
(高山) 確かに、医師もインターネット上のすべての情報が正しいとは限りませんからね。
(大西) 「その情報は間違っています」と医師が言うと、「嘘のはずがない」と反論されることもあります。
患者さんがインターネットで見た情報を印刷して持参してくるケースもあります。
医師としては、こういった状況に頭を悩ませているのが現状です。
20年前は今ほどインターネットが普及していなかったので、このような問題は少なかったのですが。
今は、医学書を読まないまでも、インターネットで医療情報を検索する患者さんが増えています。
医師はガイドラインに沿って、医学書を読み、日々勉強を重ねています。
そのため、インターネット上の不確かな情報に惑わされている患者さんを診ると、少し戸惑ってしまうことがあります。
「この症状は、きっとこの病気のはずだ」と思い込んで来院される患者さんもいます。
(高山) そういった患者さんには、どのように対応すればいいのでしょうか。
(大西) 待合室で少しずつ情報を発信していくことで、患者さんの誤解を解いていくことが重要です。
「こういった症状の場合は、こういった可能性が考えられます。気になることがあれば、ご相談ください」というように。
患者教育と自由診療
(大西) 前回、自由診療についてお話ししましたが、自由診療と患者教育は非常に相性が良いと感じています。
例えば、トイレに「EDかもしれません。ご相談ください」といったポスターを掲示しているクリニックがあります。
泌尿器科との親和性が高いので、こういった場所にポスターを掲示する効果は大きいと思います。
(高山) なるほど。待合室だけでなく、トイレなども患者教育の場として活用できるのですね。
(大西) そうですね。待合室、トイレなど、クリニック内のあらゆる場所が教育の場になり得ます。少しずつでも、積極的に情報発信していくことが大切です。
(高山) そうやって患者さんを巻き込んでいくわけですね。
20年ほど前は、待合室に掲示物を設置したり、モニターで映像を流したりするクリニックが増え始めました。
ただ、当時は情報量も限られていましたし、CMのような内容が多かったように思います。
今は、どのような情報発信がされているのでしょうか?
(大西) 今は「こんな症状はありませんか?」といったように、より幅広い情報を発信しています。
診療科目によっては情報を絞り込むこともありますが、啓もう活動に力を入れているクリニックが多いですね。
以前はCMのような内容が多かったのですが、今は患者教育という側面が強くなっています。
ポスター=CMと捉えられてしまうと、患者さんは見向きもしません。しかし、教育だと分かれば、見てくれるのです。
これが、最近の大きな変化と言えるでしょう。
コンテンツ作成をサポートする業者
(高山) コンテンツを作成するのは大変だと思いますが、何か良い方法はあるのでしょうか?
(大西) コンテンツ作成をサポートしてくれる業者もあります。
手書きのメモを渡せば、業者側できれいなコンテンツに仕上げてくれるサービスもありますし、フォーマットに従って情報を入力するだけでコンテンツが完成するサービスもあります。
こういったサポートがあると、コンテンツ作成の手間が省けます。以前は製薬会社がコンテンツを提供していました。
しかし、どうしても薬の宣伝になってしまうため、CM色が強くなってしまいます。最近は、医師が自らコンテンツを作成するケースも増えています。
(高山) なるほど。業者に依頼したり、医師が自ら作成したりと、様々な方法があるのですね。
AIの活用と課題
(大西) AIの活用も広がりを見せていますが、課題もあります。
患者さんがAIに症状を入力すると、AIが病気の可能性を教えてくれます。しかし、AIの情報源はインターネット上の情報です。
間違っている可能性も高い。AIの情報に踊らされて、「きっとこの病気のはずだ」と思い込んでしまう患者さんもいるかもしれません。
AIは発展途上の技術なので、良し悪しがありますね。医師もAIを活用し始めています。
AIの見解と医師の見解が一致すれば、診断の精度向上に役立つでしょう。数年後には、AIに関する議論も落ち着いてくるかもしれません。
(高山) AIの活用は、今後の医療において重要な役割を果たすと思いますが、慎重に進めていく必要もありそうですね。
患者を巻き込むためのポイント:家族の協力
(高山) 患者さんをチーム医療の一員として巻き込む方法として、待合室の活用についてお話しいただきましたが、他に何かありますか?
(大西) パンフレットなどを手渡しで渡す際に、「ご家族と一緒に読んでください」と一言添えています。
そうすることで、家族もチームの一員に加わってくれます。家族の協力を得やすくなるのです。
(高山) 治療には、家族の協力も不可欠です。
(大西) そうですね。治療内容を隠すことなく、家族にもきちんと説明することが大切です。
「この治療を受けたいが、どう思うか」と家族に相談することもあります。家族の意見を聞くことで、治療方針を決める上で参考になります。
「検診の結果を家族に見せるかどうか」も、重要なポイントです。
家族に見せることで、患者さんの治療に対する意識も高まります。
ワンチーム医療の重要性
(高山) 偏った情報に惑わされずに、医師と患者が適切な関係性を築くにはどうすればいいのでしょうか。
(大西) ワールドカップやラグビーなどで話題になった「ワンチーム」という考え方が、医療においても重要です。
「治療は医師が行いますが、患者さんの協力も必要です」ということを、医師はきちんと伝えるべきです。
患者さんも、そのことを理解した上で治療に協力してくれるでしょう。薬をきちんと服用したり、運動療法や食事療法に取り組んだり。
慢性疾患は、すぐに効果が出るとは限りません。徐々に良くなっていくものです。
だからこそ、患者教育が重要になります。
(高山) なるほど。「ワンチーム」の考え方は、慢性疾患の治療において特に重要なのですね。
今後のチーム医療
(高山)今日はチーム医療について、患者さんを巻き込んでいくというお話でした。
次回は、医療スタッフ側のチーム医療についてお伺いしたいと思います。
続きは次回にしたいと思います。
本日はありがとうございました。
(大西) ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。