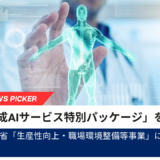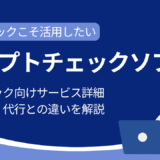PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第49回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。いよいよ49回、次回は50回ですね。今日のテーマは何でしょうか?
(高山)今日のテーマは、引き続きチーム医療についてです。
前回は患者さんを巻き込むという話でしたが、今回はスタッフ側、クリニック側のチーム医療をどうやって作っていけばいいのか、という話をしていきたいと思います。
(大西)そうですね。こちら側の方が、院長先生たちはより興味があると思うので、今回は少し掘り下げていきたいと思います。
(高山)はい。ということで、この後チームビルディングを含めたチーム医療のスタッフ側のお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
チームビルディングとは?
(高山)今回はスタッフ側のお話ですね。チームビルディングについて、どのようにチーム医療を作っていけば良いでしょうか?
(大西)そうですね。前回は患者さんに対してでしたが、今回はスタッフに対して、どのようにクリニック運営に関わっていけばいいのか、そのための話し合いの場を設けているクリニックはどれくらいあるのでしょうか?
というところから始めたいと思います。
(高山)あまり多くはないんじゃないでしょうか。
(大西)私も少ない印象です。だからこそ、このテーマでお話したいのですが。
以前、朝礼や定例会議についてもお話しましたが、実際に行っているクリニックは少ないようです。
つまり、スタッフは経営に参加しておらず、決められたことだけをこなしているということですね。
時間軸が短く、場当たり的な運営になっているクリニックが多いのではないでしょうか。
クリニック経営は、少なくとも20年は続く長い航海のようなものです。
先日も、院長先生もスタッフも65歳くらいで、勤続25年というクリニックにお伺いしましたが、皆さんの雰囲気は本当に温かいものでした。
良いクリニックを作ろうという意識の高い、まさに「戦友」のような関係でした。
(高山)25年間、同じクリニックで働き続けるというのはすごいですね。転職を繰り返す人が多いイメージなので。
(大西)そう思っていましたが、意外と長く勤めている方もいるんですね。
あるクリニックでは「20年来の付き合いだ」というスタッフの方もおられました。
もはや親友のようなものです。
クリニックのビジョン共有の重要性
(高山)クリニックによって様々だと思いますが、チーム医療において重要なポイントは何でしょうか?
(大西)意識改革だと思います。
「私は雇用される側」「私はただのスタッフ」という考え方から脱却し、徐々にマネジメント側に何人か引き上げていく必要があると考えています。
(高山)スタッフを徐々に巻き込んでいくということですね。
(大西)そうです。ただし、いきなり巻き込むのは危険です。
例えば、よく相談を受けるのが「役職はどう決めたらいいか?」「給料はどうやって上げたらいいのか?」といったことです。
これは物価上昇に伴うベースアップとは別の議論です。
スタッフの能力向上、管理業務の増加、組織への貢献度などに応じて給料は上がるべきで、その点を一緒に考えていく必要があると思っています。
(高山)クリニックをどうしたいのか、院長先生はどういう風にしたいのかを、スタッフと共有しながら考えていくことも大切ですね。
(大西)その通りです。「そんなこと、私が考えることじゃない」というスタッフもいるかもしれませんが、中には「私も一緒に考えたい」という人もいます。
そういうマネジメント気質のある人材を見つけることが重要です。
(高山)なるほど。これ気質なんですね。
(大西)気質と経験かな。過去にしたことがある人は経験。
気質は多分小学校、中学校、高校の中でもう決まってくるかもしれないですね。
だからそこで炙り出しでチームビルディングという研修を結構します。
チームビルディング研修の活用
(高山)チームビルディング研修を行うと、そういった気質を見抜けるのでしょうか。
(大西)見抜けます。
例えば「ペーパータワー」や「マカロニタワー」、別名「マシュマロチャレンジ」といったゲームを通して、5、6人のチームで協力し、1つの目標(塔を建てる)に挑戦してもらいます。
(高山)塔を作るんですね。
(大西)そうです。スパゲッティで塔を立てて、その上にマシュマロを乗せるのがマシュマロチャレンジです。
ペーパータワーは紙だけで高さを競います。
どちらも同じように客観的に状況を分析できる人がいるチームは、上手く塔を建てられます。
計画を立て、時間内に業務をこなし、設計図を作る、といったプロセスをきちんと考えられる人材は貴重です。
マシュマロチャレンジの目的
(高山)実際に塔が建つかどうかは別として、そういうアプローチができる人材を見極めるということですね。
(大西)そうです。「Aさんはこれ、Bさんはこれ、私はこれを担当します」と言える人が、マネジメント気質を持っていると言えるでしょう。
(高山)良い言い方をすればマネジメント気質、悪い言い方をすれば「仕切り屋」とも言えますね。
(大西)仕切り屋気質も時には重要です。
「これをお願いします」と言える人と「これをやっといて」と言う人では、相手に与える印象が全く違います。
こうしたゲームを通して、普段の仕事の進め方、依頼の仕方なども見えてきます。
中には、とにかく突貫工事で進める人もいれば、逆に気を使いすぎて自分で抱え込んでしまう人もいます。
頼めない。これもマネジメント気質は良くないですよ。
このゲームの目的は、心地よく頼め、そして心地よく受け取るっていう組織を作ることですので。
だからその反省会で皆に聞くんですね。
このチームビルディングゲームについてどう感じましたか?っていうと
ある人は設計図が必要だと思いました。
ある人は時間が足りなくて、もっと頑張れたのにな。
この発言だけ聞いても違うんですよね。
時間が足りないって言った人は時間さえ伸びればなんとかなるって思ってるんですよ。
設計図があればっていう人は設計図があれば時間短くできて上手く効率化できたのにっていう発想なので、前者の方が正しい理解なんですよね。
設計図全く作らない人いますからね。いきなりスパゲッティを繋ぎ始める。
(高山)そうですね。私もこれ実は社内でやったことあるんですよ。
マシュマロチャレンジ。ポキって折れちゃうんですよね。
上手くやらないとまず、茹でる前のパスタで、タワーを作って行って、軽いんだけども、マシュマロそれなりに重さがあるから、立て切るっていうのが結構難しいんですよね。
(大西)これは高くすることが目的ではなくて、時間内に皆を同じ目標ベクトルに合わせて行くっていうトレーニングなんですよね。
だから時間配分、例えば誰だれさんちょっと時間計ってとか。
先に10分だったら3分、3分、3分割して、最後バッファー作っときましょうねみたいな。
そうすると最初に3分間で何しましょう?
次の3分間で何しましょう?
最後3分間、ラスト1分何しましょう?
みたいなスケジューリングをするとか。
こういくらでも戦略ってあるんだけど、その戦略、戦術っていうことを教えるにはすごく最適なゲームだなと思います。
院長のタイプとマネジメント
(高山)では、チームをまとめる院長先生にも様々なタイプがあると思いますが、どのようにチームビルディングを進めていけば良いでしょうか?
(大西)院長先生の中には、職人タイプの方もいらっしゃいます。
そういう場合は、強いマネージャーを横に置くのが良いでしょう。
事務長のような、チームをまとめてくれる人がいると、クリニック運営がスムーズになります。
先日、ある先生に経営コンサルティングの相談を受けました。
先生は「自分は経営に向いていないから、経営のプロを雇いたい。でも、乗っ取られるのは困る」とおっしゃっていました。
外部のコンサルタントに依頼するというのも1つの方法です。
外部コンサルタントの役割
(大西)確かに、院長先生に向いているスタッフが事務長になり、他のスタッフと結託して院長先生を責めるような事態は避けたいですね。
外部コンサルタントは、月に1回、多くても週に1回程度しかクリニックに伺いません。
そのため、スタッフとの信頼関係を築くのは難しい側面があります。
コンサルタントは計画を立て、実行し、反省するというPDCAサイクルを重視しますが、計画を立てるのも、その進捗を管理するのも、現場のスタッフであるべきです。
理想的には、1年後にはコンサルタントが必要なくなるような組織作りを目指しています。
チーム運営の本質
(高山)チームを作るのが目的か、チームと仕組みを作るのが目的か、それともコンサルタントが組織に組み込まれるのが目的か、によってアプローチも変わってきますね。
(大西)そうですね。現場で意識すべき点として、緊急ではないけれど重要な取り組みを優先すること。
逆に緊急だが重要ではないものは後回しにする。
そうした組織作りが重要です。1年後、2年後、3年後、クリニックをどうしたいのか?
これがクリニックの方針であり、ビジョンです。コンサルタントとしては、この方針をスタッフ全員で共有することが重要だと考えています。
(高山)コンサルタントの立場からすると、院長先生に明確なビジョンがないと、サポートのしようがないですよね。
(大西)その通りです。ですから、私は最初に院長先生とじっくりお話をして、クリニックのビジョンやその背景にある考えを明確にしていただきます。
そして、それを言語化したものをスタッフに共有していただきたいと思います。
理念という形でも、クレドという形でも、事業方針書という形でも構いません。
年に1回は、スタッフ全員で共有する機会を設けることをお勧めします。
ビジョンのすり込み
(高山)一度方針を決めたら、それをずっと変えない先生も多いと思いますが、定期的に見直すことも必要ですね。
(大西)本当にそうです。方針は、いつの間にか当初のものからズレてしまうものです。少なくとも年に1回は見直し、確認する作業が必要です。
(大西)1年に1回、もしくは半年に1回、チームビルディングのトレーニングを行い、方針の発表と共有を行う。
これが理想的ですね。院長先生は、ビジョンを掲げるために院長になったという意識を持つことが大切だと思います。
(高山)チームを率いるリーダーとして、ビジョンを掲げるのは怖いと感じる先生もいるかもしれません。
(大西)そうですね。しかし、チーム医療においてビジョンがないチームは存在意義がありません。
(高山)厳しいですね。
(大西)厳しいですが、それが現実です。
チームである以上、何らかの目的がなくてはなりません。
目的のない集団は、ただのグループです。
ラグビーとチームビルディング
(大西)チームとグループの違いですね。日本人は、どちらかと言うと右往左往しがちで、ベクトルがバラバラになりやすいように思います。
ベクトルが揃っていなければ、スクラムは組めません。
ラグビー出身の私は、そのことを身をもって知っています。
最初は力任せに押せばいいと思っていましたが、いくら筋トレをしても、ベクトルが合っていなければ負けてしまうんです。
チームで1つの方向に進むためには、ビジョンを共有し、ベクトルを合わせることが不可欠です。
チーム運営の難しさ
(高山)組織の中で、誰かがサボったり、反対方向に走ったりする可能性もありますよね。
(大西)そうなんです。だからこそ、リーダーは常にチームの方向性を確認し、指し示し続ける必要があるのです。
ボートを漕ぐ時、先頭の人が旗を振って方向を指示するように。
(高山)なるほど。チームをまとめるのは、本当に難しいですね。
(大西)難しいですね。レベルの差、想いの差、スキルの差、経験の差。色々な差があるメンバーをまとめるのは容易ではありません。
(高山)チーム医療は奥が深いですね。
今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。
詳しいお話は、また別の機会にしたいと思います。
大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。