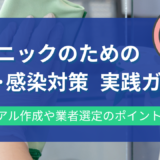PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第52回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
(高山)今日のテーマは第三者承継です。
第三者承継が増加傾向?
(大西)最近、第三者承継が増加傾向にあると聞きました。従来の承継といえば、親から子へと引き継ぐケースが一般的でしたが、第三者承継、つまり他人への承継が増えてきているようです。
私の感覚では、既に開業している医師の約1/3が第三者承継になっているように感じます。
その傾向を踏まえて、お話を進めていきましょう。
開業医が抱える承継への不安
(高山)日本医師会が実施した実態調査によると、開業医の3割以上が親族以外への第三者承継を検討しているそうです。
しかし、同時に多くの不安も抱えているようです。
信頼できる相談先が見つからない、後継者候補を自力で探せるか不安、妥当な金額で事業譲渡できるか不安、引退後の生活水準を維持できるか不安、行政手続きが煩雑そうで不安、など様々です。
事業譲渡する側の視点での実態について、大西さんのご意見はいかがでしょうか?
親族への承継の難しさ
(大西)第三者承継を検討する背景には、親族への承継の難しさがあると思います。
子供や甥姪など親族に医師がいないケース、あるいは医師であっても承継の意向がないケース、診療科が異なるため承継しにくいケースなどです。
今の時代、子供にクリニックを継がせたいと思っても、年齢が離れすぎていたり、そもそも医師を目指していなかったりする場合も多いです。
結果として、8割程度の医師が親族への承継を断念しているのではないでしょうか。
(高山)後継者候補の有無についても調査では、いる、いないが半々という結果だったようですね。
(大西)医師の家系というイメージもありますが、実際は必ずしもそうではないということですね。
4代、5代続く家系もあれば、親がサラリーマンという医師もいます。多様性の時代ですね。
少子化、晩婚化も背景にあるのでしょう。
(高山)なるほど。子供がいる医師でも、承継の意向がなかったり、診療科が違ったりするケースもあるようですね。
承継される側の視点
(大西)承継する側、つまり、クリニックを引き継ぐ側の視点で重要なのは、「何を引き継ぐか」です。
一般的には、建物、設備、患者カルテ、スタッフが挙げられますが、それぞれに課題があります。
古い建物の問題
(高山)古い建物をそのまま引き継ぐと、古さが出てしまいますよね。
(大西)そうですね。30年前の建物をそのまま引き継ぐと、30年前の印象を与えてしまいます。
特にコロナ以降、診察室や待合室のレイアウトも大きく変化したので、古い建物は使いにくく、改修が必要となるケースが多いです。
(高山)居抜き物件のようにそのまま全てを引き継ぐか、スケルトンにして建物の外観だけを引き継ぐかの二択ですが、どちらが良いかは難しいところです。
スタッフの承継
(高山)スタッフを引き継ぐ場合、年齢の問題も出てきますよね。
(大西)20年前に採用されたスタッフは、既に50代になっているかもしれません。引き継ぐ側の医師が40代であれば、年上のスタッフをマネジメントするのは難しいでしょう。
長年勤務しているスタッフを立てる必要もありますし、気を使う場面も多いはずです。
紙カルテの問題
(高山)紙カルテを引き継ぐのも大変そうですね。
(大西)紙カルテは記載内容が分かりにくく、前の先生とスタッフしか読めない場合も多いです。
そうなると、そのスタッフが大きな力を持つことになり、牛耳られてしまう可能性もあります。
本来、カルテは過去の記録として閉じるべきですが、スタッフに「先生、これ…」と過去のカルテを見せられると、なかなか断れないものです。
私がクリニックのコンサルティングに入る時は、必ず最初に紙カルテを廃止するように勧めています。
引き継ぐ側の若い先生は、ほぼ100%電子カルテを導入しています。紙カルテに付箋を貼る文化から、電子カルテに直接書き込む文化への転換が必要です。
紙カルテを使い続けるスタッフは、「電子カルテは無理です」などと言って辞めてしまうかもしれません。
(高山)主要スタッフが辞めてしまうと、承継の意味が薄れてしまいます。
(大西)開業当初からのスタッフは、クリニックにとって大切な存在ですが、承継開業時には、前の院長の息のかかったスタッフが牛耳ろうとする可能性もあるということですね。
健全な組織運営のためには、注意が必要です。
まるで、スタートラインに皆立っているのに、一人だけずっと後ろから助走をつけているような状態です。
皆が100m走なのに、一人だけマラソンを走っているようなものです。
(高山)息が合わないでしょうね。
(大西)結論としては、建物は引き継いでも、カルテとスタッフは引き継がないのが良いでしょう。
承継する範囲は、契約時にしっかりと確認しておくべきです。
元々の院長とスタッフとの関係
(高山)元の院長にとっては、長年勤務してくれたスタッフに愛着があるでしょうから、「このスタッフだけは残して欲しい」と思うでしょうね。
(大西)引き継ぐ側も、スタッフがいた方が楽だと感じるかもしれません。
つい、「ありがとうございます」と甘えてしまうこともあるでしょう。
(高山)ロックアップ期間を設定するのも一つの方法かもしれませんね。
(大西)そうですね。あるいは、一度全員を解雇し、改めて面接をして再雇用するのが良いかもしれません。
(高山)応募者には、「新しい院長の理念はこうです。このようなクリニックにしたいと思っています。賛同できますか?」と確認し、合意を得られたスタッフのみを再雇用します。
(大西)契約内容も更新し、「私の考えはこうです。合意できますか?」と確認することも重要です。
これが、承継を成功させるための秘訣の一つと言えるでしょう。
承継するメリット:場所の認知
(高山)承継するメリットは何でしょうか?
(大西)場所の認知度を引き継げることです。
人々は、「あそこに新しいクリニックができるらしい」とワクワクしながら見ています。
以前そこに何があったかという記憶も、良い効果を生みます。
(高山)一度閉院して引き継ぎ先を探すとなると、認知活動に時間がかかります。
シームレスに承継できれば、認知度は変わりません。住民や患者にとっては、「あそこにクリニックがある」という認識が既にインプットされているわけです。
法人格の承継
(高山)医療法人格を引き継ぐのは容易でしょうか?
(大西)以前は、「持分あり」か「持分なし」かの議論がありましたが、現在は「持分なし」の医療法人しか設立できないため、持分ありの法人を設立したい場合は、既存のものを買収するしかありません.
(高山)持分ありの場合は、引き継ぐ際に資産価値の評価で揉めることもあるようですね。
(大西)そうですね。専門外なので詳細は分かりませんが、高額になることが多いようです。
承継には様々なことを検討しなければなりません。
最近の傾向
(高山)最近の傾向として、全てを引き継ぐケースと、建物の外観だけを引き継ぐケース、どちらが多いのでしょうか?
外観だけを引き継いだ方が楽なのでしょうか?
(大西)外観だけを引き継ぎ、新規開業のような気持ちでスタートするのが良いと思います。
アドバンテージとしては認知活動のショートカットになり、法人格も取得できます。
法人格があると社会的な信用度が高いため、行政手続きなどもスムーズになります。
(大西)そうですね。建物だけを引き継いで、中身は新規開業と同じようにスタートするのが良いと思います。
既存の建物を利用することで、場所の認知度というメリットを活かしながら、カルテやスタッフの問題を回避できます。
また、法人格も引き継げるので、社会的な信用度も高く、行政手続きなどもスムーズに進められます。
新規開業と比べて、初期投資を抑えられる点もメリットです。
(高山)本日は、第三者承継について詳しくお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。