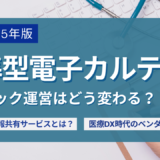PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第58回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
未経験者を医療事務として採用するときの注意点
(高山)今日のテーマは「未経験者を医療事務として採用するときの注意点」です。
経験者不足と採用活動の現状
(大西)最近は経験者募集をしてもなかなか経験者が集まらない時代ですね。
(高山)そうですね。
(大西)クリニックの現場では、3人事務さんがいて1人辞めたので1人補充、といったようにギリギリの人数で回しているところが多く、5人いるから1人を雇う余裕はありません。
3人が2人になったので1人補充、4人が3人になったので1人補充、といったように、かなり比重の高い採用活動をしているため、教えている暇がない、忙しいので時間がないというクリニックが多いのではないでしょうか。
とは言え、未経験者を雇わざるを得ない時代になってきました。
未経験者の定義
(高山)未経験者といっても、医療事務の経験がない人、医療機関で働いた経験がない人など様々です。
どういう風に未経験者を雇ってうまくやっていく方法を話していきましょう。
(大西)未経験者には大きく分けて2つのタイプがあります。
1つは医療機関で働いたことがない人。
もう1つは医療機関では働いたことはないけれど、通信教育などで勉強した人です。
私はどちらも未経験者と考えています。
医療機関で働いたことがない人は、勉強の有無に関わらず未経験者です。
医療事務の専門学校に通っている生徒も実習はありますが、医療機関での勤務経験がないという意味では未経験者ですね。
なぜ未経験者を採用するのか?
(高山)未経験者でも医療事務の仕事に飛び込んでくる人はいるのでしょうか?
(大西)未経験者を採用せざるを得ないほど、採用活動は厳しい状況です。
以前は「経験者優遇」「2〜3年の経験があれば尚可」といったように、経験者だけで現場を回していましたが、今では経験者募集の求人に応募が来ない状況です。
「未経験者歓迎」と募集を出すと、ようやく応募がちらほら来るようになります。
未経験者でも良いという求人であれば、応募する側も安心して応募しやすいのでしょう。
ただし、未経験者の多くは「現場で教えてもらえるだろう」という淡い期待を抱いているようです。
未経験者採用のミスマッチ
(高山)採用する側は教えてくれることを期待して応募してくるのに対し、現場では忙しくて教える時間がないというミスマッチが起きています。
(大西)まさにその通りです。
未経験者を募集している以上は当然教えてくれるものだと応募者は思いますが、現実はなかなか教えてもらえず、すぐに辞めてしまうというケースが多いですね。
「最近、医療事務がすぐに辞めてしまうのはなぜだろう?」と悩む院長先生に話を聞くと、「放置しすぎているからでしょう」と答えることもあります。
医療事務の仕事の責任
(大西)医療事務の仕事は、一見簡単そうに見えて、実は責任が重い仕事です。
例えば受付業務では、問診票を書いてもらう、保険証を預かる、マイナンバーを扱うなど、様々な業務があります。
保険証だけでも国保、社保、公費など多くの種類があり、それぞれ対応が異なります。
資格を確認する作業も未経験者には難しいでしょう。
お酒を販売する際に免許証を確認するのとは訳が違います。
免許証の場合は大人であればOKですが、保険証は内容が間違っていないかだけでなく、保険者の登録が正しく行われていないとレセプト請求ができません。
保険証を預かり、返却するという作業も、実は非常に重要です。
保険証をうけているのに返し忘れてしまうといったトラブルも多いようです。
以前は保険証の返却忘れはクリニックにとって大パニックでしたが、最近は「あ、すみません」で済まされてしまうこともあります。
また、保険証はコピーを取りますが、マイナンバーは取り扱ってはいけないなど、未経験者にとっては混乱しやすい点も多いですね。
医療事務に必要なスキル
(大西)医療事務の仕事は、診断書の作成や処方箋の発行など、責任が伴う業務が多く、未経験者に任せるとミスが起きやすいです。
応募する側もその点を理解していれば良いのですが、医療事務の仕事のイメージは「受付でニコニコしていれば良い」というもので、責任の重さを理解していない人が多いようです。
冷や汗をかくような仕事も多いですね。
(高山)確かに、受付業務というとホテルマンのような接客業のイメージが強いかもしれません。
お客様、つまり患者さんと接することが好きで、場を和ませるのが得意な人が応募してくるイメージですが、医療事務の場合は求められるスキルが少し違います。
(大西)医療事務には、接客業のようなコミュニケーション能力に加えて、正確に作業を行う能力も必要です。
細かい作業が得意で、マスからはみ出さずに文字を書ける、0と1、2といった数字を正確に転記できるといった正確性が求められます。
また、医療現場はデジタル化が進んでおらず、手書きの業務が非常に多いです。
そのため、綺麗な字を正しく書けることも重要です。
封筒の宛名書きや処方箋、診断書の記入など、手書きの作業は意外と多いです。
転記作業なども正確に行う必要があります。
未経験者採用における研修の重要性
(大西)私は未経験者を採用する際に、2つの研修を必ず行っています。
1つは接遇研修、もう1つは正確性に基づいた診療報酬に関する研修です。
接遇研修はおもてなし、優しさといった接客業に近い内容ですが、診療報酬の研修は専門的な知識が必要で、ミスが許されない責任の重い業務です。
未経験者の中には、この2つ両方に対応できる人が少ないため、現場で混乱が生じやすいです。
正確に作業することが苦手な人もいますし、そういったタイプの人は医療事務の仕事には向いていないかもしれません。
面接での見極め方
(高山)では、面接でどのように未経験者を見極めれば良いのでしょうか?
(大西)自己紹介の論理性や、400字程度のレポートを書いてもらうのが良いでしょう。
履歴書にある自己PR欄は、インターネットからコピー&ペーストしている人もいるので、あまり参考になりません。
原稿用紙を渡して、その場で書いてもらうのがおすすめです。
漢字やひらがなを正しく書けるか、誤字脱字が多いかなども分かります。
400字程度書いてもらえれば、正確性に問題がないかすぐに分かります。
マス目にきちんと文字を書けない人は、正確性に欠ける可能性があります。
「それくらいで大袈裟な」と思う人もいるかもしれませんが、医療事務の仕事では、細かいミスが大きなトラブルに繋がることもあります。
例えば、「あ」の後に点を打つ位置が少しでもずれていると、別の意味になってしまうこともあります。
小学校で習ったはずの丸の書き方を忘れてしまっている人もいます。
こういった小さなミスを繰り返す人は、医療事務の仕事には向いていないでしょう。
優しさを見極める方法
(大西)優しさを見極めるには、家族のエピソードを聞くのが良いでしょう。
「もし差し支えがなければ、これまでの人生で幸せだったこと、楽しかったことについてお話しください。できれば家族との思い出なども教えてください。」
といった質問をすると、家族の話をしてくれる人は温かさや優しさを持っていることが多いです。
逆に、「家族とはあまり関わらず、一人で生きてきました。人を信用していません。」といったタイプの人は、優しさに欠ける可能性があります。
チームワークも苦手かもしれません。
(高山)面接で家族について聞くのは難しい場合もありますが、学校時代や前職でのエピソードを聞くのも良いかもしれません。
「自分が何をやったか」ではなく「チームで何をやったか」を話せる人は、チームワークを大切にできる人です。
「自分が、自分が」とばかり話す人は、優しさに欠ける可能性があります。
その他の注意点
(大西)社会との接点も大事です。
例えば、「スーパーで困っているお年寄りがいたら助ける」といったエピソードを話せる人は、優しさを持っていると言えるでしょう。
(高山)最近はお年寄りが本当に困っているのかそうでないのか分かりにくいケースも多いですが。
(大西)これからは困っている人しかいなくなりますよ。
医療機関には困っている人しか来ません。
困っている人に手を差し伸べられない人は、医療事務の仕事には向きません。
目の前の人に「こんにちは」と挨拶するのは当たり前のことですが、挨拶ができない人も増えています。
「なぜ挨拶をしなかったのか?」と聞くと、「目の前の仕事が忙しかったので」と答える人もいます。
仕事を一度止めて挨拶をする、それくらいの優しさは必要です。
(高山)そうですね。やっぱ価値観が変化してってるんでしょうね。
(大西)人と仕事するとか人と勉強するとか人と何かするのは減っちゃってるのかもしれないですよ。今の世の中。
(高山)特にコロナでかなり分断が進んだと私自身も思っているので、孤立してる人が増えてるなっていう感じがしますよね。
(大西)そう。面白いですよね。顔を合わせて話せないのにコールセンター業務めっちゃできるとかいじゃないですか。
顔見てないから電話はできるんです。へえと思って。僕逆に電話の方ができないから。
まとめ
(高山)今日の話をまとめると、医療事務の未経験者を採用する際には、本を読めるか、つまり医療事務の勉強ができるか、ルールに基づいて正確に作業ができるか、接遇面での優しさを持っているか、という点が重要です。
優しさと正しさ、両方を兼ね備えた人材を採用するのが理想的です。
(高山)次回は、なぜ医療事務が孤立しやすいのか、チーム意識や帰属意識の希薄化について、クリニックの運営方法と合わせて考えていきたいと思います。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。