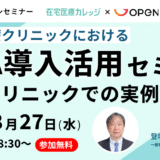PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのDOC WEB編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山) 院長が悩んだら聞くラジオ第65回始まりました。大西さんよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今回のテーマ:ーニングピラミッドを使って何を学習するのか
(高山)前回の続きになりますが、ラーニングピラミッドを使って何を学習していけばいいのかという内容についてお話していきたいと思います。
(大西)院内勉強会、あるいは院内研修会のテーマはたくさんあると思うんですけど、日々の仕事のレベルアップにつながるものがいいと思うんですよね。
ですので、どんなものがどういう効能・効用をもたらすのかということの関係性も考えていきたいなと思います。
(高山)ということでこの後、何を学んでいくのか、どう学んでいくのかということについて語っていきたいと思います。
(大西)はい、お願いします。
院内勉強会の効果的な進め方
(高山)では本題ですね。誰がどうやってやっていけばいいでしょうか。
(大西)基本的には、院長先生が主催者にあたるのですが、できれば、院長先生が講義をするのはほとんどない方がいいと考えています。
(高山)ほう。
(大西)主体性は基本的にはスタッフに置いてほしいです。その理由を端的に言うと、院長の説明を聞いてみんなが「ふむふむ」という状態だと、半年経ったら95%忘れてしまいます。
ラーニングピラミッドの原則・原理に則ると、そのやり方は向かないということになりますね。
(高山)でも必要ではあるんじゃないんですか。
(大西)必要ですけど、院長が情報を入手して、それをテーマに設定するだけでいいと思うのです。
(高山)誰がやるかというのはスタッフの方でいいということですね。
(大西)そうです。例えば診療報酬改定の勉強会を先生がすると効果がありません。
(高山)効果がない。
(大西)診療報酬の勉強をした人間を、院内に作らないといけないのです。
(高山)アクティブラーニングを主体にしてやった方がいいということですね。
(大西)要は、「やらされている感」を出すとだめなのです。
勉強が嫌々になってしまう。
(高山)偉い人から聞くと、そうなりますね。
(大西)必ずスタッフ全員が参加できるプログラムに変えます。
主体はスタッフ、テーマは業務直結の内容で
(高山)講義の時間があったり、「このテキスト読んどいてください」というのは基礎的にはあるわけですかね、段階的には。
(大西)それは先生がパスしていますね。
(高山)パスというのは。
(大西)印刷物をスタッフに渡すということです。
(高山)配布しているということですね。
(大西)「読んどいてね」と。そこで終わってしまうと、多分今までと一緒なので、読んだ内容について、誰々さん担当で発表してください、という形にします。
そうすると、発表までにその2人はめちゃくちゃ読むわけですね。
他の人はあまり読まないです。さらっと読むわけです。
今度発表者が発表して、その後にグループディスカッションで、「じゃあ当院はどうやって点数を取っていけばいいか考えましょう」と話し合い、最後に成果として「じゃあこういう仕組みにしましょう」まで落とし込むと、大体定着します。
(高山)なるほど、学習のプロセスや順番ということではなくて、効果的なものをやっていきましょうという考え方ですね。
(大西)そうです。だから「誰がやるのか」は全員ですし、「何を学ぶのか」は仕事に直結したことであればあるほどいいです。
診療報酬改定は2年に1回ありますが、その時期は12月、1月、2月、3月とずっと毎週やっているクリニックもあります。
週1はしんどいので、2週に1回か月に1回でいいのではないかと思います。
(高山)「誰がやるのか」というのは内容によって違うんですかね。
(大西)違うと思います。
外部の知見も活用する
(大西)接遇についてやろうとか、サービスについてやろうというのは、1回ぐらい外部講師を呼んでもいいかなという感じはしますね。
基準がちゃんとしたものにしておいた方がいい。
(高山)ぶれがちですよね。接客のルールとかは、「私はこうした方がいいと思う」という意見が反映されていくと、ごちゃごちゃになってしまいます。
(大西)そうそう。だから、おそらくですが、リソースがたくさんあるものは、少しぶれやすいのではないかと思います。
リソースが1個しかないものはぶれにくいのではないかと思うのです。
(高山)そうですね。
(大西)診療報酬も、基本的には点数が決まるとリソースが決まります。病気もガイドラインに則って勉強すればリソースは決まります。
あと、自治体情報や地域情報といったものもリソースが決まっていればいいのですが、このサービスに限って言うと、リソースがネットで調べてもたくさんあるので、少し怪しい。
なので1回外部に頼んだ方がいいかなと感じます。
(高山)自院の中ではできないことは、外部をうまく活用しましょうね、と。
逆に言うと、院内で得意な人がいれば、その人が教えていくということですね。
(大西)そうです。だから、たまに最近だと企業に勤めていた人が、少し新しい風を吹かしてくれることがありますね。
(高山)どんな内容ですか。
(大西)新入社員研修です。
新しく入った人というのは、企業に勤めていると1ヶ月ぐらい新入社員の研修がありますよね。
私も受けました。でも、クリニックには全くないのです。
(高山)だから、そういう企業から来た人が「やった方がいいんじゃない」と話すと、少し新人さんの教育プログラムが変わったりします。
(大西)今は丁寧に教えていかないといけない時代ですからね。それは一つの仕組みとして、ということですが。
(高山)そうそう。ただ、そういうふうに人がたくさん増えてくると、だんだん必要になることがあります。
勉強会の具体的な開催方法
(高山)いつ、どのくらいの頻度で、場所はどこでやればいいのでしょうか。
(大西)「いつ」というのは、昼休みか診察終了後なのですが、大体、午後の休みの時にやったらいいかなと思います。
(高山)食事をした後ですね。
(大西)お昼にお弁当でも食べて、「じゃあ1時間やろうか」と。
時間は、もう1時間。長くても1時間半でいいと思います。
(高山)そうですね。長いのはきついですもんね。
(大西)2時間とか3時間やっても意味がないので、1時間から1時間半でいいと思います。
「どこでやるか」というのは、できれば院内がいいので、院内の皆で集まってやれるところですね。
モニターやホワイトボードがあったらいいな、という感じです。
(高山)全員一括でやった方がいいのですか、分割してもいいのですか。
(大西)どうしても参加できない人もいるので、動画を撮るのもお勧めです。
(高山)そういう時間自体は1回で、それを動画で撮影しておいて共有してあげるという感じですかね。
(大西)そうです。
(高山)頻度としてはどのくらいできるのでしょうか、現実的にクリニックでは。
(大西)月1でしょうね。
(高山)月1ですか。そうすると、年間12回しかできないわけですよね。
この内容は結構厳選しないといけなくなってきますかね。
(大西)年間計画でやった方がいいのか、という話ですが、半々ぐらいがいいなと思います。
病気に関することが半分、診療報酬とかお金に関することが半分、ざっくり言うとそんな感じです。
制度変更も診療報酬に含まれるかもしれないので、制度が変わるよ、ということは随時やった方がいいなと感じますね。
(高山)接遇関係はそんなに頻度を高くしなくても、1、2回やればいいという感じでしょうか。
(大西)ただ、接遇が良くないところは集中的にやることはありますよ。
(高山)そうですよね。課題があるものに関しては頻度を高くやればいい、と。
(大西)そうです。そうでなければ、診療治療、病気に関することと、診療報酬や制度関係の話、いわゆる業界知識ですね、そういうのを入れていくといいと思います。
「学習する組織」が院長の心の平穏につながる理由
(高山)そうすると、自走する組織というか、院長が毎日機嫌良く過ごせる組織が作れる、というわけですかね。
(大西)最後に少しだけ話すと、機嫌が悪くなる原因は、自分が一生懸命頑張っているのに、振り返ると誰もついてきていない、という状況にあるのではないかと思います。
(高山)自分ばっかり頑張っている、と。
(大西)みんなが追いついている感じがするのが、この勉強会なのです。
(高山)ほう、なるほど。
(大西)学び、教え、また学び、教え、が何回も繰り返されていくと、先生に少しずつ追いついていくのです、段階的に。
先生も実は1人でこれをやっているのですよ。
新しい問題が起きたら勉強し、分からなかったら誰かに聞きに行き、なんとか一歩一歩壁を突き破っていく。
(高山)乗り越えているわけですね。
(大西)この行動と、この勉強会は似ているのです。
(高山)言われてみたらそうですね。
(大西)面白くて、個人事業主の方って、誰にも教わらずにやらざるを得ないのです。
(高山)そうですね。必ず壁にぶち当たります。
(大西)本当そうですよ。多分、税金を納めようと思ったら、税金の納め方を勉強しなきゃいけない。
スタッフさんと揉めたら、解決の方法を学ばなきゃいけない。
いつでも機嫌よく過ごすためにはどうすればいいか、という問いの1つのヒントが、自分と同じことをみんなにしてもらう、ということでしょうね。
(高山)それが自然にできるのが、この「学習する組織」ということなんですね。
(大西)そうです。学習する組織が定着すると、先生は「この分野はこの人の方が自分よりに詳しいな」と思えるので助かるのですよ。
(高山)それは気持ちが楽になりますね。
(大西)よくありますよ。
診療報酬をめちゃくちゃ勉強した子がいて、もう博士みたいになっているのです。
先生たちもかなわないから、その人の言うことを聞く、みたいな。
(高山)ただ、いいことは、最初から知っている子ではないということです。
(大西)ほう。
(高山)教え方を教えてあげて成長した子なので、偉そうにするとかはないのです、この学習する組織には。
(高山)大事ですね、それは。
「私知ってます」って言われても、ハレーションが大きくなるだけですから。
(大西)「私知ってます」を「みんなに教えてあげよう」という組織が学習する組織なので、「みんなが知ってます」という状態になって初めて、あなたの成長だ、という風に言っています。
勉強会成功のコツは「なぜやるか」の共有から
(高山)最後に、やる時のコツみたいなものはありますか。
(大西)アイスブレイクを先に必ずやっています。
(高山)ほう。
(大西)アイスブレイクは氷を溶かすという意味ですが、よくやっているのは「褒め褒めワーク」といって、3分間お隣の人を褒めましょう、と。
褒めてから勉強会をスタートしています。
(高山)大体イメージ的には何人ぐらいを想定されていますか、今。
(大西)10人から20人の間です。
(高山)結構な大所帯というか、クリニックにしては多くないですか。
(大西)いえ、先生も含めると10人ぐらいが多いかなと思いますよ、平均人数は。
受付さん、看護師さん、それ以外の方が2人ぐらいで先生がいて8人、9人。
(高山)10人ぐらいという感じですね。
(大西)20人ぐらいになると、20人が入れる場所がなかったりするので。
(高山)そうですよね。外部の会場を借りなきゃいけなかったり。
2回に分けなきゃいけない、というのもあるかもしれません。
(大西)面白いなと思うのが、みんなこの種明かしをしないまま、大体勉強会を始めるのですよ。
だから最初のうちは「なんでこんなことやらされてるんだろう」と言うのです。
(高山)目的が分からない。
(大西)そうそう。種明かしをしてからスタートするといいのかな、ということで、1回だけ私が「なぜ人は学習するのか」という授業をしてからスタートするケースも多いです。
(高山)なるほど。確かに、今まで「いつ、誰が、何を、どうやって(How)」という感じで話を聞いていましたが、一番大事なのは「なぜ(Why)」ですね。
(大西)なぜ。それを先に説明して、ラーニングピラミッドの話をしてからスタートするといいのではないかと私は思います。
(高山)それだと全然違いますね、この前提を引くのと引かないのとでは。
(大西)「なぜアクティブラーニングをしなきゃいけないのか」というのが分かれば、積極的に参加しなきゃいけないなということも分かりますし。
そうそう。人間って、意味が分かると嬉しくて、成果が出るとさらに嬉しいという動物みたいです。
(高山)誰でもそうなのですかね。
(大西)これはどこかの機会で話し合いたいのですが、「人は成長したいのか」ということを話し合いたいのです。
私は全員が成長したいと思っていない気がするので。
(高山)なかなか深い話になりそうなので、またいつか機会を設けて。
ということで、「学習する組織作り」について何回かにわたって話してきました。
最後に、どうやればいいのかという具体的なやり方も教えてもらいましたので、ぜひこのラジオをお聞きの院長先生には実践をしていただきたいです。
まだ定着率が5%、10%という「聞くだけ」の状態だとだめなので、ぜひクリニックで実践していっていただきたいなと思います。
では、続きは次回にしたいと思います。大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ 今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。