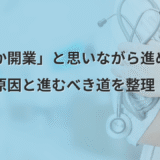PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第70回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。
(高山)今日のテーマは何でしょうか?
今回のテーマ:骨太方針の最終回・総まとめ
(高山)骨太方針の最終回ということで、総まとめのお話をしていきたいと思います。
(大西)骨太の方針の中の1番最初に書いてある言葉がすごくセンセーショナルなんですよね。
「今日より明日が良くなると実感できる社会」。これが副題なんです。高山さんこれについてどう感じますか?
(高山)そうですね。全人類の望みじゃないでしょうか。
(大西)「今日より明日はきっと良くなる」「幸せになる」。
それがベースにある中で、では医療はどうなるのかというのが今日のテーマですね。
(高山)ということで少し全体的なお話をしていただくことになると思います。よろしくお願いします。
医療費削減で守るべきもの、変えるべきもの
(高山)ではまとめですが、医療費削減はどのような方向に向かうのか、少し解説をお願いいたします。
(大西)医療費を削減するために、守らなければいけないことと、守らなくてもいいことがあると思うんです。
守らなければいけないことというのは、まず、みんなが保険に入れるという「皆保険制度」。
そして、自分たちがかかりたい時にかかれるという「フリーアクセス」。この2つは基本的に守らなければいけないルールです。
一方で、守らなくてもいいものとして、医療機関を増やしたり減らしたりということについては、特にルールには何も無いので問題ありません。
(高山)量の話ですもんね、そういうのは。
(大西)ただ、量を減らしすぎるとフリーアクセスが脅かされてしまいます。そして保障制度自体が破綻すれば、当然ながら皆保険制度も破綻する。
この2つについて、財務省や政府はこのままでは厳しいという見方をしているわけです。
(高山)これ両方あるみたいですけどね、見方として。
(大西)ただ、私が一番心配しているのは、人がいなくなるという問題です。
(高山)人?
(大西)スタッフですね。医療機関が潰れる理由は、患者がいなくなるか、スタッフがいなくなるかです。
(高山)前回も小児科の先生が病院からいなくなってしまったという話がありましたね。
(大西)患者がいなくなるという現象は、実は結構起きています。
市民病院が直面する「空洞化」の現実
(大西)市民病院などが、たまに民間に譲渡されているんですよね。その理由は、どんどん患者が目減りして採算が合わなくなり、売却するという流れです。
(高山)いなくなっているというのは、人口減少の話ですか?
(大西)いえ、違うんです。市民病院が町の中心にあって、その周りに開業医の先生が増えていくと、患者さんが民間の先生のクリニックにどんどん移っていって、市民病院の患者さんがだんだんいなくなるという現象です。
(高山)空洞化現象ですね。
(大西)空洞化現象というか、役割がなくなっていくんです。例えば、町ができて市民病院ができて、その町の医療を支えてきたとします。
その町が発展すると開業医の先生が増えてくるので、ある時期から市民病院の役割がだんだん少なくなっていく。
そうすると残ってくるのは、生活保護の方や、医療費の支払いが困難な方、あるいは最近の問題で言うと外国人の方など、少し難しい患者さんばかりが集まってくる傾向があります。そうなると、だんだんスタッフが疲弊していくんです。
(高山)手続きが大変ですからね。
(大西)患者が少ないのに手間がかかる人ばかりになっていき、スタッフが離脱していくということがあります。
それに、市民病院はあまりCM活動のようなこともしませんし、市自体が儲かっていないと建物の建て替えもできません。
(高山)どんどん老朽化する一方ですね。
(大西)そうです。医療機器も最新ではありません。想像してほしいのですが、医療機器が最新ではなく、先生もベテランで、建物も最新ではない医療機関と、若い先生が開業した、医療機器は最新で建物もピカピカのクリニックと、どちらを選びますか?
(高山)そうですね。あとは家に近いなど、様々な要因があるでしょうし。
(大西)その通りです。市民病院は基本的には区役所の近くだとか、土地を買って少し山の上にあったりします。
そうすると、医療機関の数が増えてくると、私は売却や譲渡というのが一つの選択肢になると思います。
そういうことを考えると、売却・譲渡した方が効率がいいとなれば、医療機関の数は減っていくわけです。
先日も相談を受けたのですが、昔はたくさん医療機関があった地域が、今では1つしかない、というような場所もあるわけです。
(高山)ええ、そうなんですか。
(大西)そういう状況になってくると、厚労省としては、この流れは少子高齢化と医療費削減の流れの中で、「本当に地域に必要な医療機関」と「そうでない医療機関」の選別を始めたい、という意図が見えてきます。
国が進める医療費削減の3つの柱
(高山)これはだいぶ前から取り組んでいますよね。地域医療構想という形で。
(大西)そうですね。全体像で言うと、前回の診療報酬改定であった処遇改善、いわゆるベースアップが、さらに首を絞めることになります。
もともと市民病院のような公立の病院は、年功序列で給料が高い傾向にあります。
そこに、民間の医療機関にも賃上げを促す信号が出ると、人件費がさらに上がっていく。結果として、経営がどんどん厳しくなっていきます。
今日の大きなまとめとして、国が何をしたいのかを考えると、医療費を減らして社会保障をスリムにしたいわけです。
そのために、まず「選別」ですね。本当にこれは地域に必要な医療機関なのかどうか。これを地域医療構想で決めましょう、というのが一つ目。
次に、必要ではあるけれども、過剰に儲けているところをどう取り締まっていくか。これが二つ目で、診療報酬の改定がそれに当たります。
三つ目は、患者さん自身を「予防」という観点から、どうやって病気にさせないようにするか。この3つの観点が盛り込まれていると感じます。
予防医療とデータヘルスの可能性
(高山)今後、長い目で見たらこの予防医療、予防領域というのはどんどん拡充されていくのでしょうか?
(大西)この予防領域というのが、まだ医療費に組み込まれていないんです。例えば、ある病気になっていて、次の病気に進行しないようにする予防、つまり糖尿病の患者さんが透析にならないようにする予防には、ちゃんと点数がついています。
しかし、そもそも糖尿病になるのを予防するための点数というのは、病気ではない人は病院に来ないので、設定が難しい。ですから、検診事業をきちんとやっていくしかないですよね。
(高山)糖尿病予備軍に対して医療費が使えるかというと、現状では使えないわけですね。
(大西)そうです。あとは、ここに「全世代型」と書いてあるように、負担を皆で分かち合うという考え方なので、おそらく高齢者も3割負担というのが出てくるでしょう。
今は上限が2割ぐらいですが、収入がきちんとある高齢者の方は3割を負担することになります。
70歳、80歳になっても元気な方は、それなりに負担をしてください、という流れです。
(高山)自分で稼げる人は、ということですね。
(大西)その通りです。一方で、ずっと課題になっているのが社会保障費です。
今、給料の3割が社会保障費と言われていますが、これを何とか打破できるかは、政治の力にかかっています。
年金、保険料、税金と、日本の負担はやはり厳しいものがあります。
(高山)特段高いのかというと、諸外国と比べるとどうなのでしょう。
(大西)日本はだいたい諸外国と比較するよりも、過去の自国と比較するので、「上がってきている」ということを問題視しがちです。
「スウェーデンなど北欧諸国の方が高いじゃないか」と言っても、別にそこを目指しているわけではない、というのが言い分になります。
(高山)お財布に直結するところなので、難しいですね。
(大西)ただ、選挙のことを考えると、社会保障費を削減しましょう、という方が有権者へのアピールにはなりやすいですよね。
(高山)全体の財源をどうするのか、という議論がなされないので、判断が難しいです。
(大西)局地戦で勝負しますからね。もう一つ大事な視点として、「データヘルス」という領域があります。
今、DXが進む中でデータが集まりつつあり、そのデータを活用すれば、無駄をなくして医療費を削減できる可能性があります。
実は病院ではDPC(診断群分類包括評価)という制度があり、そのデータは全て管理されているので、無駄な手術や検査を減らす方向に動いています。
よく考えられた仕組みですが、どんな検査や手術をしても点数が同じなら、より少ない検査数で済む方を選択するようになります。これが「包括払い」という考え方です。
一方で、やった分だけ無限に点数が上がる「出来高払い」という仕組みから、病院はどんどん外されていっています。
しかし、クリニックの外来は、相変わらず出来高払いが基本です。
クリニックが取るべき今後の戦略
(高山)そのあたりは、長い目で見ればメスが入るかもしれませんね。
(大西)そうです。生活習慣病にも包括の仕組みが入ってきましたし、かかりつけ医についても、昔は「外来慢性疾患管理料」のような点数がありました。小児科領域では、すでにかなり包括の仕組みが導入されています。
一番医療費を下げる方法は、検査を減らし、薬を減らし、来院日数を減らすことです。
だとすると、今後は包括払いの方向に舵を切っていくのだろうと感じます。
(高山)本当に長い目で見れば、だんだん当たり前のことをやり始めているように見えます。
そう考えると、やはり「病気にならない」ように、どんどんと早めの対策を取ることが、今後ますます大事になってくるのでしょうね。
国民の多くが生活習慣病ですから。自らの生活習慣で病気になり、その治療のために医療費が増大し、その結果、財政が厳しくなって消費税や所得税が上がり、生活が苦しくなる。
元をたどれば国民の生活習慣の問題なので、そこを根本的に変えれば医療費は削減できる、という考え方が長い目で見れば出てくると思います。
(大西)そう考えたときに、先ほど言った「予防」という考え方や、「デジタルヘルス」「データヘルス」の活用は、今のトレンドです。
最後にまとめになりますが、国が医療費を減らそうとする中で、今日聴いていただいているクリニックの先生方は、その方向性さえ間違えなければ、生き残っていけるはずです。
もし、国の方向性がおかしいと感じるのであれば、自費診療の分野を広げるしか道はなくなってきます。
保険診療でやっていくならば、厚労省や国の意図を読み解く必要があります。
その意図とは、薬を減らし、来院日数を減らし、無駄な検査をなくすという流れなので、経営的には明らかにマイナスに振れます。
その中で、どうやって患者さんからの人気を得て、患者数を増やし、それをどう捌いていくかという課題に直面するでしょう。
あるいは、検診を増やしたり、自費の医薬品や検査に取り組んだり、予防医療に関わっていくというのも、これから重要なテーマになるかもしれません。
(高山)そうですね。
(大西)そうしたことを読み解く必要があります。5回にわたって話してきた内容のまとめとしては、次の診療報酬改定も厳しくなることが予想されるので、準備を怠らず、国の方針を見誤らなければ、経営はもう少し楽になるのではないかと思います。
(高山)うまく舵取りをしていただき、こういった方針について質問や疑問がありましたら、ぜひ投稿していただければと思います。
皆さんからのご質問をお待ちしております。ということで、続きはまた次回にしていきたいと思います。今回も大西さん、ありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。