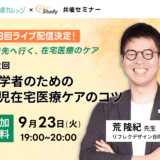PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第74回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか。
今回のテーマ:「失敗しない開業」
(高山)今日のテーマは前回に引き続きになりますが、クリニック開業のトレンドとして、今後「失敗しない開業の仕方」を語っていきたいと思います。
(大西)成功する開業の仕方の本はたくさん出ていますからね。あえて「失敗しない」、あるいは「こうしたら失敗するよ」という話をしてきたらいいなと思います。
(高山)ぜひ失敗例を参考にして成功につなげていただく、ということでこの後、失敗例について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
開業の失敗談①:立地選び
(高山)では逆張り戦略ということで、失敗談ですね。「こんな失敗がありますよ」というようなことを教えていただければと思うのですが、まず1つ目は何でしょうか?
(大西)立地ですね。
(高山)立地。立地で失敗することもあるわけですね。
(大西)あるんですよ。これが僕が経験した失敗例ですが、実は「駅前立地で、これはいい」と思って開業したものの、そのエリアはどんどん人がいなくなる場所だったんです。
(高山)いなくなるエリア。
(大西)もう一つ駅ができてしまったんです。
(高山)ああ、はいはい。
(大西)新しい駅の方に人がざあっと動いていって、元のエリアはどんどん寂れていきました。
(高山)そんなことがあるんですね。
(大西)あるんです。最近の再開発は、めちゃめちゃ怖いですよ。
(高山)そうですね。今までなかったところに、長期計画ではあったんでしょうけど、駅ができたりというのは山手線でも最近ありましたからね。
(高山)高輪ゲートウェイとか。
(大西)そうです。その先生は、その計画を知らずに「駅前立地だ」ということで開業されたんですよね。
その駅は昔ながらの駅でした。だから当然、昔からの住民が住んでいた。昔からの住民はみんな高齢者なので、その後どうなるかというと、家は空き地になり、その人たちは老人ホームに入っていく、というようなエリアだったんです。
(高山)なるほど。これは高輪の話ではないですよね。
(大西)違います。違うエリアです。
診療圏調査の落とし穴
(大西)気をつけなければいけないのは、自分が駅前立地で「これはいいぞ」と思っていて、診療圏調査の結果も良かったケースです。
よしと思っても、その診療圏調査が5年前のデータだったりするんです。5年前の国勢調査のデータなので、5年も経てば実は人口が激減している地区だった、ということがあります。
(高山)なるほど。
(大西)「なんでかな?」と思ったら、同じエリアに別の駅が2つもできていた。そこにマンションがばんばん建って、クリニックモールもできて、患者さんが全部そっちに流れてしまった、と。
(高山)そうなってしまうと、もう引っ越すしかないですか?
(大西)引っ越しました。先生と一緒に、引っ越し先であるクリニックモールの中へ。
(高山)苦労されましたね、その先生は。
(大西)いやあ、損をしましたね。ただ、これは意思決定が早かったからよかったんです。
意思決定せずにずるずる行っていたら、今頃大変だったなと思います。
(高山)そうですよね。それまでの患者さんも大事ですけど、やはり成り立たなくなってしまうと大変ですから、早めに決断していかないといけませんね。
(大西)そうなんです。この立地の難しさは、開業した時は患者さんが多いのに、じわじわと減っていく点です。
この減るスピードが意外とゆっくりだと、気づかないんですよ。
(高山)何が原因か分からないですもんね。
(大西)分かりません。ただ僕は、この立地の問題において、地域に駅ができるとか、マンションが建つとか、もっと言えば「なんでこんなに良い立地なのに誰も見向きもしないんだろう」という場所には、何か原因があると思っています。
(高山)そうですね。
(大西)そういうことを調査せず、診療圏分析だけを信じたから見抜けなかった。
(高山)診療圏分析のデータが古いというのも一つありますけど、やはり町を歩いて、どんな状況なのか自分の目で確かめた方がいいですね。
(大西)そうです。僕はなんなら「住んだ方がいい」と言っています。やはり、住んでみないと分からないですよ。
(高山)そうですね。
個人開業のリスクと街の変化
(高山)そういう意味では、個人で全くの新規開業をするのは、やはりリスクに感じますよね。
(大西)そうなんですよね。
(高山)経営がしっかりしたグループで、店舗開発の部署がきちんと調査をして、そこで開業する。
最初は雇われかもしれませんが、そこで院長をやるという選択の方が、安心は安心ですよね。
(大西)そうですね。例えば、ショッピングセンターができたことによって町が一つ消えるなんてこともよくあります。
どこのショッピングセンターとは言いませんが、そういう場所は集客力がものすごくありますから。
(高山)ありますね。
(大西)それができると、人がみんなそっちに向かって住み始めます。すると、元々の商店街は全部駆逐されてしまう。
その商店街の中にあるクリニックは厳しくなりますよね。
(高山)厳しいですよね。商店街問題というのはずっとありますが、一度寂れてしまうともう一度復興させるのは相当難しいですよね。
(大西)新しく作った方が簡単ですからね。
(高山)ええ。
(高山)最近テレビで、横浜近くの野毛という地域が、コロナで飲食店の経営が厳しくなった後、個人開業する若手の飲食店オーナーがどんどん入ってきて、今では若い女性に人気の「野毛飲み」エリアになっていると聞きました。
でも、これはテレビで取り上げられるくらいなので、成功例だとは思うんですが、ほとんどの地域ではそんなことはできないですよね。
(大西)野毛の問題は、僕は横浜在住なので10年見てきて感じることですが、コロナで大打撃を受けました。
もともと「野毛飲み」は昔からありましたが、汚い店のイメージだったんです。
(高山)そうですよね。おじさんたちが来るようなイメージでした。
(大西)そうです。野毛とか黄金町、伊勢佐木町はすごく汚い、つまり古いイメージでした。
古くて昼から飲んでいるおじさんたちがいたので、女性は来なかったんです。逆に。
それが今では、コロナを境にその人たちがどこかへ行ってしまい、お店もすごく綺麗な立ち飲みが増えました。
すると一気に若い女性が入ってきて、おじさんがいないから安心だと。そして若い女性目当てに若い男性も来て、盛り上がったという感じです。
(高山)なるほど。
(大西)うまくいった例と言っても、偶然ではなく、やはりコロナの影響も大きい。あとは、街が少し古くなっていたというのもあるでしょうね。
ただ、そこは横浜駅から一駅ですし、桜木町からもすごく近いエリアなので、「チャンスだ」と思った若い人たちがたくさんいたんでしょう。
(高山)そうですね。そういう世の中の流れというか、トレンドを見抜く力も重要ですよね。
(大西)その街が生きるか死ぬかは、なかなか読めません。ただ唯一読めるのは、近所の再開発の影響は絶対に受けるということです。
再開発があるなら、再開発される側に乗った方がいいです。
(高山)そうですよね。新しい街づくりに参加して、新しい人口を受け入れる受け皿として開業する方が、リスクは少ないでしょうね。
(大西)逆に、商店街問題に巻き込まれていくと苦しくなるので、前回話したように、M&Aをする時に「商店街の中の超高立地案件」というのは怖いんですよ。
(高山)行ってみたら、もうスカスカみたいな感じですね。
(大西)自分のクリニックは出したけれど、周りはシャッター通りだ、みたいなことがあり得るわけです。
ただ、「有名な商店街の中の高立地」と言われると、つい気になってしまいますよね。
(高山)そうですね。
(高山)そこに愛着や憧れがあって、「どうしてもこの地域で出店したい」というなら別ですが、やはり経営が成り立たないところに思いだけで出店するのは、かなり大変になりますよね。
「一本裏の道」と「ビルの価値」
(大西)あと、失敗した事例として、「一本入った道」というのは怖いですね。
(高山)路地ですね。
(大西)路地です。大通りがあって、そこから一本裏に入ると、急激に人の流れが悪くなります。
これ、人の目につかないからか分かりませんが、僕が経験したケースでは、電話での道案内がめちゃくちゃ大変でした。
(高山)ああ、なるほど。
(大西)「そちらに行きたいのですが」と言われた時に、「そのビルの裏手です」という説明になってしまう。
これが大通りに面していたり、有名な通り沿いなら「その通りを入ったところです」と言えるんですが、「そこからもう一本裏です」となると、結構迷うんですよ。
(高山)そうですね。知らない場所には行けないですからね、人間は。
(大西)都心の路地は結構入り組んでいますから、路地の奥の方はあまりお勧めしません。その「一本」が、結構な影響をもたらします。
(高山)いいエリアと言われる場所でも、そういった小さな路地に入ってしまうと、本当に人通りがなくなりますからね。
目的地を設定して行っても、入り口が見つからないこともありますし。
(大西)あります、あります。1階だからいい、2階だから、3階だから、というのは最近あまり関係なくて、そのビルが有名かどうかが大事ですね。
(高山)知名度とか、ですね。「あのビルだよね」と分かっていれば、後からクリニックが入っても「あのビルに入ったクリニックだよね」となるので、行きやすいでしょうね。
(大西)ビルの価値というのもあると思います。「その名前のビルは価値がある」「その名前のビルはあまり価値がない」みたいなものがあるんです。
(高山)なるほど。
(大西)そのエリアの人に聞かないと分かりません。ビルの所有者の問題なのかもしれませんが、「〇〇ビル」と言って通用するビルがいいなと僕は思います。
(高山)そのあたりは、開業を手伝ってくれるコンサルタントの方がしっかり調べてくれて、情報が得られるといいですね。
(大西)そうですね。どうしても開業する先生もその地域に住んでいるわけではないので、ビルの名前まではこだわっていないことが多いです。
(高山)そこまでは、なかなか。
(高山)そもそもクリニックが開業できるテナントビルを探すこと自体が結構大変じゃないですか。
開業できる物件自体が少ないので、先生が「このエリアがいい」と希望したら、無理やりではないでしょうけど、「お勧めはしないけど、ここもありますよ」という形で紹介しますもんね。
(大西)先生側も調べないといけないし、開業コンサルタントも調べないといけない。
もっと言えば、そこの地元の人と話ができたら一番いいなと思います。
(高山)地元の人というと、誰を捕まえればいいんでしょうか。
(大西)本当は、医師会がウェルカムならいいんですけどね。
(高山)ウェルカムじゃない地域もあるでしょうね、今は。
(大西)あります。だから医師会には聞けないし、かといって…というところがあるので、キーマンが誰かというのは、さすがに僕らも分かりません。近所の地主さんなのか、とか。
(高山)昔からいる、街の不動産屋さんとか。
(大西)結局、不動産屋さんや地主さん、そういったところと人間関係を築いていくしかないんでしょうね。
物件オーナーや薬局との関係性
(大西)立地は本当に大事です。そして、ビルの所有者、オーナーさんも結構大事だと思います。
(高山)オーナーさんですね。
(大西)ここの関係が悪くなると、値上げされたり、急に契約を切られたりしますから。
だからやはり、大手の不動産会社や開発会社が所有している物件に入る方がいいというのは、そういうことなのかもしれませんね。
個人のオーナーよりも、少し家賃は高いかもしれませんが、安定はしますからね。
というのもありますし、間に誰か入ってもらうと、その間の人とまた揉めたらややこしいですし。
ビルで開業する際はビルのオーナー、土地から建てる場合は土地のオーナーとの関係は、結構大事な問題だと思います。
(高山)そうですね。あと、薬局との関係性でクリニックモールに入居されるケースもありますが、その辺りも良し悪しをしっかり見ないといけませんか?
(大西)その薬局が関わる場合は、確実に何かしらのマージンが乗っています。
薬局が患者さんを集めてくれるという期待もあるかもしれませんが、一方で薬局側は「先生が集めてくれるだろう」という期待を持っています。
責任の所在が曖昧になっていると、うまくいかないでしょうね。
(高山)そうですね。
(大西)薬局はあくまでオーナーである、と割り切った方が、逆にいいのかもしれません。あまり当てにしすぎない方がいいです。
(高山)結局、薬局が集客するというのはかなり難しいと思います。
(大西)難しいですし、「〇〇薬局が入っているビル」というだけで、知名度が上がるくらいでしょう。
(高山)しかも1階に薬局が入ることが多いですよね。
(大西)そうなると、クリニックは必ず2階以上に入らなければいけない。一番いい立地を抑えられてしまって、区画の自由度もかなり低くなります。
(大西)「そのビルの1階に、たまたま薬局がいた」くらいの割り切り感があった方がいいと思います。
(高山)そうですね。もしこれをお聞きの薬局さんがいらっしゃいましたら、「実際はこうですよ」というのをコメントいただけると嬉しいですね。
(大西)薬局さんも苦労している気がするんですよ。「この区画をいつまでに埋めなければいけない」という状況で、埋まっていない区画をたくさん抱えているわけですから、必死だと思います。
(高山)処方箋の枚数を集めないと商売にならないですし、成り立ちませんからね。
(大西)どうしても、何か別の科が欲しい、と。内科だけでは困りますからね。
本当に苦労すると思います。だから逆の視点で考えると、薬局側が苦労しているからこそ、入る側は慎重になってほしい。
誰もそこを選ばなかったわけですから。しばらく空いているテナントにすっと入るのは危ないかもしれません。
(高山)ますます空いているところが埋まらないという話になってしまいますが、何かしら条件があって、それでも周辺の状況が変わってきて「今まではこういう理由で入らなかったけど、これから隣に新しいビルが建つ」など、状況の変化によって入っていい物件も出てくるわけですから。
その辺り、やはり周辺の状況を見通す力が一番大事なんでしょうね。
建物の構造も「立地」の一部
(大西)立地で、もう一つだけ話をすると、先ほど再開発や路地、オーナーの問題、ビルの名前など色々話しましたが、何はともあれ、立地というのは「視認性」だけでなく「居心地」も関係すると思うんです。
部屋の作りとか。図面が引きにくい立地は、結構きついですね。
(高山)立地というか、建物そのものの話ですね。
(大西)建物の構造も、僕は立地の一部だと思っています。例えば、すごく大きな柱があるとか、コンセントの位置が異常におかしいとか。
一番心配なのは、「え、そっち側にドアを作るの?」みたいなビルがあるんですよ。そういうところに入ると、ずっと苦労します。
(高山)そうですね。
(大西)「すごく寒い」「すごく暑い」とか。こういうのは医療機関として結構致命的だったりします。
(高山)確かに。すごく寒い場所はきついですよね。
(大西)きついですし、すごく暑いところはエアコン代がものすごくかかります。あとは、周りに駐車場が全然ないというのも結構きついですね。
(高山)駐車場問題はありますね。駐輪場もそうですし。
(大西)都心部は特に苦労します。都心は30分でいくら、と駐車料金がすごく高いじゃないですか。
でも、車で生活している人はたくさんいますからね。
まとめ:美味しい話には飛びつかない
(高山)立地だけでも色々考えなければいけないことがありますが、今までは面倒を見てくれるコンサルタントの「ここがいいですよ」という言葉を信じて決めるスタイルが多かったと思います。
しかし、今のお話を聞いていると、先生自身も色々調べて、自分でしっかり判断し、慎重に吟味していくことが必要だということですね。失敗しないためには。
(大西)そうです。失敗しないためには、美味しい話にすぐ飛びつかないこと。
(高山)裏があるぞ、と。
(大西)それは、自分で調査することをお勧めします。
(高山)そうですね。はい、ということで、今回は失敗から学ぶ第1弾として「立地」を取り上げました。次回は、立地以外の失敗談も見ていきたいと思いますので、続きは次回にしたいと思います。大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。