
PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第77回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。
患者視点で作られるクリニックの基幹システム
(高山)今日のテーマは何でしょうか?
(大西)今日のテーマは引き続き、クリニック開業のトレンドです。具体的なテーマとしては、クリニックの予約システム、いわば「基幹システム」についてです。
これまで電子カルテが基幹システムと言われてきましたが、今回は患者さん視点、つまり患者さんを軸に作られた基幹システムについて語っていきたいと思います。
(大西)最近の開業では、どういう患者動線を作るかを事前に決め、かなり作り込むケースが増えています。
その中でも、やはり予約システムが中心的な役割を担っていると感じますので、その点について話していければと思います。
(高山)では、この後よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
進化したクリニック「クリニックフォア」の体験
(高山)実は私、昨日クリニックに行きまして、自分で予約をして診療を受けて帰ってきました。
そのクリニックが非常に動線がスムーズで、初診だったにもかかわらず、とても気持ちよく利用できたという体験をしました。
(高山)そのクリニックの名前は「クリニックフォア」というところで、都内に11医院、その他に埼玉の大宮や大阪の心斎橋にも展開しており、かなり多店舗展開されています。
その仕組みに「ここまで進化したのか」と、とても感動しました。大西さん、このクリニックはご存知ですか?
(大西)最近勢いのあるクリニックですね。
(高山)業界でもよく知られている感じでしょうか?
(大西)先ほどお話しした、動線設計が優れたクリニックとして有名です。
(高山)驚いたのが、まず初診の問診入力が非常にしやすく、予約もスムーズに取れて、来院してから帰るまでがあっという間でした。
こんなにスムーズなクリニックはなかなかないと思い、非常に良かったのですが、このシステムはクリニックフォアが独自に開発しているのでしょうか。
(大西)おそらく、予約関連のシステムは自社で開発しているのではないかと思います。
最近はクラウド技術の発展で開発のハードルが下がってきているので、独自でシステムを組むことも、それほど難しくなくなってきています。
(高山)極端な話、全てのクリニックがこのシステムを導入すればいいのに、と思うくらい使いやすかったです。
新規開業と既存クリニックのシステム導入の違い
(大西)新規開業の場合と既存のクリニックでは、状況がかなり違うと感じています。
新規開業の場合は、理想の動線をゼロから作り込むことが可能です。
一方で、既に運営しているクリニックの場合は、現在の運用方法に合わせる必要があり、システム導入にはかなりの制約が伴います。
これは大きな違いです。
(高山)そうですね。これまでの業務フロー自体を変えなければいけませんからね。
予約システムの進化「順番予約」から「完全時間予約」へ
(大西)これまで予約システムは、「順番予約(番号を発行する)」、「時間予約(時間を指定する)」、そして「時間帯予約(大まかな枠で予約する)」といった形で進化してきました。
しかし、クリニックフォアのような新しいクリニックは「完全時間予約制」を採用しています。
(大西)ある先生から聞いた話ですが、もともと順番予約制だったクリニックが、コロナ禍を機に時間予約制に切り替えたところ、患者数が減るかと思いきや、逆に減らなかったそうです。
(大西)例えば1日に100人の患者さんを診る場合、これまでは100番までの整理券を発行して順番にこなしていくという流れでした。
それを、単純に100人分の予約枠を作り、その枠を埋めるように運営するという考え方に変えたのです。
仕事の進め方を変えただけで、残業も患者さんの待ち時間も大幅に削減できた、という話でした。
初診からのネット予約とキャンセルの課題
(高山)先ほど私が体験したような、初診からのネット予約というのは、多くのクリニックが導入に二の足を踏む傾向にあります。
(大西)その一番の理由は、キャンセルのリスクが怖いからです。
(高山)気軽に予約できる分、気軽にキャンセルもできてしまうということですね。
(大西)それについても、キャンセル率を管理する工夫や、キャンセルをしにくくする仕組みさえ導入すれば、実はそれほど怖がる必要はありません。
また、ある一定数のキャンセルは仕方がない、と割り切ることも一つの考え方です。
「クリニックフォア」の柔軟な運営モデル
(大西)クリニックフォアの裏側にある大きな仕組みの一つは、おそらくアルバイトの先生を多数抱えていて、その先生たちのスケジュールに合わせて予約枠を組んでいることだと思います。
(高山)そうですね。私が行った時も、診察室は3つありましたが、実際に使われていたのは1つだけでした。
(大西)「今日は医師が1人」「今日は3人」という状況に応じて、予約枠を毎日調整しているのでしょう。
「3人いれば100人診られる、1人なら50人」というように、柔軟に対応しているのだと思います。
(高山)予約枠を調整できるから、医師がいる時だけ診察室を開けるという運営が可能なんですね。
(大西)その通りです。例えば、一般的なクリニックは「朝9時から12時まで、ドクター1人」という固定的な考え方です。
しかし、クリニックフォアのような形態では、先生の出勤時間に合わせて予約枠を作るので、必ずしも朝9時に開ける必要はありません。
先生が10時からであれば、10時から予約枠を開ければいいのです。
(高山)予約システム上で予約枠を「×(受付終了)」にしておけばいいだけですもんね。
(大西)そうです。「9時から診療しているけれど、予約がいっぱいです」という見せ方ができます。
開業場所はWeb上へ。新しいクリニックの立地戦略
(高山)外からは中の様子が分かりませんし、予約が基本なので、予約なしで直接来院する人は少ないでしょう。
クリニック自体もビルの5階にあり、さらに興味深いことに、外には目立つ看板がありません。普通のオフィスビルの入り口にある集合案内板に「5階 クリニックフォア」と書いてあるだけで、いわゆる”ふらっと立ち寄る”患者さんを想定した動線にはなっていません。
(大西)これも時代の大きな流れで、クリニックの開業場所はもはや物理的な場所ではなく、Web上になったということでしょう。
(高山)まさにそんな感じですね。
(大西)つまり、実際の地面にはもうクリニックの”入り口”はないのです。Web上に存在し、患者さんを集めています。
これは「場所貸し」のビジネスモデルとよく似ています。
(高山)業種は全く違いますが、例えるなら美容師などに場所(面)を貸すようなイメージに近いですね。
(大西)レンタルオフィスやセミナー会場をWebで探すのと同じ感覚です。空きテナントを整備して最低限診察できる状態にし、そこにドクターを集める。そういう戦略だと思います。
(高山)今、クリニックフォアのクリニック一覧を見ていますが、浅草橋が2階、池袋が2階、大手町は地下1階、渋谷も2階、新橋は9階、心斎橋は10階など、路面店ではない空中階がほとんどですね。
10階のクリニックというのは珍しいです。
(大西)物理的な立地にこだわらないことで、予約なしで直接来る患者さん(直来)を減らしているのでしょう。
初めての患者さんはネットから予約し、2回目以降の患者さんはネット予約の方が早いことを知っているので、やはりネットから予約する。
そういう流れができています。
スタッフの効率化と新しい働き方
(大西)このモデルの最大のメリットは、スタッフの数を最小限に抑えられることです。
以前、同様の業態を取材した際に分かったのですが、受付スタッフは1〜2人で十分運営できます。
常に受付に立つ必要はなく、患者さんが来る時間だけ対応すれば良いので、それ以外の時間は裏で別の業務を進められます。
(高山)私が行った時も、受付は2名体制で、バックヤードに1人、そして診察室に女性の先生が1人という人員配置でした。
(大西)イメージとしては、クリニックフォア側が「箱(場所)」「設備」「スタッフ」を用意し、登録しているドクターは決められた日に来て診療する、という形です。
このように経営と診療を分離することができます。
(高山)受付システムや業務フローは全院で統一されているでしょうから、店舗間でのスタッフの移動もしやすそうですね。
(大西)その通りです。例えば「今日はあちらのクリニックが混んでいるから、そちらに出勤して」というような指示が可能です。
もしかしたら、クリニックフォアというグループ全体でスタッフを採用している可能性もあります。
(高山)都心部に集中して出店しているので、スタッフの移動も容易ですね。
(大西)スタッフは自分のスマートフォンでシフトを確認し、「今日は〇〇院に出勤」「担当は〇〇先生」といった形で動いているのかもしれません。
看護師などにとっても、柔軟で働きやすい環境だと言えるでしょう。
(高山)先生自身も、日によって違うクリニックで診察している可能性がありますね。
(大西)その可能性は大いにありますね。例えば3時間だけの勤務など、短い単位での働き方が可能になっているのだと思います。
フロント業務に特化したビジネスモデル
(高山)各クリニックで診療科目に多少の違いはありますが、ほとんどが内科、皮膚科、そして自費診療(ダイエット、AGA、EDなど)をセットで提供していますね。
(大西)簡単な処置や手術は、対応できる設備のあるクリニックに患者さんを振り分ける、という形を取っているのでしょう。
(高山)なるほど。これは、いわば「コンビニクリニック」というか、医療のフロント業務に特化したモデルですね。
(大西)面白いのは、ビジネスのゴールを「薬の処方」に置いている点です。
複雑な検査や処置、手術といった部分は思い切って切り離し、「簡単な検査と薬の処方」に割り切ることで、ビジネスを成り立たせています。
(高山)その場合、患者一人当たりの単価は上がりにくいのではないでしょうか。
(大西)薄利多売にはなりますが、その分、運営コストを劇的に下げているのです。
スタッフやドクターが時給ベースで働くことで、人件費をかなり抑えることが可能です。
(高山)まさに「隙間バイト」の仕組みが、医療の世界にまで浸透してきた、という感じですね。
(大西)そうです。医師の世界でも、特定の病院に所属しない「フリーランス」の先生が増えてきています。
これまでは「勤務医」か「開業医」という二者択一でしたが、「フリー」という第三の選択肢が当たり前になってきました。
(高山)テレビドラマのような特別なスキルを持つ医師だけでなく、一般的な内科医や皮膚科医の先生にとっても、フリーランスとして活躍できる場が広がってきたということですね。
(大西)マーケティングや運営はクリニックフォア側が全て担ってくれるので、医師は診療だけに集中できるわけです。
(高山)その裏側には、医師に対する評価システムのようなものもありそうですね。
(大西)おそらく、ドクターの評判をデータ化しているはずです。評判の良い先生にはより多くのコマ(診察時間)をオファーし、評判の悪い先生は減らす、といった調整が可能です。
(高山)将来的には、参加する先生が増えることで、よりそうした運営が色濃くなっていくかもしれませんね。
(大西)これもまた、新しいクリニックの形だと思います。
(高山)そうですね。ということで、今日は時間になりましたので、この続きは次回に回したいと思います。
(大西)はい。
(高山)大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
少しでも気に入っていただけましたら、番組のフォローをぜひお願いします。
新しいエピソードがいち早く届きます。
番組への感想はハッシュタグ「#院長が悩んだら聞くラジオ」をつけて投稿いただけると励みになります。こ
の番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
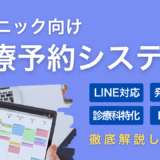 【2025年最新版】クリニック診療予約システム27製品比較|料金・選び方・導入事例まとめ
【2025年最新版】クリニック診療予約システム27製品比較|料金・選び方・導入事例まとめ
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。
