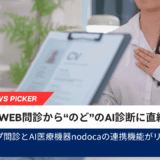PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第80回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
今回のテーマ:「給料の決め方」
(高山)今日のテーマはですね、ずばり「給料の決め方」ということでやっていきたいと思います。
(大西)80回という節目の回にいいテーマですよね。いいテーマというか、難しいテーマですね。
院長先生が一番悩んでいることじゃないかなと、今は思います。
(高山)そうですね。具体的にどう給料を決めていけばいいのか、また今後の方向性について考えるきっかけになればなと思いますので、この後よろしくお願いいたします。
(大西)お願いします。
(高山)スタッフの給料ですが、スタッフと言っても職種はいくつかあります。
事務長さんがいるところは事務長さん、それから事務スタッフの方、あとは看護師、そのほかにもサポートスタッフがいるクリニックもあるかもしれません。
院長はご自身で決めるととして、院長以外の給料の決め方を教えていただきたいなと思っています。
クリニックの状況や規模によってかなり違ってくると思うので、そのあたりも踏まえながら教えていただきたいです。
国が給料決定に関与?ベースアップ評価料の影響
(大西)クリニックの経営が今大きく変わろうとしているのは、2年に1回の診療報酬改定です。
今度26年改定があるのですが、国が初めて「ベースアップ評価料」という、給料に直接影響する点数を作ったことが大きいですね。
これは結構大きな事件です。簡単に言うと、これまで給料の決め方はクリニックや病院に委ねられていましたが、そこに国が関与し始めたというのは、すごいことだと思います。
だって、普通は何かをしたら診療報酬点数が付くじゃないですか。ベースアップ評価料は、給料を上げたら付くという、初めて見る点数の付け方なんです。
いわゆる「体制加算」なのですが、例えば「看護師が何人いたら何点」「医師事務作業補助者が何人いたら何点」というのはこれまでもありました。
人員配置基準で点数を決めていたわけです。
しかし今回は初めて、給料を上げたら点数が上がるという仕組みになりました。
患者さんからすると何のことやらという話でしょうが、これがきっかけで給料の決め方に悩み始めている先生が多いと感じます。
(高山)給料のコントロールを国がし始めたということですね。
(大西)下駄を履かせてくれているわけですが、過去に介護業界であったのは、この下駄を履かせた分を全部経営者が取ってしまったという事例もありました。なので、こういうやり方が本当に健全かどうかは少し疑問です。
給料アップの原資とクリニックの経営状況
(高山)これもやはり経営状況によると思います。ベースアップできた分だけ還元できる利益体質があるところと、それを払うと赤字になってしまうから少しでも足しにしないと、という状況のところもあるでしょう。
クリニックの場合は赤字経営は少ないかなと思いますが、もしかしたら介護施設よりも着実に反映が進むのかもしれないと想像しました。
(大西)儲かったらお金をあげるという考え方と、先行投資としてお金をあげるという考え方は違いますよね。
ルールをしっかり決めておけば、ベースはちゃんと上がっていくはずです。だから、このルールをどう決めるかというのが給料の決め方の本質なのでしょう。
給料のルール作りとキャリアプランの重要性
(高山)そうですね。職種によっても変わりますが、これは人材への「投資」になると思うので、消費するような給料の決め方だと、本当に使い捨てのようになってしまいます。
そういう意味では、計画的に上がっていくプラン、つまりキャリアプランのようなものがあって、働いている人が「こうやっていけば給料が上がるんだな」という希望が持てる制度が作れるといいですよね。
(大西)その通りです。事務職の平均離職率は3年くらいだそうですが、中には20年働いている人もいます。
もし20年間ずっとベースアップし続けたら、とんでもない給料になってしまいますよね。
女性が多い職場なので、結婚、出産、育休、そして復帰というサイクルもありますから、キャリアプランをちゃんと設計してあげないと、なかなか職場に戻ってきてもらえません。
結婚・出産しても帰ってこれる職場をどう作るか、という課題でもあると思います。
(高山)お金以外の報酬、例えば働きやすさや居心地の良さといった部分も重要ですね。
給料を上げ続けるのには限界がありますから。アッパーまで行ってしまった場合に、何を楽しみにして仕事してもらうか。
(大西)そうなんですよ。例えば笑い話ですが、時給が毎年10円しか上がらない場合、10年で100円上がります。
でも、昨今の情勢では毎年100円、200円上がる時代ですから、「なんじゃこりゃ」となりますよね。
インフレと診療報酬のジレンマ
(大西)やはり給料はインフレ率に連動させなければいけません。ただ、ここがクリニックの一番難しいところで、クリニックの診療報酬点数がインフレにあまり連動していないのです。だから、経営はどんどん苦しくなります。
前回、福利厚生のところでも話したように、「何をもって給料を上げるか」という基準が重要です。
ずっと何もしなくても給料が上がるのではなく、能力が上がったり、経験が増えたり、資格を取ったり、役職に就いたりといった、手当系の給料の上げ方の方がやりやすいでしょう。
(高山)そうですね。役割を広げてくれた分、その責任の重さとして給料を上げていくというのは分かりやすいです。
(大西)今、国は4%の賃上げなどを進めていますが、医療機関に対しては毎年2.5%上げてほしいという話がずっとありました。
2.5%が福利で上がっていくととんでもない額になるので、おそらく景気が落ち着けばこのベースアップという考え方はなくなるでしょう。
だからそれよりも、繰り返しになりますが、給料アップの対象となる「項目」を作ってあげたいですね。測る尺度というか。
(高山)物価に対応するために、このベースアップ評価料があるわけですね。
(大西)そうです。ベースアップは物価連動とし、それ以外は個人の資質によって給料が変わる。
みんなが同じように給料が上がる時代はもう終わっているのだと思います。
これからの事務職に求められる「ダブルライセンス」
(大西)先日、医療事務の専門学校の学生たちに話を聞くと、「長く働く」という考え方が減りましたね。
きつい時代になったなと感じます。残業はしない、有給は取る、できれば定時に帰りたい。でも給料は欲しい、という人が多いようです。
一方で看護師は逆で、残業も夜勤もOKという人が多い。また、最近は看護学校や事務学校が廃校になっているという話も聞きます。
医療を目指す人が「あれ、他の業界より給料が上がらないぞ」と気づき始めたのかもしれません。これは結構怖い話です。
(高山)多様化というか、職業がたくさんありますからね。看護師を目指す人は、お金というよりは仕事の内容で選んでいるのではないですかね。
(大西)ただ、資格を取ってそれが給料に跳ね返るから、という人もいます。
看護師という国家資格を取ることで、ベースの給料が200万円ほど上がる。だから投資しても回収できる、と。
一方で事務職は、資格を取っても国家資格ではないので宙ぶらりんになりがちです。
このままだと、クリニックは事務スタッフを全く採用できなくなるかもしれません。
(高山)今後、長い目で見たときに、事務職は必要な職種なのでしょうか。
(大西)ぶっちゃけて言うと、診療報酬も効率化され、受付も無人化が進んだときには、別の職種になっているのではないでしょうか。
最近の流行りでいうと、医師事務作業補助者(クラーク)や医療コンシェルジュ、さらには広報や企画といった役割です。
一般企業と同じですね。ただの事務ではいらないけれど、広報が得意、企画力がある、という人は採用される。クリニックも当然その流れになると思います。
(高山)なるほど。磨くべき能力が違ってきますね。
(大西)だから僕はいつも「ダブルライセンス」と言っているのですが、事務をやった上で何をやるか、看護師をやった上で何をやるか、というのを考えるべきですね。
スタッフの隠れた才能を引き出す評価制度
(高山)なるほど。でもそれを考えて採用するかしないかで、未来は大きく変わりますね。
(大西)変わります。例えば、ホームページやInstagramの運用を任せたい事務スタッフがいれば、その分の手当を付けてあげられるわけです。
普段は受付をしていても、1日2時間だけ広報活動をしている人もいます。
(高山)そういう知識を持つ人は、新卒ではないかもしれませんね。経験者が事務の勉強をして入ってくるのか、専門学校卒の新卒が別に勉強して力をつけるのか。
(大西)別の業界から事務職に入ってくる人たちが、一番早く戦力になるでしょうね。元デザイナーや元イラストレーターといった人が、「面白い」と採用されるケースもあります。
先日あったのは、スカンジナビア航空の元CAさんを採用したクリニックです。4カ国語くらい話せるそうで、その地域は外国の患者さんが多く、言葉が重要だったからです。
元々CAさんなので接遇は完璧で、スタッフの接遇トレーニングをしてもらったり、コミュニケーション能力を活かして問診票の作り替えをしてもらったりしたそうです。意外と他業種からの転職はアリですよね。
(高山)よくその世界に飛び込みましたね。
(大西)田舎だったので、他に仕事がなかったのかもしれません。専門学校の学生にはいつも言っているのですが、「今のやりたいことを諦めなくていい」と。YouTuberやインスタグラマー、ゲーム実況を趣味でやっている学生もいます。
ある学生から「イラスト業界に行くべきか、それともイラストは趣味にして事務職に就くべきか」と相談されたとき、「両方やればいいじゃない。クリニックでもイラストの仕事はあるよ」と話したら、今、実際にやっています。
(高山)それは大西さんだからこその発想かもしれません。新規開業ならまだしも、長年やっているクリニックだと現状維持になりがちです。
(大西)その通りです。僕がコンサルに入った時にまずやるのが、「委員会活動」で役割を明確化することです。
そうすると、スタッフの意外な特性が発見できます。整理整頓が抜群に得意な人は美化委員、SNSが得意な人は広報室、といった具合です。ベースの仕事とは違う仕事が得意な人は意外といるんです。
それを発見することが大事で、「給料の決め方」というテーマですが、実は給料よりもその人の資質を見極める力の方が重要なのかもしれません。
(高山)そうですね。事務の方を「事務」としてしか見ていないと、一側面しか見えず、給料も上げられない、ということになりますね。
(大西)そうです。だから「イラストを1枚描いたら1万円」という先生もいます。外注するより、中の事情を知っているスタッフが描いた方が良いものができますから。
そうやって院内で練習しているうちに、他のクリニックにそのイラストを売りたい、なんて相談を受けることもあります。
(高山)アイデアを出せる人もいいですね。
(大西)アイデアを出せる人。これはちゃんとお金で評価してあげたい。企画手当をつけても面白いかもしれません。企画1本いくら、とか。
(高山)その質の判定が難しいですが。
(大西)難しいですね。でも、例えば「患者が減っている。増やす方法をスタッフ全員から募集して、最優秀賞に手当を出す」といったやり方も考えられます。
そういう空気を作れたら、すごいことだと思います。毎月企画を出せば、12の企画が走る。そのうち1つでも成功すれば十分です。
ボトムアップで考えると、びっくりするくらい斬新な企画が出てきますよ。
(高山)そういうアイデアは、みんなで出した方が柔軟な発想で出てきますね。
(大西)「新奇歓迎」、つまり新しいこと、奇妙なことを歓迎する姿勢が大事です。下の子たちは「変なこと言ってるかも」と恐る恐るアイデアを出してきます。
その時に「面白いね」と言われたら、モチベーションが上がりますよね。
僕自身もアイデアマンな方ですが、サラリーマン時代はそれが給料に全く反映されませんでした。もし反映してくれていたら、絶対に会社に残っていたと思います。
まとめ:成長を促す給料制度とは
(高山)まず認めてもらうこと、採用されたらさらに素晴らしいし、それが推進されて結果が出たらもっと嬉しいですね。
(大西)自分の給料が、チャレンジによって得られるものである方が健全です。「私には何の能力もない」という人でも、今から磨けばいい。
そして、どのベクトルに走ればそのクリニックで評価されるかを、院長が示してあげるべきです。
(高山)目的やビジョンをしっかり掲げて、それに対するアイデアを募集したり、新しい取り組みに巻き込んでいく、ということですね。
(大西)そう思います。アイデアの有無ではなく、スタッフが成長できるような給料の決め方をしてほしい。
今日のまとめは、「成長の源泉が給料であるべき」ということです。成長するためのインセンティブですね。
ただ、のんべんだらりと給料を上げ続けるのは、いつか破綻してしまうと思います。
(高山)ということで、今日は給与の決め方についてお話ししていただきました。
今後もクリニック運営や経営に関するマニアックな話もしていきたいと思います。それでは続きは次回に。今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
少しでも気に入っていただけましたら、番組のフォローをぜひお願いします。新しいエピソードがいち早く届きます。
番組への感想はハッシュタグ「#院長が悩んだら聞くラジオ」をつけて投稿いただけると励みになります。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。