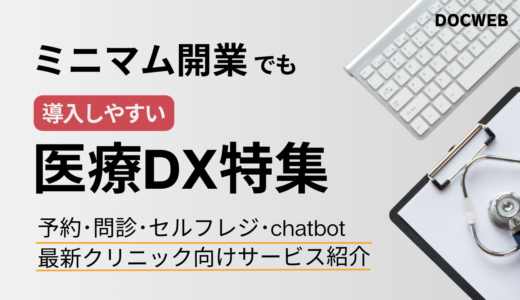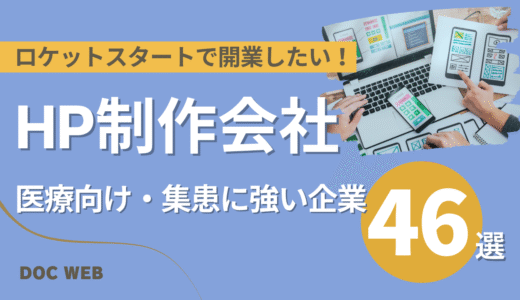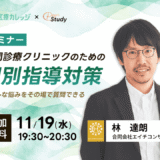PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第81回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
受付電話の最適化と無人化時代への移行
(高山)今日のテーマは、クリニックの受付電話の最適化ということで、お話を進めていきたいと思います。
(大西)クリニックにおいて電話対応は大事な仕事だと思います。
しかし、その電話対応が、逆に受付スタッフの負担になっているという話をよく聞きます。
「受付を一人増やしてください。なぜなら電話がたくさん鳴るからです」といった会話は、よくある話です。
実は、人を増やしても解決しない問題だというお話ができればと思います。
(高山)それでは、今後「受付無人化時代」に突入していく中での電話対応の最適化について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いいたします。
「受付無人化時代」の現状と過渡期の課題
(高山)私たちのエピソードの中で、過去を遡ってみると「受付無人化時代」というキャッチーな言葉に反応してくださるリスナーさんが多い、という印象があります。
ただ、「受付無人化」といっても、完全にスタッフをゼロにするわけではなく、様々なシステムや仕組みを導入したとしても、何人かはスタッフが必要になりますよね。
現状は、本当に人の力だけで運営してきた時代から、そうした無人化の時代へと移行していく過渡期だと思います。
リスナーさんの中にも、まだ特別なシステムは使っておらず、かかってきた電話はすべて受付スタッフが対応している、というクリニックも多いのではないでしょうか。
最近は自動電話対応のシステムもクラウド化され、昔のように何百万円もかけて導入するという感じではなくなってきていますよね。
クリニックもそうした仕組みを活用しながら、最適な電話対応のフローを構築できる時代になってきたかと思いますので、そのあたりの最新事例や今後の流れについてお伺いできればと思います。
電話が苦手なスタッフの増加という新たな課題
(大西)最近の電話対応における一つの流れとして、そもそも電話が苦手なスタッフが増えている、という点が挙げられます。
(高山)電話をあまり使わない世代ですものね。
(大西)そうなのです。スマートフォンを持っていても、電話機能はあまり使わず、メッセージでのやり取りが中心です。
そうした環境に慣れてしまうと、「電話が怖い」と感じたり、電話が鳴っているのに取らなかったりするスタッフも珍しくありません。
誰かが取ってくれるだろう、と。
あるいは、本当に苦手で、電話に出るだけでおどおどしてしまう人もいます。
専門学校で学生に研修を行う際にも、電話応対のトレーニングがありますが、やはり苦手そうな学生が多いですね。
(高山)それは時代の流れなのでしょうか。
(大西)電話には慣れも必要ですが、普段から電話を使わない人にとっては、もはやコミュニケーションツールとして選択肢に入っていないのかもしれません。
(高山)私も最近はあまり電話を使わないので、とっさに言葉が出てこないことがよくあります。
(大西)電話を主なコミュニケーション手段とする世代が60代、70代だとすると、それより下の世代は、もはや電話をしない層なのかもしれませんね。
(高山)若い頃はかなり使っていましたが、機会が減ると慣れもなくなり、不慣れになっていく、ということですね。
電話問い合わせを減らすためのホームページ活用術
(大西)もう一つの背景として、電話で質問して答えてもらうよりも、ネットで検索した方が早い、というケースが多いことも挙げられます。
(高山)「ちょっと聞いてみよう」という感覚がなくなりましたね。
(大西)ですから、電話を減らすための一つのポイントは、分かりやすいホームページを作ることです。
(高山)ホームページを見れば解決するようにする、ということですね。
(大西)その通りです。よく「ホームページに書いてあります」と受付の方が答える場面がありますが、重要なのは「書いてある」ことではなく、患者さんがその情報に「たどり着ける」かどうかです。
その動線設計がうまくいっていないホームページは、結果的に電話問い合わせを減らすことができません。
(高山)ご指摘の通りでございます。
(大西)そこを軽視してはいけません。
患者さんが早く情報にたどり着けるように、逆算して導線を設計する必要があります。
そうすれば、電話は自然と減っていくはずです。
(高山)電話が減ると、スタッフはさらに電話に不慣れになって、余計に対応が難しくなる、という悪循環もあり得ますね。
自動音声応答(IVR)は過去のもの?
(大西)私がいつも電話研修でお伝えしているのは、「人間は一度に多くのことを理解できないので、伝えたいことは絞りましょう」ということです。
セミナーなどでも、「たくさんの情報をお伝えしても忘れてしまうので、今日はこれとこれだけ覚えて帰ってください」というような言い方をします。それと同じことですね。
(高山)一方で、最近は自動音声応答のシステムもかなり充実してきていると思いますが、クリニックに導入することで電話対応は楽になるのでしょうか。
(大西)うーん、昔は流行りましたが、最近は下火かもしれません。「1番、2番、3番…」とプッシュ操作で進んでいくのが面倒だと感じる患者さんが多いようです。
(高山)今のスマートフォン時代なら、電話をかけると画面にボタンが表示されるなど、もっと操作しやすくなってもよさそうですが。
電話からチャットボットへ:新しいコミュニケーションの形
(大西)そうなると、チャットボットを使うケースが多くなります。
そもそも電話をすること自体に抵抗がある若い世代にとっては、最初からチャットで問い合わせて、チャットで返事が来る方が自然です。
それがリアルタイムであればあるほど、電話よりもチャットを選ぶでしょう。
(高山)チャットボットも、対応できるのは途中までですよね。
(大西)そうです。つまり、コミュニケーションの手段が電話からチャットに置き換わってきているのです。
今後はAIチャットが流行りそうですね。
(高山)ちゃんと稼働すれば楽だろうなと思う一方で、本当にうまく機能してくれるのか、という不安もあります。
(大西)それは業者選びが非常に重要になります。
(高山)何かお勧めの業者はありますか?
(大西)会社名は伏せますが、選ぶべきポイントは、サポートがどれだけ手厚いか、という点です。
(高山)システム系はサポートの充実度を重視すべきだと、大西さんはいつもおっしゃっていますね。
(大西)どうしても「あとはご自身でやってください」というスタンスの会社が多いのです。
その背景には、電話の話と同じで、現代人のコミュニケーションの特性があると思います。
今の人は、自分の言いたいことは言いますが、人の話をあまり聞かない傾向にあります。
それがチャット文化の弊害でもある、と。
自分の聞きたいことを伝え、その答えが返ってきたら、そこで会話は終わりです。
雑談のようなコミュニケーションが生まれにくくなっています。
業者側も合理的なので、「マニュアルを送ります」「遠隔でサポートします」という対応になりがちで、だんだんと冷たい感じになってしまいます。
(高山)しかし、クリニックとしては、相手は病気で困っている人だ、という大前提を忘れてはいけません。
(大西)そうした患者さんの心情まで汲み取ったシステムを構築するのは、かなりの手間がかかるので、まだ完全に対応できているところは少ないかもしれませんね。
(大西)ただ、逆にロボット(システム)が相手だからこそ、クレームになりにくいという側面もあります。
DXで「苦手」を克服する新しい働き方
(大西)今日のテーマである電話対応の最適化という点では、電話だけに依存せず、様々なコミュニケーションツールを使い分けていくことが、これからの時代に求められます。
そして、これは高山さんにもお聞きしたいのですが、苦手なことの克服には、ものすごく時間がかかりますよね。
(高山)辛いですね。
(大西)だから、「苦手」な部分をデジタル化で補う、というのが最近のトレンドなのだと思います。
(高山)それはよく分かります。
電話対応が苦手なスタッフがいるのであれば、その部分をシステムで補う、というのは非常に理にかなったストーリーですね。
(大西)一つ例を挙げると、「事前に患者さんに電話をしなければならない」という業務があったとします。
しかし、電話が苦手なスタッフが担当すると、患者さんが出なかったりして、うまくいきません。
それならば、チャットやLINEを使ってみてはどうか、という提案をします。
(高山)なるほど。つまり、受付スタッフだからといって、必ずしも電話対応が得意である必要はなくなってきている、ということですね。
院長とスタッフの意識のズレを埋める
(大西)もう一つ、院長先生自身の尺度で物事を考えてはいけない、という点も重要です。
院長先生は「電話の方が早い」と思っているかもしれませんが、スタッフは「電話は遅い」と感じています。
この意識の違いに、早く気づいてほしいのです。
(高山)電話は「繋がれば」早いですが、繋がらないことも多い。
そして繋がったと思ったら、受付の対応が微妙で、かえってマイナスになってしまうこともある、ということですね。
(大西)そうです。そして、伝えたい情報が「今すぐ」でなければならないのか、それとも「後で読んでもらえれば良い」のかを考える必要があります。
ほとんどの情報は後者です。緊急性が高いのは、薬局とのやり取りくらいでしょう。
それも、最近の若い世代はLINEなどでも返信が早いですからね。
そうした点を踏まえて、私が推奨するのは、「電話を補うためのDX(デジタルトランスフォーメーション)」であり、その前提として、スタッフの「得意・不得意」をしっかり見極めることです。
自院に合ったコミュニケーション手段の最適化
(高山)もし電話対応が得意なスタッフが揃っているのであれば、電話を中心とした運用でも良い、ということでしょうか。
(大西)患者層が高齢者中心であれば、その方が「優しいクリニック」になりますね。
(高山)理想はそうかもしれませんが、患者層によっては、必ずしも電話対応を最優先にする必要はない、と。
(大西)その通りです。
(高山)ぜひリスナーの先生方、あるいは事務長の方々も、ご自身のクリニックの状況を再検討し、電話対応の最適化を図っていただければと思います。
では、この続きはまた次回にしたいと思います。大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
少しでも気に入っていただけましたら、番組のフォローをぜひお願いします。新しいエピソードがいち早く届きます。
番組への感想はハッシュタグ「#院長が悩んだら聞くラジオ」をつけて投稿いただけると励みになります。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。