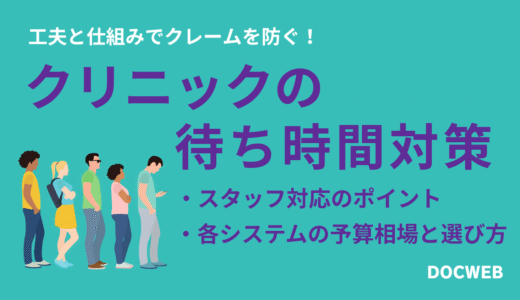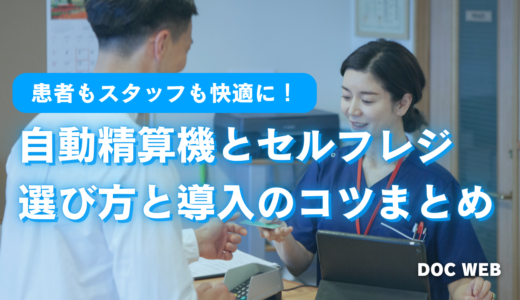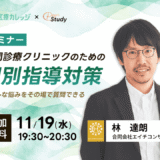PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第82回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか?
受付会計業務の最適化と無人化時代
(高山)今日のテーマは前回に引き続き、「受付無人化時代」をどう乗り切るかということで、今回は特に「受付・会計業務の最適化」についてお話をしていきたいと思います。
(大西)受付や会計に、AI受付、自動精算機、セルフレジといったシステムが続々と導入されてくると、最終的には「無人化」という方向性を考えることになると思います。
ただ、それにはうまくいくケースとうまくいかないケースがある、というお話ができればと思います。
(高山)それでは、この後よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
スーパーマーケットに見る「無人会計」の現状
(高山)今日はクリニックの受付・会計業務の最適化というテーマですが、最近、私の住む地域でもスーパーの無人会計がだいぶ増えました。
大西さんのところでも増えているかと思います。
私が住んでいるのは東京の下町で、高齢者がかなり多い地域です。スーパーの品揃えもそれに合わせたものになっています。
私はいつも晩酌セットのような決まったものしか買わないので、並ばずにパッと会計を済ませたいと思っていました。
この半年ほどで無人化がかなり進み、今では会計方法が3種類ほどあります。
まず、スタッフがいる「有人レジ」。
次に、私が使っている「スマホ決済」。
そして「セルフレジ」です。このセルフレジも、現金が使えるものとカード専用の2種類があり、客が自由に選んで並ぶ形です。
この仕組みのおかげで、レジで並ぶことがほとんどなくなりました。
(大西)ユニクロや無印良品も、ほとんどが無人レジですよね。6台のレジに対してスタッフが1人いる、くらいの配置です。
(高山)ユニクロや無印良品のお客さんの層は30代から50代が多いので、ある程度は自分で対応できるのだと思います。
一方で、先ほどのスーパーで有人レジに並んでいる人を見ると、やはり年齢層が高めの方が多い印象です。
これは前回の電話の話と同じで、患者さんの層に合わせて会計システムをデザインすべき、ということでしょうね。
クリニックにおける自動精算機の導入事例
(大西)先日、ある整形外科の事例を見ましたが、整形外科は自動精算機の導入が最も多い診療科の一つです。
その理由は、多くの患者さんの料金が同じだからです。
銭湯のようなものですね。
みんな同じ330円、といった具合です。そうなると、セルフレジや自動精算機は非常に向いています。
逆に、受付で様々な対応が必要になるクリニックでは、有人のほうが向いている場合もあります。
先日考えたのですが、受付の無人化と会計の無人化では、やはり高山さんがおっしゃるように会計の無人化の方が進めやすいと感じます。
診察が終わったらすぐに帰りたい、というニーズが高いからです。
では、なぜ受付の無人化はなかなか進まないのでしょうか。
受付の無人化が難しい理由
(大西)一番の理由は、新患(初めての患者さん)がいるからです。
初めて来院した方は、院内の勝手が分からないため、誰かに質問しないと前に進めません。
(高山)確かにそうですね。動線が分からないと、どこで待てばいいのかも分かりません。
(大西)その方たちのために、有人受付は少なくとも1人は必要になります。
クリニックの新患比率は、だいたい1割から2割です。つまり、10%ほどの方は有人受付を使い、残りの90%は無人システムを利用する、という形になります。
やはり、受付から人をゼロにすることは難しいのです。
スーパーに複数種類のレジがあるように、クリニックも選択肢を用意する必要があるということですね。
ただ、明らかなのは、待ち時間が減っているということです。
重要なのは、待ち時間を減らすことであって、完全に無人化すること自体が目的ではない、という点がポイントです。
無人化で生まれた時間をどう活用するか?
(高山)スーパーの例で言うと、スタッフの数は以前とさほど変わっていません。
レジに張り付く時間が減った分、品出しなどの業務に時間を割いているようです。
(大西)非常に良い点に気づかれましたね。クリニックも同じです。
よく先生方から「最初から人を雇わなければいいのでは?」と質問されますが、それは少ない運用を前提とした話です。
すでにスタッフを雇っている場合、簡単に解雇はできません。
だからこそ、「空いた時間に何をさせるか」が非常に重要になります。
クリニックにおける「品出し」とは、具体的にどのような業務になるのでしょうか。
診療科目によって異なりますが、基本的には「診察室に入っていくこと」だと考えています。
看護師のサポートや医師のサポートなど、サポート業務全般がそれに当たります。
(高山)なるほど。会計スタッフがそうしたサポートに入ることで、先生や看護師さんも助かりますね。
(大西)実は、そこが待ち時間の本当の原因だった、ということに気づくのです。
(高山)会計スタッフは、これまではただ待っているだけでしたからね。
(大西)マイナンバーカードの導入で保険証の登録作業がなくなった今、会計スタッフには時間的な余裕が生まれているはずです。
将来的には、保険証も公費の証明書もすべてオンラインで確認できるようになり、患者さんが来院する前に資格確認が終わっている時代が来ます。
そうなると、受付業務はさらにシンプルになります。
(高山)診察そのものに時間がかかるわけですから、その周辺業務を手伝ってもらう、ということですね。
(大西)そうです。耳鼻科などでは、先生の隣にいるのは事務スタッフであることがほとんどです。
眼科、皮膚科、耳鼻科あたりは、先生の周りの業務を事務スタッフが担うケースが多いです。
患者に寄り添う「人間らしい」サービスの重要性
(大西)面白い話ですが、患者さんが一番時間がかかるのが、洋服を脱ぐことだったりします。
(高山)それはコントロールできませんね。
(大西)しかし、スタッフが手伝ってあげれば良いのです。
最近はセクハラの問題もあり、先生方は患者さんに触りにくい状況にあります。
だからこそ、女性スタッフが介助する。これも立派な仕事です。
(高山)それは非常に分かる気がします。
(大西)冬場に厚着をしてきた高齢の患者さんが、診察室でゆっくりと服を脱ぐ光景はよくあります。
(大西)よっこいしょ、と脱ぐのに倍くらい時間がかかります。
「お手伝いしましょうか」と声をかけたり、先生が来る前に脱ぐのを手伝ってあげたり。
他にも、ベッドに寝かせる、靴下を脱がせる、診察室へ誘導するなど、これまで看護師がやっていた業務の中には、医療免許がなくてもできることがたくさんあります。
(高山)人員配置を転換する、と聞くと大げさですが、受付や会計業務を効率化することで生まれた時間を使って、診察そのものの時間を短縮できるということですね。
(大西)そうです。そして、そうした業務は人間ならではの仕事です。
患者さんと「触れ合う」ことは、非常に人間らしいサービスであり、そこは手厚くすべきです。
逆に、触れ合いのない事務的な仕事は、人を減らしていく。
そう考えると、受付無人化の本当の意味が見えてきます。
受付無人化の本質は「コンシェルジュ・サービス」の実現
(高山)受付の無人化というと、無機質で合理的なイメージが先行しがちですが、本質はそこではないのですね。
(大西)そうです。人間のサービスで最も価値があるのは、コンシェルジュのような役割です。
良いホテルが評価されるのは、受付が素晴らしいからではなく、コンシェルジュの対応が素晴らしいからです。
その人たちをどう育成するかが重要であり、接遇がより大事になってきます。
(高山)単なる挨拶の言葉遣いではなく、患者さんがいかに快適に、そして安心して過ごせるかという環境作りそのものが接遇だ、ということですね。
(大西)手を添える、手を触れる、助ける。
それが本当の接遇だと私は思っています。
「歩いている人が困っていたら、手を差し伸べられますか?」と問いかけ、「はい」と答えられる人を雇うべきです。
忙しい時代だからこそ、人々はそういう優しさに飢えているのではないでしょうか。
(高山)特に都会に住んでいると、そう感じるかもしれません。
(大西)無機質であればあるほど、人は寂しさを感じます。
医療機関は本来、優しい場所であるはずなのに、無人化によって無機質な場所を目指してしまっては本末転倒です。
無人受付を導入したいと考えている先生方には、配置転換によって「優しさ」を生み出してほしい。そこを強化するのです。
(高山)なるほど。
(大西)一つノウハウをお伝えすると、人間、特に高齢者は、優しくされるとファンになりやすいのです。
自分の身内に対するように、優しく接することが大切です。
(高山)昔、布団の訪問販売で、優しくされてつい買ってしまった、という話がありましたね。
(大西)そうです。スーパーで品出しをしているスタッフが、高いところの商品を取ってくれる。
そういう些細なことで、そのお店のファンになるのです。
対面販売に近いサービスを提供できれば、クリニックの評価も上がります。
患者中心のクリニック作りへ
(大西)先日、リウマチ専門のクリニックをお手伝いしましたが、リウマチの患者さんは手足が不自由な方が多く、洋服を脱いだり、お金を出したり、字を書いたりすることが大変です。
であれば、そこを重点的にサポートすべきなのです。
(高山)自分の業務に集中するのではなく、患者さんをよく見て、患者さん中心のクリニックを作っていく、ということですね。
(大西)自分の仕事が早い、ということは、必ずしも患者さんにとって良いこととは限りません。
究極的に言えば、相手をしっかり観察し、相手がしてほしいことは何かを考えることが大切です。
(高山)受付の無人化というテーマから、非常に本質的な話になりました。
(大西)それでは、この続きはまた次回にしたいと思います。
(高山)大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
少しでも気に入っていただけましたら、番組のフォローをぜひお願いします。新しいエピソードがいち早く届きます。
番組への感想はハッシュタグ「#院長が悩んだら聞くラジオ」をつけて投稿いただけると励みになります。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
- 院長の理念と思いやりの心を行動で届けることができる、おもてなし力の高い個人とチームを育成する研修プログラムを提供
- クリニックにふさわしい応対の流れを創るロールプレイを多用した研修
- ホスピタリティにあふれた高品質の接遇を提供していきたいクリニックにおすすめ
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。