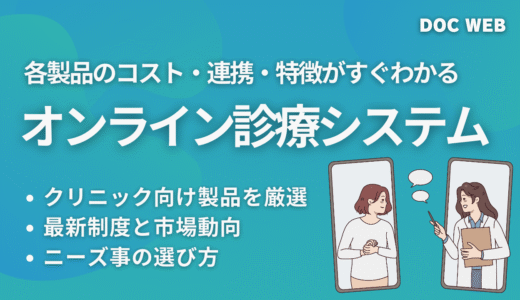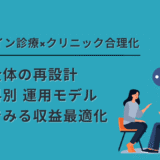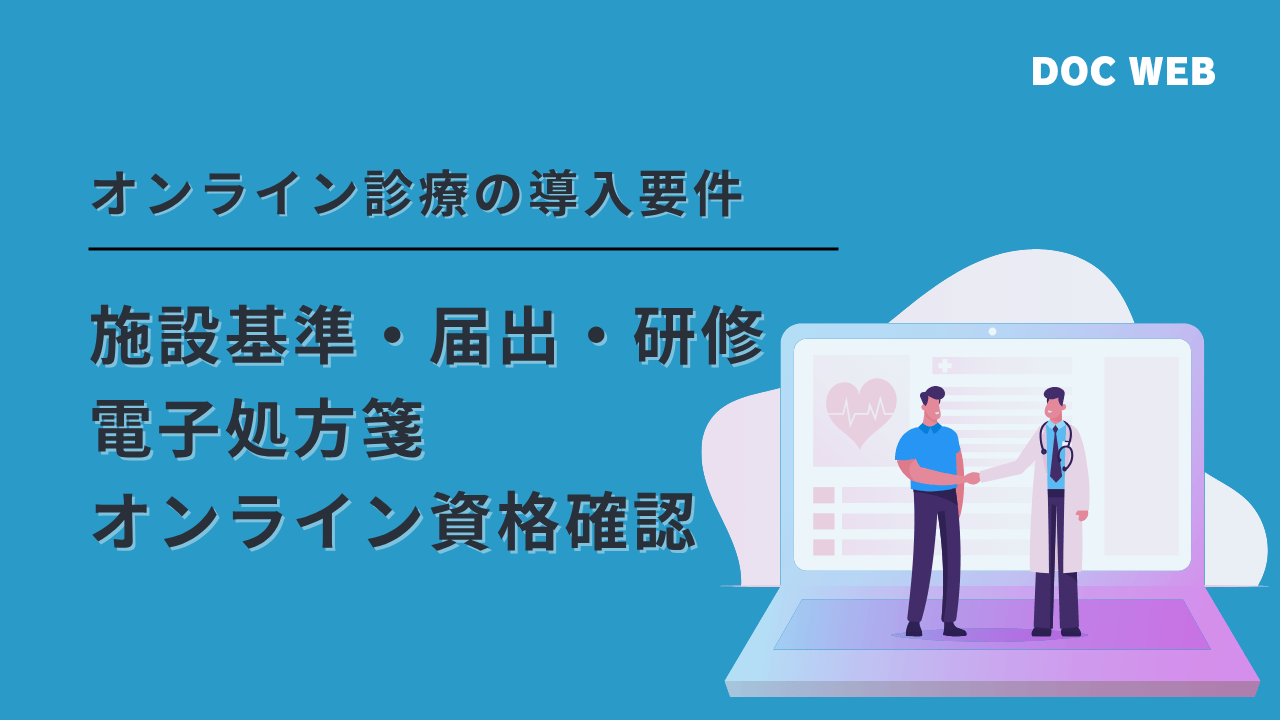
- オンライン診療を導入する際に必要な 制度・届出・研修要件
- 電子処方箋・オンライン資格確認 の仕組みと導入ステップ
- 導入後にトラブルを防ぐための セキュリティ・運用体制
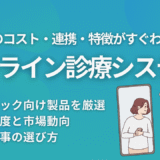 【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)
【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)
制度の枠組み(法的位置づけと指針)
オンライン診療は、医師法第20条・医療法・個人情報保護法のもとで運用される保険診療の一形態です。
厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」が、導入・運用の基準となります。
この指針では、
- 患者・医師双方の安全を確保する
- 医療の質を担保する
- 不適切な過剰診療・形骸化を防ぐ
ことを目的とし、次の5つの領域を定義しています。
- 実施医療機関の要件(届出・研修・体制整備)
- 診療実施方法(通信環境・同意取得・本人確認)
- 診療報酬算定要件(オンライン診療料・遠隔診療管理料等)
- 処方箋・薬局連携(電子処方箋・服薬指導)
- 情報セキュリティ・個人情報保護
出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」
施設基準・届出・研修
オンライン診療を保険診療として算定するには、地方厚生局に施設基準の届出が必要です。
あわせて医師のオンライン診療研修修了証が求められます。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 管轄地方厚生局に届出書を提出 | 「オンライン診療料」「遠隔診療管理料」等、算定項目ごとに届出 |
| ② | 届出書に添付する体制・運用資料 | 同意書テンプレート、緊急時対応フロー、管理責任者の配置 |
| ③ | 医師研修修了証の添付 | 厚労省指定e-learning修了証を印刷添付 |
| ④ | 電子カルテ・通信体制の概要 | 通信暗号化・録画禁止設定を記載(システムベンダー証明可) |
参考:『開業医のためのオンライン診療』より
【研修内容の概要】
- 安全管理体制
- 初診・再診の区分と患者適格性
- 緊急時対応・対面診療移行基準
- 記録保存・同意書管理方法
電子処方箋の仕組み
医師が処方情報を電子署名で送信
↓
電子処方箋管理サービス(厚労省
↓
薬局で処方データを確認
↓
患者にオンライン服薬指導・処方薬配送
この流れにより、
- 処方箋のFAX送信・郵送を不要化
- 患者側の受け取り忘れ防止
- 処方箋の有効期限(発行日+4日)を自動管理
が実現されます。
2025年10月現在、電子処方箋導入済み医療機関は約45%、薬局は95%を超過しており、2025年度中に義務化対象拡大(レセプト電子化対応医療機関含む)が見込まれています。
参考:厚生労働省・電子処方箋運用ガイドライン
オンライン資格確認と本人確認の流れ
オンライン診療では、保険資格確認と本人認証が必須です。
これにより、なりすまし受診や不正請求を防止します。
【本人確認の方法】
- マイナ保険証(ICチップ認証または顔認証付きカードリーダー)
- SMS・メールによる二段階認証を併用する医療機関もあり
- 録画・録音は原則禁止(指針による)
オンライン資格確認システムを電子カルテとAPI連携させれば、受付〜診療〜会計までを一気通貫で処理可能です。
処方箋:即日/期限/FAXの実務整理
オンライン診療における処方箋の扱いは、「電子処方箋が原則」であり、やむを得ない場合のみFAXによる暫定対応が認められています。
ここでは、導入前に確認しておくべき実務上の要点を整理します。
処方箋発行と受け渡しの基本
| 項目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 処方箋の発行タイミング | オンライン診療終了後、電子処方箋システムを介して即時発行が可能。 | 電子署名付き処方情報が薬局に自動送信される。 |
| 紙処方箋の扱い | 電子処方箋未導入の場合、医師が署名・押印した処方箋を患者または薬局へ交付。 | 郵送・来院受け取りいずれも可。 |
| 処方箋の有効期限 | 発行日を含め4日間(電子・紙共通)。 | 休日をまたぐ場合は患者に期限を説明。 |
FAX送信の暫定対応
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」第5章では、
次のように定められています。
「電子処方箋の活用が望ましいが、やむを得ない場合には、
医療機関から薬局へ処方箋をFAX等で送信し、
後日速やかに原本を送付することができる。」
したがって、FAX送信は特例的な暫定措置と位置づけられ、継続的な利用は推奨されていません。
送信は医師の責任のもと実施され、薬局との間で安全確保策(誤送信防止・送信記録保管)を講じる必要があります。
今後は電子処方箋への移行が基本方針とされており、2025年度までにほぼ全薬局で対応完了が見込まれています。
| 区分 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| FAX送信の可否 | 医療機関→薬局間で一時的に可 | 緊急時・例外的運用のみ |
| 原本郵送義務 | FAX送信後、速やかに原本を郵送 | 郵送遅延は管理不備とみなされる |
| 電子化推奨 | 電子処方箋システム導入が原則 | 厚労省が段階的義務化を予定 |
薬局連携と服薬指導
電子処方箋とオンライン服薬指導を組み合わせることで、患者は受診から服薬までを在宅で完結できます。
民間のオンライン診療プラットフォームでは、服薬指導・薬配送までを一元化した仕組みを実装し、患者の利便性と継続率の両立を実現するシステムも登場しています。
支払い方法とセキュリティ
オンライン診療の支払いはオンライン決済(クレカ・後払い)が主流です。
経理上は「医療報酬と同様の分離管理」が必要です。
また、通信経路・端末・サーバはいずれも「医療情報システム安全管理ガイドライン」に準拠しなければなりません。
- 通信はTLS1.2以上の暗号化
- サーバは国内管理・アクセスログ保存
- 画面録画・録音は禁止
- スタッフ端末もウイルス対策・自動更新必須
よくある質問(FAQ)
条件付きで可能です。かかりつけ患者や慢性疾患を有する患者、または医師が過去の診療情報を把握している場合に限られます。初診時にオンライン診療を行う際は、患者の安全性を確保するためのガイドラインに従う必要があります。
電子処方箋そのものは、無料の公的システム(電子処方箋管理サービス)を通じて利用可能です。ただし、電子カルテやレセコンとの連携を行う場合は、システム改修や追加オプション費用が発生することがあります。
移行期においては、電子処方箋とFAXの併用が認められています。ただし、将来的には医療DXの推進に伴い、電子処方箋への完全移行が想定されています。薬局側の対応状況を確認しながら段階的に移行を進めることが推奨されます。
関連記事リンク
※本記事は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」、
『開業医のためのオンライン診療』『オンライン診療が切り開く地域医療の最前線』、
「患者へのWebアンケート調査に基づいた、オンライン診療および医療機関の電子化のあり方に関する調査研究」
に基づいて作成しています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。