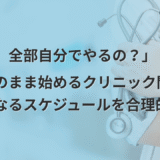PODCASTエピソードはこちら
DOCWEB『院長が悩んだら聴くラジオ』この番組は開業医の皆さんが毎日機嫌よく過ごすための秘訣を語っていく番組です。 通勤時間や昼休みにゆるっとお聞きいただけると嬉しいです。
(高山)おはようございます。パーソナリティのドックウェブ編集長、高山豊明です。
(大西)おはようございます。パーソナリティのMICTコンサルティング、大西大輔です。
(高山)院長が悩んだら聞くラジオ、第72回始まりました。大西さん、今回もよろしくお願いします。
(大西)よろしくお願いします。今日のテーマは何でしょうか。
今回のテーマ:オンライン診療の今後
(高山)前回に引き続きオンライン診療となります。今日は、オンライン診療が今後どうなるのか、国の思惑、そしてクリニックがどう活用していけばいいのかという点についてお話していきたいと思います。
(大西)国というのは、役割的に言うと規制をかける側なんですよ。
だから自由競争を推進するというのは、実は厚生労働省の役割にはないんですね。
(高山)なるほど。
(大西)ですから、国の動きというのは「どうすればリスクが減るか」という考え方に基づいています。
一方で、世の中の動きは「どうすればリスクを減らしながら事業を拡大できるか」という視点です。
利害が逆方向に動くというのが、一つの考え方かなと思います。
(高山)なるほど、面白い視点ですね。ということで、この後後半戦へ行きたいと思います。よろしくお願いします。
(大西)お願いします。
国が目指すオンライン診療のあり方
(高山)オンライン診療ですが、今後、国はどのように進めていく、あるいは規制していくという流れなのでしょうか。
(大西)オンライン診療は、あくまで補完的な意味合いであり、外来診療や在宅医療の補完に過ぎない、という位置づけです。
ですから、決して「外来・在宅・オンライン」というように並列で考えているわけではありません。
そのため当然、オンライン診療が使える範囲を完全に拡大するということは、なかなかないだろうなと思います。
(高山)なるほど。今、クリニックによってはオンライン診療を主軸に展開しているところもあると思いますが、当局としてはそういった使い方はあまり想定していないということですね。
(大西)そうだと思います。イメージとしては、外来診療や在宅医療を行いながら、補完的にオンライン診療を増やしていくという形ですね。
そうなると、利用範囲を限定させるというのが厚生労働省の考え方になります。
前回お話ししたように「ネガティブリスト」、つまり「やってはいけないことを決める」という考え方が正しいのではないでしょうか。
逆に「やっていいこと」を決める「ポジティブリスト」方式だと、対象がどんどん増えてしまいます。
自由競争に保険診療は向かないと考えているようなので、ある程度の制限を設ける方向になるでしょう。
(高山)なるほど。では診療を行う側が自由診療でオンライン診療を行う場合、保険側の規制を全く受けない、自由な世界で展開していくということになりますね。
(大西)そこが厚生労働省にとっても直近の課題になっていて、議題にも上がっています。
例えば、患者さんが直接美容外科に行ってしまうといったケースや、美容医療の世界での様々なトラブルが心配されているわけです。
(高山)そうですね。規制があるからこそ、その枠から飛び出してしまうという側面もありますね。
(大西)規制があるから飛び出してしまう。だから、これまで国は規制を調整しながら、逸脱しないようにコントロールしてきました。
ただ、厚生労働省の思惑とは少しずれるかもしれませんが、医療費が劇的に増えすぎたため、もう引き締めざるを得ない状況になっています。
医療費を抑制するというロジックで考えると、外来患者を減らし、在宅患者を増やし、入院を減らすという従来型の方針になります。
しかし、そうすると現場が「患者が増えすぎた」「在宅が大変だ」と悲鳴を上げてしまう。
そこに、オンライン診療が補完的な役割を果たせるのではないかと期待されているわけです。
(高山)なるほど。本来やりたい本筋の医療政策を進めるために、補完的にオンライン診療を組み込むことで、現場の先生方の理解を得ようという考えですね。
(大西)そうですね。すると、例えば花粉症や高血圧の薬のように、特に詳しい検査をせずに定期的に処方しているリピートの薬などは、オンライン診療に移行させようという流れになります。
また、検査結果を聞くだけといったケースもオンライン診療に向いています。現場ではそのように考えられています。
そうなると、儲かる・儲からないという視点ではなく、本当に外来で診るべき人とオンラインで十分な人とを「仕分けする」という視点に変わっていくのではないでしょうか。
そして厚生労働省としては、「儲からないからオンライン診療をやらない」という状況から、「患者さんが溢れているからオンライン診療をやる」という方向に変わっていくと、理想的だと考えていると思います。
(高山)そうですね。人口動態を考えれば、いずれそうなるはずですが、まだそうなってはいないこれから急激に変化していくという感じでしょうか。
医療従事者の高齢化とオンライン診療の担い手
(大西)その変化の一つの鍵が、医療従事者の高齢化だったようです。
要は、クリニックを運営している側が年配のため、オンライン診療についていけないという現実があります。
一方で、オンライン診療の主な対象となる患者さんは20代や30代の若い世代です。
そうすると、30代ぐらいで開業する若い先生たちは、その層をターゲットにオンライン診療を展開していきます。40代、50代、60代の先生たちは外来診療が中心です。
この流れの中で、アルバイトを雇ってオンライン診療部門を運営するというような形態も出てくるのではないでしょうか。
(高山)なるほど。得意な人に任せていこうということですね。
(大西)そうです。受付業務をコールセンターに委託したり、中にはずっとLINEの返信だけを担当するスタッフがいるようなクリニックもすでに出てきています。
横で見ていると少し不思議な光景ですが、モニターにLINEの画面を映して、ひたすら返信作業をしているんです。
ただ、その際の返信の仕方一つでトラブルになることもあり、LINEでのコミュニケーションは日本語力が非常に重要になります。
(高山)大事ですね。なるほど、LINE版のコールセンターのようなイメージですね。
(大西)電話は向いていません。若い世代は電話を嫌いますから。
(高山)そうですね。我々の世代が「面倒くさいから電話してしまおう」と考えるギリギリの世代かもしれません。
(大西)ですから、今後は「SNSセンター」のようなものが主流になってくるでしょう。
例えば、飲食店を予約する際に、時間がない時はネット予約を使い、時間がある時は電話をかける。でも電話が繋がらないとイライラしますよね。
(高山)繋がらないですからね、飲食店は。
(大西)それとクリニックも同じです。電話が繋がらないとイライラする。それならLINEの方がいい、ということで「LINEコールセンター」のようなサービスが出てきました。
これがオンライン診療と非常に相性がいいのですが、その分、問い合わせの数が膨大になります。
決済方法の多様化と課題
(大西)少し脱線しますが、支払い方法一つとっても、クレジットカード、QRコード決済、PayPayなど多様化しています。
基本的にはクレジットカードはオンラインで利用できます。交通系ICカードやPayPayは接触が必要ですが、ネット決済に対応した後払いや前払い、即時払いなど、支払い形態は山ほどあります。
世の中には色々なことを考える人がいるなと思います。
(高山)そうですね。決済方法が非常に多いため、その全てに対応しようとすると、システムの利用料も高額になりますしね。
(大西)カードがメインで他はサブだろうと思っていたら、PayPayがメインという人もいますからね。
「お小遣いはPayPayでもらっています」というような。医療機関側としては、あまり対応しすぎても良くないかなという感じがします。
(高山)そうですね。ある程度、決済方法が収斂されるまでは、少し様子を見た方がいいかもしれません。
(大西)クレジットカードだけでもいいのではないかと、個人的には思っています。
そのあたりのやり取りもLINEで行われているわけですね。「何が使えますか」とか、「今、現金がないので後払いでいいですか」とか。
そういったやり取りを見ていると、人間の欲はすごいなと感じます。「お金はないけれど、薬は欲しい」と。
(高山)そういう方向けに、自治体や国が発行するクレジットカードやプリペイドカードがあってもいいのかもしれないですね、今後は。
(大西)うーん、ただ自治体独自のものだと、また新しいシステムを構築しなければなりません。
難しいところですが、薬を必要としている人が、必ずしも支払い能力があるとは限らない。
非常に難しい問題です。医療機関は、あらゆる人を相手にしていますから。
その現実が、オンラインだとより露骨に現れるという感じがします。
なるほど。外来であれば、保険証とは別に生活保護や公費、子ども医療費助成といった制度があり、顔を見て判断できます。
しかしオンラインの場合、極端な話、カメラをオフにされたらどうしようもない。本当は禁止されていますが。
(高山)そうですね。「電波が悪いので」と言ってカメラをオフにされたり。
(大西)すると、保険証の本人とは全く違う人がそこにいる、という可能性もゼロではありません。
(高山)それを確かめる術がないというのは、大きな課題ですね。
なりすましリスクと本人確認の重要性
(大西)「顔が違うようだ」と指摘しても、保険証に顔写真がなければ確認できません。マイナンバーカードであれば顔写真がありますが、そのやり取りも簡単ではない。
初診からオンライン診療をOKにするのは、非常に大きなリスクを伴います。
だからこそ、なりすましを防止するために「本人確認をしてください」というルールがあるわけです。
(高山)そこはもうマイナンバーカードを使うしかないのでしょうか。
(大西)そうですね。自宅でマイナンバーカードを読み取れるように、今、スマートフォンでの対応が進められています。
iPhoneではFace ID(顔認証)を使って認証し、マイナンバーにアクセスして本人確認をするという流れです。
AndroidはIDとパスワードを使う方式ですね。
(高山)なるほど。現状はまだ使い勝手が悪く、何度もログインを求められることがあります。「一度ログインしたのに、また聞かれた」というような。
(大西)ありますね。クレジットカードの決済も2段階認証が導入されました。
支払ったと思ったらSMSに認証番号が送られてきて、それを入力しなければならない。そのわずか5秒ほどが、とても長く感じます。
(高山)一方で、スーパーでの買い物ではパスワードすら不要で、サインもいらない。大丈夫かと心配になります。このさじ加減が難しいですね。
(大西)金額によるのか、何なのか。
そういった現状を踏まえてオンライン診療の今後を考えると、国は規制をかけたいので、リスクヘッジとして「こういう病気の人、こういう薬を飲んでいる人は対象から除外した方がいい」という規制は今後も続くでしょう。
ただ、本当に困っている人、例えば僻地に住んでいる方や遠隔医療が必要な方々にとっては、利用範囲が拡大していくのではないでしょうか。
また、寝たきりの方の利用も増えていくはずです。在宅の現場でヘルパーさんや看護師さんがいる時に、オンラインで医師とやり取りをするといった活用法ですね。
そうした利用は、今後さらに評価されていくでしょう。そうなれば、オンライン診療は若い人だけのものではなく、アシストしてくれる人がいれば高齢者でも使えるツールになります。
(高山)そうですね。家族がサポートしてもいいわけですしね。
(大西)そうした方向に活路を見出していくのだと思いますが、やはり最大の課題は、このお金周りの問題が厄介だということです。
(高山)そうですね。この辺りが解決されれば、より使いやすいものになるでしょうね。
民間に任せるという手もありますが、サービスがバラバラになってしまう。個人的には、自治体や国が統一したものを作った方がいいと感じます。
(大西)保険診療が後回しにされ、自費診療が優先されるからこそ、自治体が関与してくるという側面もあります。
(高山)自費診療は「ご自由にどうぞ」という世界なので、国も規制しないでしょうし。
(大西)その「ご自由にどうぞ」の世界における規制のあり方を、きちんと考えてほしいですよね。
(高山)そちらはもう医療法しかありませんからね。
(大西)だって、事故は必ず起きますし、トラブルも発生します。例えば、なりすましで薬を仕入れて、その人がまた別のオンライン診療を行っていたら、怖くないですか。
あるいは、医師ではない人がオンライン診療を行っていたら、とか。
(高山)ありえますね。見分けがつかないですから。
(大西)医師免許の番号を画面で見せるわけではありませんし。
(高山)確かに。それなら大西さんでも診察できてしまいますね、オンライン診療で。
(大西)いえ、捕まりたくないのでやりませんけど。
(大西)怖いですね。まるでブラックジャックのような世界が本当に起こり得ますね。しかも、実行する側にとってはリスクが少ない。
(高山)なるほど。リスクの少ないところで善意の顔をして、素人が診察している、という状況があり得るわけですね。
(大西)だからこそ「LINEドクター」はサービスを終了したのかもしれません。なりすましの問題や、利用者とのトラブルなど、色々なことがあったようです。
患者さんの書き込みに対して医師が回答するのですが、それが不適切だったり、それが原因で炎上したり。
もしかしたら、その書き込み自体、医師がしたものではなかったのかもしれない。
そこで今、国が考えているのが、医師版のマイナンバー、つまり電子処方箋を発行するための医師資格証(HPKIカード)です。
これを保有していなければオンライン診療ができない、という仕組みにしようとしています。
(高山)そうですね。そうしないとダメでしょうね。タバコだってtaspoがなければ買えませんでしたし。
(大西)でも、今はコンビニで免許証を見せれば買えますからね。taspoはどこへ行ったのやら。
ただ、このなりすまし問題というのは、お金の面でも薬の面でも、今後もずっとついて回る課題だと思います。
(高山)そうですね。本人確認は、どこまでいってもいたちごっこですね。全く違う話ですが、法人の登記簿は誰でも取得できますが、印鑑証明だけは法務局で印鑑カードを見せないと発行してもらえません。
(大西)ありますね。
(高山)個人の場合はマイナンバーカードでコンビニでも取得できますが。
(大西)法人の印鑑証明だけはダメですよね。
(高山)そうなんです。しかも、そのカードを窓口で見せるだけで、機械で読み取るわけでもない。見て終わりなんです。
(大西)じゃあ、そのカードを貸したら、誰でも取れてしまいますね。
(高山)そうそう、貸したら終わりなんです。怖いなと思います。
(大西)選挙も同じじゃないですか。投票所の受付担当者は、投票用紙の引換券を見て、私の顔は見ていない。
(高山)そうそうそう。
(大西)「大西大輔さんですね、どうぞ」と。何もチェックしていない。あそここそマイナンバーカードを使うべきだと思うんですけどね。
(高山)本当ですね。
(大西)笑ってしまうくらい、この本人確認の大変さが、そのままオンライン診療の大変さに繋がっていると、僕は思っています。
(高山)そうですね。これは社会全体の仕組みとして考えていくべき問題で、マイナンバーカードはやはり必要不可欠ですし、スマートフォンの重要性もますます高まっていきますね。
(大西)国はマイナンバーカードを普及させたいのであれば、もっと便利な使い方を提案すればいいのに、と思います。
(高山)そうですね。マイナンバーカードで選挙ができるようにするとか。
(大西)リスクはあるのでしょうけどね。面白い話ですが、もしマイナンバーカードで選挙ができるようになると、若者の投票率は上がり、高齢者の投票率は下がるんですよ。
(高山)ほう。
(大西)マイナンバーカードは、年齢が上がるほど普及率が低いからです。おそらく80歳以上の層では、かなり低いでしょう。
だから自民党はマイナンバーカードでの選挙に踏み切らない、なんて話もあります。
(高山)あまりそこを突っ込んでいくと、大西さんの身の上が心配になるので、この辺にしておきましょうか。
ということで、続きは次回にしたいと思います。大西さん、今回もありがとうございました。
(大西)ありがとうございました。
この番組への感想は「#院長が悩んだら聴くラジオ」でXなどに投稿いただけると嬉しいです。番組のフォローもぜひお願いします。
この番組は毎週月曜日の朝5時に配信予定です。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。
クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。