目々澤 肇(めめざわ はじめ)
東京都医師会・理事
経歴 1981年に獨協医科大学医学部卒業。スウェーデン・ルンド大学医学部実験脳研究所へ留学している。日本医科大学千葉北総病院でSCU(脳卒中救急ユニット)立ち上げを行ったのち、1933年から続く目々澤醫院(東京都江戸川区)の第3代目院長に就いた。 東京医師会医療情報担当理事、地域包括ケアシステムの実現に必要なICTネットワークを構築している。東京都・日本医師会と協調を保ちつつ現場医療を最優先している。ICTを使いこなし、毎日の診療に励む。
65歳以上が3人に一人、75歳以上が7人に一人という超高齢化社会を迎える2025年問題を見据えて医療、介護、福祉のサービスの整備が急務である。東京都医師会は住み慣れた地域で、自分らしい生活ができる地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域の医療機関と介護サービス事業者の連携を密接にし、安心安全にサポートできる体制づくりを目指し、東京都の地域医療を支援する「東京総合医療ネットワーク」を構築している。
最前線で医療ネットワーク構築を指揮、活動している目々澤氏に医師会での取り組みや現状の課題について話を伺った。
東京都医師会の電子カルテ連携への取り組み
電子カルテを使用している医療機関は約半数に増えましたが、地域医療の連携を活用している医療機関は、その中でさらに、約2割に留まっていると調査の結果が出ています。連携を普及する上での障壁の一つが異なるベンダーの電子カルテを参照できないことでしたが、地域医療連携システム構築検討委員会の検討で「PIX/PDQを用いたIHE規格に基づくデータセンター間接続」であれば大がかりなサーバーを設けなくても参照できることがわかりました。
そこで、都内で約80%のシェアを占める富士通、NEC/SEC二社の電子カルテ連携システムを利用している病院間で実証実験を実施し、相互に電子カルテを参照できることを確認しました。
この結果をもとに、病院間で電子カルテを結ぶ「東京総合医療ネットワーク」の組織作りが進められ、東京都の支援を受けて運営協議会を設立し、連携参加を検討している病院への説明会やモデル病院におけるテスト連携などが実施されました。昨年11月の実稼働開始後は普及に向けてさらに活発に活動を行っています。
また、電子カルテネットワークへの参加に必要な連携システムの導入に関しては、東京都の補助事業において、新規導入やバージョンアップのための費用が半額補助の対象となっています。現在、東京総合医療ネットワークでは二社の電子カルテ連携システム間で処方薬・注射内容・血液検査結果の相互参照が出来るようになり、さらに第三のベンダーの参入や閲覧施設としての診療所の参加についても検討を始めました。
今後の課題としては、画像の連携が大切ですが、それぞれのメーカー同志の病院間ではMRIなどの画像を参照し合うことはできるのですが、メーカー間の相互参照可能には至っていません。また、全都内での普及・運用に至るまで時間がかかります。
このような電子カルテネットワークが将来高度に整備されると、一刻を争う救急の場合患者の氏名、性別、生年月日などから過去の受診歴や投薬内容も照会できるようになります。そこまで進化すれば、医師とスタッフの負担が軽減され患者さんの効率的かつ迅速な診療につながります。こうしたカルテ開示の議論をしていて一番の障害になることが、「ほかの医師に自分の記録を見せたくない」という姿勢がまだまだ残っている部分があることです。ここから脱却していかないと患者さんのための連携にはなりません。
ICT・AIを活用した業務の効率化
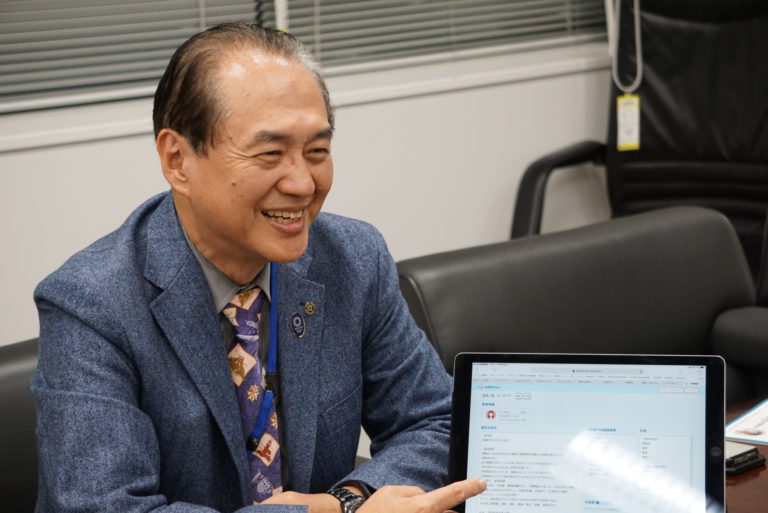
一般診療において、特に慢性頭痛の問診についてはICT化が効果的であると考えています。当院で使用しているWEB問診では、タブレット上の問診アプリが表示した質問に患者さんが選択肢を選ぶ形で返答すると、その内容に応じ患者さんの診断に必要だと推測される次の質問をAIが判断して表示します。この問診結果から、AIが可能性の高い病名を列挙する仕組みです。
その問診の情報が医師側のパソコン端末に表示され、医師はそれらの情報を参照することにより、問診に必要以上の時間を割かず、効率よく診察することが可能になります。AIが整理した問診情報は電子カルテにあたかも医師が書いたかのような文章を貼り付けることができ、カルテ作成記載に割く時間を短縮できます。効率的な診療が可能になることで、純粋な診察や病気の説明に時間をかけることができます。
AIが今の日本の医療を変えていくことは間違いありません。海外では、AIは問診ばかりでなく病理診断やX線読影の実用化、さらにはゲノム医療への応用に向けて、大企業による参入ばかりでなく数多くのベンチャー企業も生まれています。
また、DtoD(医師同士)のコミュニケーションにICTを導入し便利にすることで、医療行為を効率化できると考えています。例えば、今まで見たことのない症状があったとき、また早急な処置の必要性があると思われる事例に遭遇したときに使う医療関係者のためのチャット形式コミュニケーションアプリがあります。
これらは、医療機関のシステムと直結させることはできませんが、院内撮影したCT、MRI、X線、心電図などデータを匿名化した上で指導医のモバイル端末で確認することができるアプリもあります。そして、指導医の判断を仰いで現場の担当医師が治療を開始したり患者転送に踏み切るなどの判断を診療することができるようになります。
医療現場での課題
いま、ICTを医療の現場で利用する上で気になる問題点は、「BYOD」(Bring your own device、私的デバイス活用、個人所有の携帯用機器を職場に持ち込み、業務使用すること)が原則として認められていないことです。東京都内では他県に先駆けて医療介護連携のサービスが都内数カ所で約7-8年前にはじまり、その後行政からの補助金事業が始まったという経緯から多くの地域でBYODによる医療介護連携が運用されています。育ってきた連携をさらに推進していくために医師会は行政と協調し、現状をふまえた法整備を積極的に働きかけていきます。
最近では、第四世代のアップルウォッチの血圧計心電図機能について、日本医師会への要望を行いました。アメリカのFDAでは認可されており、アメリカで販売された個体(個人輸入でもよい)であれば日本でも心電図機能がとれる状態にもかかわらず、日本国内でのモデルでは利用できません。この辺りは政府の動きが鈍く、米国アップルも嫌気を感じて日本導入を見送りそうな原因でもあります。私自身は予期せず発生する不整脈に気づくための個人の目安として用いられるのみであれば健康増進に寄与することになるため、認可基準をより緩和すべきであると考えています。
未来の診療像(AIクリニック)
患者さんが医師の前に座り、問診が始まればその内容が音声認識され、打聴診や触診に進めばカメラにより動作が認識されてAIが音声・行動を解釈して、電子カルテに指を触れることなく文章として自動的にカルテに書き込まれるという技術的発展を期待しています。具体的には、患者さんの触診の結果によりある部分に痛みがあるとしたら、痛い、と言った患者さんの言葉に自動で反応し、なおかつカメラに収められた映像から正確な部位を同定し、カルテに文章として書きこまれる、といった具合です。
医師の診療時間外の作業は診療報酬請求業務や診断書・意見書などの公的書類の作成にあります。病院・診療所の運営業務の効率化は、電子カルテなどのICT機器を基盤としてAIを効率的に用いれば意外に簡単にできる可能性があります。医療従事者が患者さんと向き合い、集中して真摯に医療行為を行うためにICTやAIのさらなる進化が必要と考えます。
医療関係者と患者、相互利益のためのICT・AIとネットワーク
診察までの待ち時間、診察や検査、会計とさらに薬局で待たされ、往復の時間を含めると病院での受診は1日がかりになります。しかし、近所のかかりつけ医の診療所、あるいはICTを用いたオンライン診療で、数十分ぐらいで全てが終わるということになれば、患者や家族にとっても、負担も少なくなっていきます。そうした身近な診療所が大病院も含む医療ネットワークに直結できていれば健康管理の安全度も高まり、効率的かつ適切な医療を受けられることに繋がります。
そのような観点から、医療機関の運営、医療者の仕事の変革、そして何よりも病気の早期発見と治療への道にICT・AIの利用が役立つことには間違いないと思います。
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。

