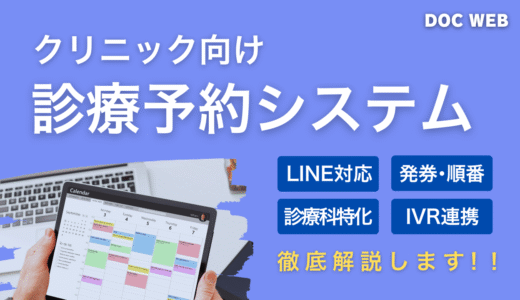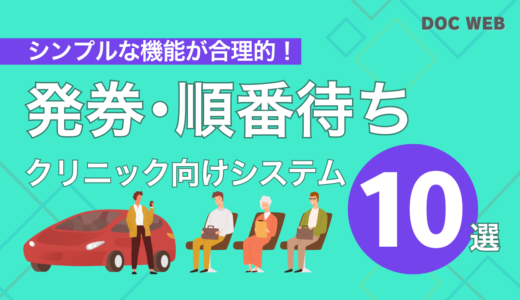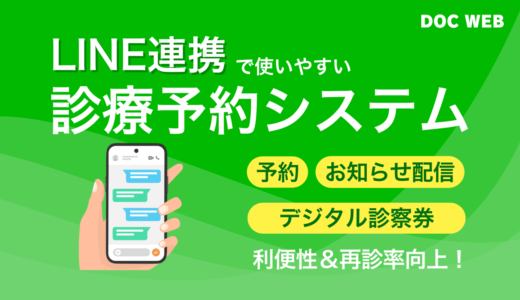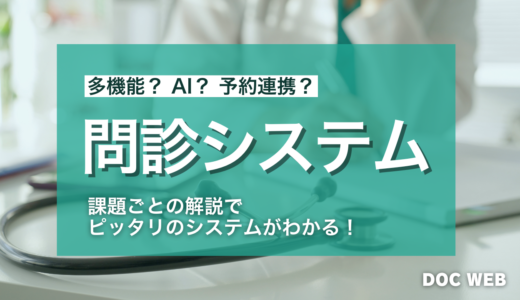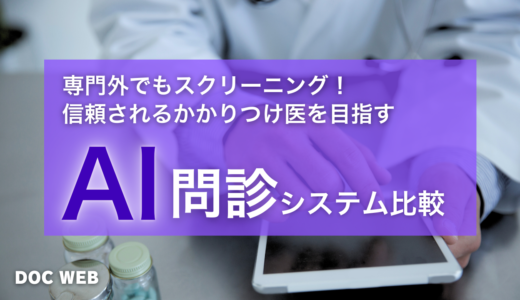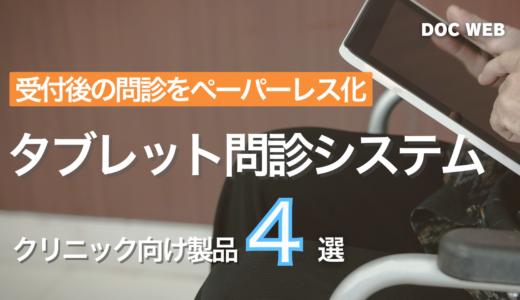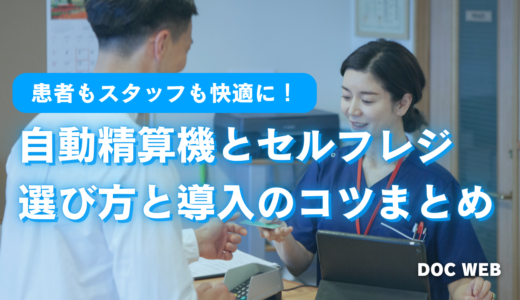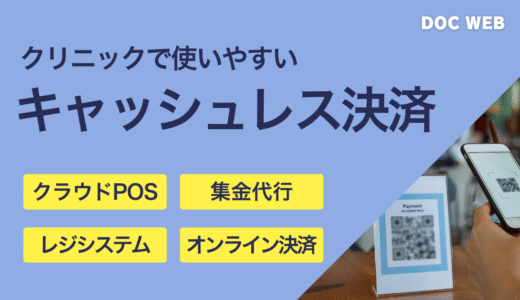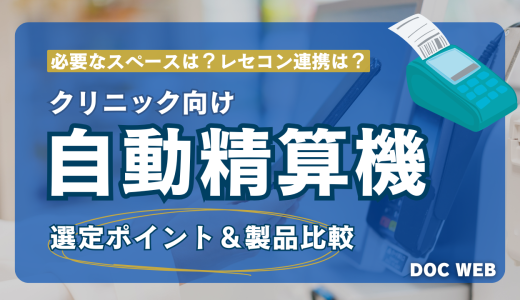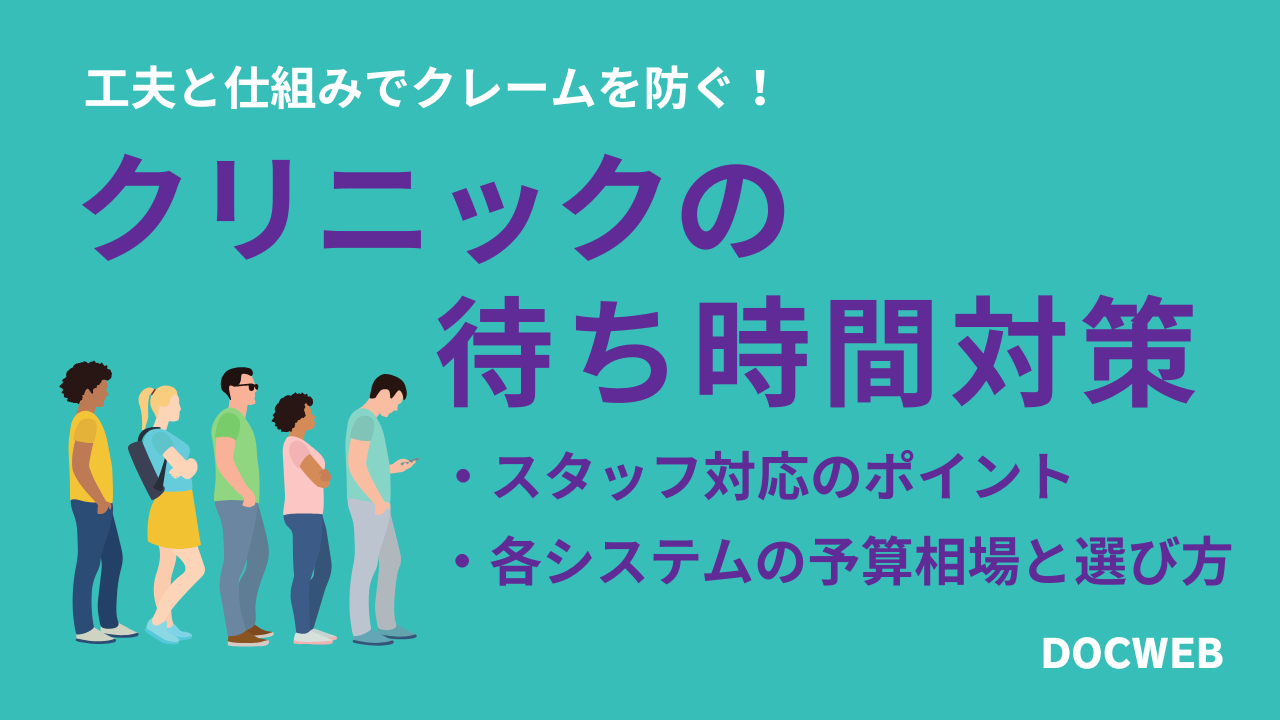
患者の不満やクレームの原因第1位は、診察までの待ち時間です。
しかし、これを「急ぐ」などの意識付けだけで解決しようとすると、診療の質の低下に影響がでてしまいます。
本記事では、予約・問診・会計といった仕組み化による効率化と、スタッフによる案内や接遇の工夫で、
開業時に準備できる費用に合わせ、待ち時間の不満を最小化する方法を解説します。
なぜ今、クリニックの「待ち時間対策」が重要なのか?
クリニックを新規開業する際、多くの医師が注力するのは診療内容や設備ですが、実際の患者満足度に大きく影響するのが「待ち時間」です。特に初診時の印象は、その後の再来院や口コミ評価に直結します。
厚生労働省「令和4年 受療行動調査」によれば、外来患者の約70%が「30分以内の診察開始」を希望している一方、待ち時間の長さは医療機関への不満の最上位にも挙げられています。
このギャップを放置すれば、初診患者の離脱やクレーム発生につながるため、開業時からの戦略的な対策が重要です。
データで見る|患者が医療機関の待ち時間に感じている不満とは?
診察までの待ち時間の平均は?
多くの患者が、医療機関の「待ち時間」に対して不満を抱いています。
特に問題視されやすいのが、診察までの待ち時間です。
厚労省の外来患者調査(2023年)によれば、診察までの待ち時間は以下のとおりです。
| 待ち時間 | 実際の割合(病院全体) |
|---|---|
| 15分未満 | 27.8% |
| 15〜30分未満 | 24.8% |
| 30〜60分未満 | 20.6% |
この結果から、全体の約7割が「1時間以内に診察を受けている」ことがわかりますが、裏を返せば約3割は一時間以上待たされているということでもあります。実際、「診察までの待ち時間」は外来患者の不満理由で最も多く、25.5%にのぼります。
診察後の会計待ち時間もクレームが出やすいポイント
一方、診察後の会計待ち時間も別の大きなストレス要因です。グローリー社の調査では、患者の73%が「会計の待ち時間がストレス」と感じており、「10分以内で終えてほしい」と考える人が大多数でした。
このように、診察前・診察後の両場面で「できるだけ待ちたくない」というのが患者の本音です。加えて、「口コミと実態が違う」「診療時間がWebと異なる」といった情報のズレによる不満も目立ちます。
クリニック経営では、待ち時間の短縮と情報の正確性の両立が、患者満足度向上のカギを握っています。
スタッフの工夫で防げる待ち時間クレーム|声かけで不満を解消する
システム導入に先立ち、スタッフによる対応力と案内の工夫でクレーム抑制と体感待ち時間の短縮が可能な場合も多くあります。
以下は、DOCWEB Podcast「受付の構造から見るクレームの原因と対策」の内容をもとに、現場でできる工夫をまとめたものです。
出典:DOCWEB Podcast 第17回「受付の構造から見るクレームの原因と対策」
患者が「事前に知りたい情報」とは?
患者は「どのくらい待つのか分からない」ことに強い不安を感じます。
この不安を解消する最も効果的な方法が、見通しのある声かけです。
「●分ほどお待ちいただきます」
「●番の方が終わり次第ご案内します」
といった時間の目安+進行状況の説明があるだけで、クレームの発生を大きく防ぐことができます。
診察をスムーズにする「受付での一言」
待ち時間を短くするためには、診察の効率化も欠かせません。
その第一歩が、受付時に目的を確認しておくことです。
たとえば
- 「今日は薬の継続処方ですね」
- 「発熱がありますか?」
といった情報をスタッフが事前に医師へ共有することで、診察の準備が整い、無駄な確認が減るため、診察時間が短縮されます。
結果的に、後続の患者の待ち時間削減にもつながります。
「待たせない」より「納得して待ってもらう」
全ての患者を時間通りに診察するのは難しい場面もあります。
だからこそ重要なのは、患者が納得できる状態をつくることです。
- 待ち人数や目安時間の掲示
- 定期的な状況報告
- 簡単な会話や気配り
こうした工夫が「ちゃんと気にかけてくれている」という印象を生み、“体感”の待ち時間を短縮します。
声かけと案内の工夫だけでも、クレームはある程度予防できることがあります。
まずは現場スタッフの対応力を見直すことが、患者満足度向上への近道です。
仕組みで差がつく|クリニックの待ち時間対策と診療効率アップの方法
スタッフの案内や接遇の工夫は、患者の不満を和らげる大切な要素です。
しかし安定した診療体制を築くためには、工夫に加えて仕組みの導入も考えていく必要があります。
特に開業を控えた医師にとって、待ち時間をどう設計し、どう効率化するかは経営に直結するテーマ。
患者満足度だけでなく、スタッフ負担の軽減、クレーム予防、再診率の安定化にも関わる重要な施策です。
以下では、クリニックで実践できる待ち時間対策を、費用目安と導入のポイントを交えてご紹介します。
まずは、導入しやすい順に予算感を整理した表をご覧ください。
クリニック待ち時間対策ツールの費用比較表(開業時の検討にも)
| 対策カテゴリ | システム名 | 初期費用(税込)目安 | 月額費用(税込)目安 | 特徴・導入時の要チェックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 来院調整・受付混雑の緩和 | 予約システム | 0〜20万円 | 5,000〜15,000円 |
・時間帯予約・順番受付・LINE対応など豊富な形式 ・電子カルテ連携の可否は必ず確認 |
| 診察効率化・医師負担軽減 | オンライン問診 | 0〜10万円 | 3,000〜10,000円 |
・事前情報取得により診察の無駄を削減 ・高齢者配慮として紙との併用も検討 |
| 会計業務の効率化 | 自動精算機 | 80〜150万円 | 0〜10,000円 |
・セルフ精算によるレジ前の混雑解消 ・設置スペースと決済対応範囲を事前確認 |
※ 上記は2025年時点での参考価格帯です。実際の費用はサービス・機能・契約条件により変動します。
大切なのは、患者属性・診療スタイル・スタッフ体制に応じてカスタマイズすること。自院に合った「仕組み+工夫」を選定することがポイントです。
予約システムで来院数のコントロール
時間帯予約や順番予約を導入することで、混雑の波を平準化できます。
また、クリニックによっては順番待ちシステムのみの導入が効果的な場合もあります。
LINE連携型や再診予約の自動化など、患者・スタッフ双方の負担軽減に有効です。
POINT:電子カルテとの連携可否を事前に確認しましょう
診療予約システム・発券順番待ちサービスをもっと知る
オンライン問診で診察の事前準備を効率化
患者情報を事前に把握できることで、診察時間を短縮し、医師の問診負担も軽減。
特に初診患者の所見聴取がスムーズになり、待ち時間の圧縮に貢献します。
高齢層には紙問診との併用も視野に検討しましょう
オンライン問診サービスをもっと知る
自動精算機で会計のボトルネックを解消
診察がスムーズでも、会計窓口で混雑が発生すれば、最終的な患者満足度が下がる恐れがあります。
自動精算機を導入すれば、会計時間の短縮だけでなく、金銭トラブル防止やレジ締め効率化にもつながります。
POINT:電子マネー・クレカ対応機のニーズが高まっています
自動精算機・自動釣銭機についてもっと知る
待合室の「体感待ち時間」を減らす工夫
「何分待ったか」よりも、「どう感じたか」がクレーム発生を左右します。
Wi-Fi・雑誌・給茶機の設置だけでなく、デジタルサイネージによる呼び出し案内や健康情報の配信も有効です。
また、現在の待ち人数や呼び出し順を表示することで、患者の不安軽減と納得感向上が期待できます。
ドクターズクラークの活用と業務分担の見直し
医師がカルテ入力や事務作業に追われると、診察1件ごとに数分の遅れが蓄積します。
クラークが入力を代行することで、医師は診療に集中でき、1人あたりの診察時間が短縮されます。
また、受付・会計スタッフの増員や、再診予約の徹底なども、業務フローのボトルネック解消に直結します。
現場で実行できる!待ち時間改善ステップ
- 現状を把握(1日平均待ち時間・ピークタイム分析)
- 課題の見える化(混雑やボトルネックを図にする)
- 小さな改善から着手(予約導線の整備や再診予約の徹底)
- システム導入で仕組み化(予約・問診・精算の連携)
- PDCAで継続的に改善(スタッフと振り返り・患者アンケート)
まとめ|「待たせない」より「不満を生まない」が鍵
クリニックにおける待ち時間対策は、単なる“時短”ではなく、患者との信頼構築の第一歩です。
限られた人員やスペースでも、スタッフの工夫とシステム活用によって、合理化と患者満足度は両立可能です。
開業準備段階から、「待たせない仕組みづくり」を意識することで、集患力と評価を高め、長く選ばれる医院経営が実現します。
【参考】
サイジニア株式会社「病院・クリニック選びに関する全国調査(2020年7月)」
グローリー株式会社「診療費支払いに関する患者・医療事務関係者向け意識調査(2022年4月)」
厚生労働省 医療機能実態調査(病院)2020年/PDF資料「待ち時間厚労省.pdf」
待ち時間対策のよくある疑問
厚生労働省のデータによれば、病院の外来で30〜60分程度が平均的な待ち時間とされています。クリニックでも同等の傾向がありますが、混雑状況により差があります。
予約システム、オンライン問診、自動精算機の導入が有効です。スタッフ対応やデジタルサイネージなど、低コストでできる工夫もあります。
事前の案内や説明、スタッフの声かけで患者の不安を和らげることが重要です。待ち時間の見える化や接遇力向上も効果的です。
待ち時間対策関連記事
開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします
- 開業に役立つ記事・動画が見放題
DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる
手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード
詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。
公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。